頼迅庵の新書・専門書ブックレビュー30
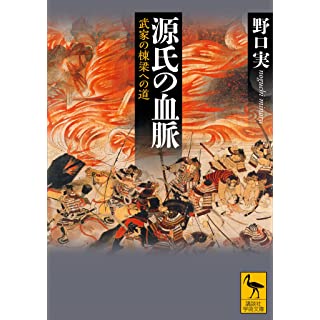 「源氏の血脈 武家の棟梁への道」
「源氏の血脈 武家の棟梁への道」
(野口実、講談社学術文庫)
武家として最も栄えた源氏の代表といえば誰を思い浮かべるでしょうか。武将中の武将として八幡太郎義家を思い浮かべる方も多いと思います。
確かに義家は摂関家に仕え、父に従い前九年の役を戦い、後三年の役を自ら戦い勝利しました。その間、東国の武士たちと情誼的な主従関係を結び、後の鎌倉武士の精神的な支えともなりました。義家こそまさに武家の棟梁にふさわしい人物といっても過言ではないでしょう。
仮に栄光の源氏の代表者を源義家としておきましょう。その義家亡き後、源氏は平家に押されて零落し、頼朝によって再び源氏が栄えるというイメージを何となく持っているかと思いますが、本書はそんな源義家の子為義、その子義朝、そして、草深い板東の武者を組織して京の平家を打倒したその子頼朝と義経という源氏の血脈4人を取り上げています。
ちなみに、栄光の源氏の代表者源義家というイメージについても、実は後世に作られたものだと述べています。どういうことでしょうか?
源氏について、従来の見方を変える最新の歴史学の成果に基づいた専門書ですが、単発で発表された論文を整理、再配置し、4人の略伝を付した本書は、専門書とはいえそれほど難しい内容ではありません。
その第1章は「構想する源為義」です。
為義は義家の子義親の四男とされていましたが、義家の子であるようです。兄たちが不祥事を起こしたため、義家の後を継いで源氏の嫡流となります。
為義といえば、「終生受領に任じられることもなく」「白河院に疎まれて源氏の地位を失墜させ」「保元の乱に敗れて、子息義朝に処刑される」というマイナーなイメージがあります。
しかしながら本書では、それは「貴族社会における家格の低落」によって起きたもので、源氏低迷期に嫡流を継承した為義は、「政治的な不遇のなかで、その打開策を模索していた」と述べています。
具体的には、「遠隔地の武士団の組織化」「各地の宗教勢力との提携を積極的に進め」ることなどでした。そのために、子の義朝を東国に、為朝を鎮西(九州)へ派遣します。
残念ながら、摂関家の孤立、義朝の院への接近によって、為義は不幸へと向かっていくこととなります。
第2章は「調停する義朝」です。
義朝というと、父に背き平清盛を除くべく藤原信頼と提携して自滅する武将というイメージがありますが、院に近侍し、平治の乱後は殿上人に任じられるなど源氏の地位を著しく向上させた人物でもあるようです。
本書では、武家の棟梁とは、「地方武士の要求を中央の政治に反映できる地位に立つ存在として規定されるべき概念で」あるとして、「最初の武家の棟梁は義朝」であると高く評価しています。
義朝は廃嫡されて(弟の義賢が為義の後継者とされた)、少年期を板東で過ごしますが、当時の東国は様々紛争が生じており、義朝はそうした紛争の調停者としての地位を築いていきます。その過程で、国衙を基盤とする在地武士の要求を掴み、摂関家ではなく院へ接近し、保元の乱を経て武家の棟梁というべき地位を築いていきます。
平治の乱に敗れたのは残念ですが、再起は嫡子頼朝に託されることとなります。
その頼朝は、「起ち上がる頼朝」として第3章で取り上げられています。
伊豆に流された頼朝は、20年に及び流人生活を送るのですが、京都の乳母の関係者、母の弟にあたる熱田大宮司家の援助を受けていました。そのため、京の政情の変化は正確に掴んでいまのです。
また頼朝は、平治の乱の最中の除目で、右兵衛権佐という上級貴族の子弟並の官職に任命されています。平家打倒に起ち上がった源氏は、頼朝一人ではありませんが、頼朝が「各地で挙兵した源氏の中でヘゲモニー(主導権)を確立できたのは、このような経歴によって、地方部氏から『貴種』と認められていたところが大きい」と本書では断じています。
第4章は「京を守る義経」です。
義経は義朝の末子です。鞍馬寺に預けられますが、武芸を磨き、奥州の藤原秀衡を頼ります。その庇護のもと、頼朝のもとに駆けつけ、卓越した軍略で平家を滅ぼしますが、梶原景時の讒言などもあり、兄頼朝に疎まれ、最後は奥州で秀衡の子泰衡に討たれる悲劇の武将として知られています。
しかしながら、義経には「海の武士団が多く組織されて」おり、京の貴族や板東の武者ら支援者が多く存在したようです。そのことが「頼朝に義経を畏れさせる大きな背景になって」しまいました。
義経は検非違使尉(判官)に任じられ、従五位下にも叙されています。また、院の御厩司の職務にもついており、在京の武士からも人気があったようです。
なお、終章で、なぜ征夷大将軍は源氏に限られるようになったのか、について考察されています。
今日においては、すでに定説となっているものもありますが、改めて読むと、鎌倉時代幕開けまでの源氏の苦闘が偲ばれる気がします。ここまで頑張り、最後は平家を滅ぼして征夷大将軍として兵馬の権を一手に握るのですが、源氏将軍はわずか三代で滅びてしまいます。
そこに歴史の無情を見るか、無常を読み取るか、歴史の面白さを感じ取るか、それは読者それぞれでしょう。
この時代を描いた小説はいくつかありますが、やはり本作をあげるべきでしょう。第52回直木賞受賞作でもあります。
「炎環」(永井路子、文春文庫)
(お詫び)
私の都合により3週間休載します。次回の更新は7月3日になります。
