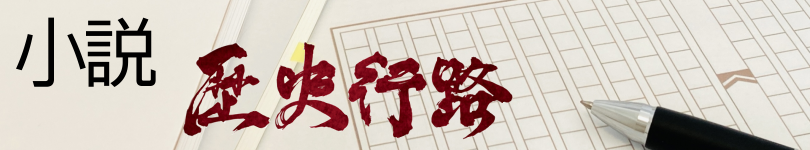飯島一次
一
選りすぐりの醜い女たちであった。
「あそこの女衆(おなごし)は器量が悪いほど給金がええんや」
道修町(どしょうまち)の讃岐屋といえば、富裕な商家の多い北船場でも一、二を争う老舗だが、そんな評判が立つと、並の女たちもなかなか奉公したがらない。そこは口入屋も心得て、山から這い出しの粗削りな女ばかりを厳選して斡旋する。鍋底よりも色黒のお鍋どん。赤ら顔で梅干しのごとく皺くちゃのお梅どん。四角四面で融通が利かず目鼻に凹凸のないお角どん。元女相撲の関脇、一斗釜を楽々と持ち上げるお六どん。上女中から飯炊きの下女にいたるまで、生半可な不美人ではない。
店と奥内とは厳密に区分されているとはいえ、これが紅や白粉を商う家で女中が皆不器量ならば商売に差し支えよう。が、さいわい和漢の生薬を扱う薬種問屋である。店に浮ついた空気の漂いようがなく、番頭も丁稚も軽口ひとつ叩かず、苦虫を噛みつぶしては、ひたすら薬草を分類し加工し荷造りしたので、家業はますます繁盛した。
一人息子の作治郎は珍奇な女たちには目もくれず、物心つく頃から純度の高い小判や丁銀を玩具に与えられ、金銀のこってりとした重量と感触を掌の上で楽しみながら幼時を過ごした。山吹色に輝く上質の正徳小判や享保小判、濃厚ですべすべと吸いつくような丁銀の手触り、薄暗い奥座敷に引き籠もり、畳の上に幾種もの金貨銀貨を分類し、花札ならぬ小判合わせ、敷き並べては金銀双六、小粒を積み上げ豆板はじき、ひとり黙々と飽くことを知らなかった。
「けったくそ悪い。銭の有り余った奴はろくなことを考えんもんじゃわい」
天下の通用金を粗略に扱うなどもっての外、眉をしかめる親類縁者もいたが、讃岐屋が幼い跡取り息子を金銀で遊ばせるのは、驕れる商人の悪趣味ではない。幼少から本物の貨幣に慣れさせ、それぞれの金銀の含有量を色艶や手触りで覚えさせることで眼を養い、真贋を識別できるようにとの配慮からだった。
讃岐屋では過去二代続いて男子に恵まれず、作治郎の誕生は家付娘(いえつきむすめ)である母と祖母を狂喜させた。ただし、実直な性格を見込まれ他家から養子に入った父の佐兵衛だけはさほど喜ばない。娘ならば生え抜きの番頭なり、同業者なり、いくらでも優秀な人材を婿に迎えて家業の繁栄を望めるが、男の子ではこの先どうなることか。
船場の商家は案外につつましい。小判を玩具に与えてはいても、倹約を重んじ、幼い作治郎も母や祖母とともに奉公人と変わらぬ質素な食事に甘んじた。
飯と薄い味噌汁と香の物の朝食、夜には冷飯に野菜の煮付、魚は月に一度だったが、美食の味を最初から知らなければ特に不満もなく、腹八分でもよく噛めば滋養は体内に充分いきわたる。もとより力仕事とは無縁で食は細い。
「これ、なんちゅうもったいないことをするのじゃ。行儀の悪い。お膳の隅にご飯がこぼれているやないか、一粒。そのように汚のう食べ残しては、まるで猫のようじゃな」
好き嫌いを言わず、食べ終えた食器には白湯を注いで舐めるようにきれいにした。
作治郎の祖父であった先代の佐兵衛は、孫の顔を見ることなく卒中で亡くなっている。堅い一方の父とは違い、若い頃から趣味が広く、絵心もあり、茶道、香道、俳諧、謡曲など一通り嗜んだ。作治郎の母が生まれる直前、まだ男盛りの頃、ふと魔が差したものか、奥向に仕える女中との間違いが露見し、懐妊中の祖母が逆上して、母は月足らずで生まれたという。
このたった一度の祖父の過ちが、以後、女中の顔触れを一変させた。不義は御家の御法度、美女は命を断つ斧である。祖父が隠居した後、神経質で几帳面な父はこの慣習を守り通すばかりか、さらに一歩押し進め、家の中にできうる限り不細工な女中を寄せ集めた。
家の中を見目悪き女たちがうろうろするのは、不義密通を防止する以外にも意義がある。いずれどこか利害の一致する釣合いの取れた商家の娘を嫁に迎えなければならないが、親の決めた縁組の相手が、必ずしも好感の持てる容貌の持ち主とは限らない。多少色が黒かろうと、顔が長かろうと、鼻が低かろうと、造作の粗雑な女中で慣らしておけば、少々不細工な嫁でも、そんなものかと得心し、不平不満を訴えることはなかろう。苦労人の佐兵衛はそこまで先を読んだ上で、口入屋に厳しく女中の容貌を注文した。
少年時代の作治郎は異性に特別関心を示さなかった。読み書きの習得に寺子屋に通った以外には、外出を好まず、雨でもないのに昼間から奥の一室に籠もってひとりで遊ぶことが多い。偶然にも古い葛に押し込められた絵草紙や滑稽本を発見したのがきっかけで、読書に夢中になった。葛の中の奇想天外な戯作本は祖父の貴重な遺品であったのだ。手の込んだ料理の味も知らず、醜い女性たちに囲まれて、娯楽の少ない環境で金貨銀貨だけを玩具に暮らしていた少年にも祖父の柔軟な血が流れていたのか、あっという間に滑稽本の世界にのめり込んだ。
祖母など金銭に余裕があるから、つい孫の笑顔見たさに、請われるまま本を買い与えたので、江戸から取り寄せられた黄表紙、洒落本などを所狭しと座敷に並べて、にやにや笑う作次郎であった。
息子の愚にもつかぬ読書を堅物の父が禁じなかったのは、書物の中にしち難しい和学や四書五経の類が一冊もなかったからだ。町人に不相応な学問にかぶれて家業を軽視する気づかいはない。堅実な商人にもさばけた部分は多少必要と判断して、父は息子の道楽を黙認した。
日の当たらない奥の部屋で絵草紙ばかり集め暮らしているうちに、作治郎は色白、下ぶくれ、撫で肩と三拍子そろい、芝居の女形にでもすれば人気が出そうな華奢な青年に育ってしまった。
そうなると、父親は急に心配する。少しは外の風に当てたほうがよかろうが、元来内気で奉公人ともほとんど口を利かないほどだから、気を許す友のひとりもいない。家業を仕込んで鍛えるのが一番だが、讃岐屋ほどの大店ともなれば、有能で信頼できる番頭が店を取り仕切っており、青二才の若旦那ごときに出る幕はない。外に遊びに出して、金のかかる軟弱な道楽は覚えさせたくもないし。
そこで算段したのが、神社仏閣への参詣だった。大坂には由緒ある社寺が多いし、歩くことで適度の運動になる。安上がりの気保養に加えて家内安全商売繁盛を祈願させれば一石二鳥との算盤をはじいた。
「どうや、天神さんへでも御参りしたら」
こうして父に命ぜられるまま、作治郎の社寺巡りが始まった。今日は天満天神、明日は四天王寺に今宮戎、丁稚の定吉ひとりを供に連れてぶらぶらと出歩く。格別に信仰心があるわけではない。最初はさほど気も進まなかったが、続けていると身も心も軽くなる。参拝だけでなく、まわりの風景を楽しんだり、御札や御守りを集めたり、好奇心にかられて御神体の由来や宝物の縁起を調べたり、これが意外と奥が深く、知らず知らずに熱中していた。
「わたい、若旦さんのお供できるのが、何よりうれしおますわ」
丁稚の定吉がいそいそと後に従った。
「ふうん、おまえもなかなか信心深いのやな」
「へへ、茶店の羊羹がうれしおます」
定吉の言うように門前の店で今まで知らなかった美味いものに出会うことも多い。運動量が増えたので食欲も増進する。半年もすると、近隣の名のある神社仏閣で参詣していないところはなくなった。
母も祖母も作治郎の顔色のよくなったのは神仏の御加護とうれしさを隠せなかったが、社寺巡りを誰よりも喜んでいるのは作治郎本人で、手帖に記した神社仏閣の数が増える幸福をしみじみと噛みしめていた。後生は徳の余りというが、こうなると、信心も彼の新たな収集癖を満足させる道楽に過ぎない。
「信心過ぎて極楽を通り越すという言葉もある。ちょっと度が過ぎるのと違うか」
父は顔を曇らせた。自分が勧めた手前、むげに反対もできない。参詣に行こうとする者を引き止めると、止めた人間に罰が下るとも言われている。
軽い風邪をこじらせて作治郎が寝込んだのは、大坂の社寺も巡りつくし、そろそろ堺や河内にまで足を伸ばそうかという矢先のことである。気力がなくなり、食欲も減退し、ついに寝床から立てなくなった。
薬問屋の息子が患いついたとあっては、坊主の不信心、儒者の不身持、外聞が悪い。店にある最上級の高価な薬を処方して与えても、一向によくなる気配がない。そのうち、ふっくらとした頬が痩せこける。もはや世間体をかまっていられず、商売上の付き合いのある蘭学者、橋本曇斎(どんさい)に相談し、門人の蘭方医を紹介してもらった。
結果は芳しくなかった。作治郎を消耗させているのは風邪でも食あたりでもない。心因性のふさぎ病というやつで、それもかなり進行しているとのこと。店中の薬を浴びるほど服用させたところで効果はない。良薬といえども万病に効くわけはなく、誤った匙加減で無闇に薬を与えるとかえって病を重くする。それよりも今は心の中に思い詰めている悩み事を一刻も早く吐き出させなければ手遅れになるというのだ。
原因さえ判明すれば話は早い。佐兵衛は、ふせっている息子にどんな願いでも叶えてやるから申してみよと説き伏せたが、頑として口を開かない。半狂乱の母や祖母が代わる代わる枕元で哀願しても、何を考えているのやら、作治郎は寂しく口元に笑みを浮かべるばかりである。
長町で小さな煙草屋を営む福松屋九郎兵衛が呼ばれた時、作治郎はすでに見る影もなかった。もともと青白い顔色が赤黒くくすんで、両眼は落ちくぼみ、半開きの口からようやく重苦しい息を吐いている有り様だ。
九郎兵衛は佐兵衛の実の弟ながら、目先の投機に走って躓いたり、色町で浪費したりで評判が悪く、近い親戚とはいえ、つい疎遠となりがちだった。が、どういうわけか内気な作治郎と陽気で磊落な九郎兵衛とは馬が合う。気兼ねして両親や祖母には言いかねる内容でも、叔父になら心を割って打ち明けるかも知れない。
「おい、こら、作治郎。チャッとせんかい。いったい、どないしたのじゃ。ええ若いもんがキナキナ思いごとして寝てるなんぞ、今どき、流行りはせんぞ」
大柄な九郎兵衛は座敷に入るなり一喝した。顔つきそのものは佐兵衛に似ているのだが、商人にしては色浅黒く、目つきも鋭い。ぽかんと目を丸くしている付添いの女中に、九郎兵衛はそっと出ていくよう合図した。
「これは長町の叔父貴。えらい御心配をおかけいたしまして」
体内にわずかに残された気力を振り絞るように作治郎は半身を起こそうとした。今にも消え入りそうなか細い声に、これはもう長くなさそうだと、九郎兵衛は思わず眉をしかめ、そのほっそりと弱々しい背中を支えてやった。
「それはそうと、今出て行った女衆」
「お熊が何か」
「ほう、お熊というのか。名は体を現すというが、その通りやな。この家はいつも女衆が凄まじいわい。わしは、ここへ来た晩は必ず夜中にうなされて目が覚める。まあ、そんなことはどうでもええ。それより、おまえ、親の商売を考えてから患えよ。薬問屋の倅が寝込んだやなんて、そんなみっともないことがあるかい」
「面目次第もございません」
「いったい、何があったのや。医者の話では、思てることが叶いさえすれば、嘘のように治るそうやないか。さあ、どんなことか知らんが、思い切って言うてしまえ」
「それが言えるぐらいなら、こんな苦しい思いはいたしやしません。言うて叶うことならば、聞いてももらいます。及びもつかんことを言うたところで、かえって親たちの苦を増すばかり。言うも不孝、言わぬも不孝。同じ不孝なら、このまま黙って死んで行きとうござります」
「難儀なやつやなあ。そこがおまえは若いというのじゃ。おまえは一途に思い詰めてるが、叶う話か叶わん話か、わしが聞いて、なるほどこれはあかんと思たら、この胸三寸に収めて兄貴には決して言わへん。その代わり、わずかでも望みがあるなら、どんなことしてでも叶えてやろうやないか」
「ほんまですか、叔父貴」
「ああ、ほんまやとも」
「叔父貴がそこまで言うてくださるのなら、思い切って申します。決して笑うてくださいますなや」
よしと肯き、九郎兵衛は女中の置いていった煙草盆を引き寄せた。
二十日ほど以前のことである。作治郎は丁稚の定吉を供に連れ、高津神社の絵馬堂前にある茶店で一服していた。高津神社には社寺巡りを始めた昨年の秋に参詣したが、今回は産湯稲荷の帰り、絵馬堂からの春の景色を急に眺めたくなって、高津さんの長い石段を登ってきたのだ。信心よりも社寺の数をこなすのがうれしく、一度参拝した場所には滅多に詣でない作治郎が、引き寄せられるようにやってきたのも何かの因縁であろうか。桜の時節には少し間があり、人は多くない。手を伸ばせば、空一面の白い鱗雲に届きそうだった。作治郎は道頓堀まで一望に見渡せる眺めを楽しみながら、暖かい日射しの中、のんびりと茶を飲み、手帖に向かって参拝記録の文案を練った。
その時である。華やいだ声がして、三人の女が作治郎の斜め向かいに腰を下ろした。作治郎はそれとなく女たちを見る。三人の内訳はひとりが振り袖の町家の娘、ひとりがお供の小間使い、年かさの女は乳母といったところ。二人も供を連れているのは大きな店の箱入り娘に違いあるまい。作治郎の目は自然と娘に吸い寄せられた。年の頃は十五、六、背は高からず低からず、くっきりと色白で、娘らしい恥じらいを秘めながらも、幼い色気を発散させている。作治郎の視線に気づいた娘は頬を赤らめ、にっこりと微笑んだ。作治郎は思わずうつむく。しばらくして女たちは席を立ち、再び華やいだ声を残して去って行った。
それだけならば、別段何事も起こらずに済んだのかも知れない。社寺巡りを始めて、作治郎は世間には美しい女が数多存在することを改めて認識した。が、それらは彼の生活とは何ら関わりのない行きずりの風景に過ぎないとも承知していた。作治郎の日常に密着した女性と言えば、平凡な母であり、年老いた祖母であり、美しくもない奉公人たちでしかなかった。
茶店で向かい合った娘もまた、一言の言葉を交わすことなく、作治郎の前から消えてゆく別世界の幻影なのだ。つかの間の目の保養ができたと喜んで、明日には顔さえ忘れてしまうはかない存在だった。
娘の立ち去った席に目をやり、作治郎は息をのんだ。さきほどまで娘の膝に乗っていたはずの茶袱紗がうかつにも置き忘れてあったのだ。高鳴る胸の鼓動を押さえながら、作治郎はふらふらと立ち上がり、茶袱紗をつかむや、三人連れの後を追った。
「あの、もし。これ、あんたさんのではござりませんか」
作治郎のうわずった声に、女たちはいっせいに振り返った。若い男に声をかけられて娘は怪訝な様子をしたが、彼の手に自分の置き忘れた茶袱紗があるのを認めると、満面に喜びの色をたたえ、じっと作治郎を見つめた。二人の視線が絡みついたのは、ほんの一瞬に過ぎない。作治郎の生涯にこれほど長い瞬間はこれ以前も以後もなかった。
「これはこれは、御親切にどうもありがとさんでござります」
年かさの乳母がしゃしゃり出た。その手をさえぎり、娘は作治郎から直に茶袱紗を受け取った。そのとき、乙女の甘い香りが作治郎の鼻孔を快く刺激した。娘はそのまま茶店に引き返し、紙に何やらさらさらとしたため、作治郎に手渡し、逃げるように去って行った。
つくばねの峰よりおつるみなの川
百人一首にある陽成院の上の句だった。いったいどういうつもりなのか。作治郎はとっさに下の句を思い浮かべた。
こひぞつもりて淵となりぬる
背筋を痺れが走り抜けた。一瞬の恋が積もり積もって深い思いの淵となるという激しい意思表示ではなかろうか。茶袱紗の礼に、娘は恋の歌を自分のために返してくれたのだ。作治郎は夢遊病者のごとく家に戻り、それからは娘のことが頭から離れなくなったというのである。
「なんや、阿呆らし。そういうことやったんか。おまえもそういう年頃になったのやなあ」
九郎兵衛は胸いっぱいに吸い込んだ煙草の煙を、ふうっと一息に吐き出した。
「で、その娘はそれほど別嬪やったか」
「それはもう、菩薩か天女かというくらい、とてもこの世のものとは思えません」
作治郎は苦しい中にも目をぎらぎらと輝かせた。この家の女中を見慣れた目には、たいていの女は美しく映るだろう。思えば罪な家風もあったものだ。
「なるほど。それなら、親に訳を言うて、その娘を嫁に貰たら済むことやないか。お公家のお姫様かお武家のお嬢様ならいざ知らず、町家の娘ならなんとでもなるわい。それにしても、初対面で陽成院の歌を突きつけるとは、なんとも大胆な。で、いったい、どこの何者や」
「それが、皆目……」
あまりのことにぼんやりして、作治郎は相手の名前も家も尋ねなかった。これが世慣れた若者なら、丁稚に女の跡をつけさせ、素性を確かめるぐらいの才覚はあるのだが、あいにく世間知らず、純情一筋の作治郎のこと、再び偶然でも起こらぬ限り、娘に再会する手立てはない。その日から毎日高津神社の絵馬堂に出かけ、雨の日も風の日も一日中、陽成院の歌を頭の中で反芻しながら茶店に座っていたが、娘が現れないまま、風邪をこじらせ寝込んでしまったのだ。このまま一生逢えないと思うと恋しさが募り、病は重くなる一方だという。
銭のあるやつはつまらぬことで患うもんじゃわい、と九郎兵衛は内心舌打ちし、煙管を灰吹に叩きつけた。
「しかし、定吉に跡をつけさせなんだは、うかつなことやったなあ」
「どこの誰とも知れんお人を恋焦がれるやなんて、恥ずかしゅうて親にもよう申せません。この話は、どうか叔父貴ひとりの胸に収めていただいて」
「それは何を言うのじゃ。なんぼ手掛かりがないと言うたかて、供が二人なら、どこぞ御大家の娘じゃろう。讃岐屋の嫁に不足はないわ。こうなったら、大坂中、虱潰しに当たって、見つけ出してみせようやないか」
「そんなら、見つかりましょうか」
「ああ、見つかるとも。大船に乗ったつもりで、わしに万事まかせておけ」
病は気からと言うが、作治郎はまったくの気の病なので、九郎兵衛に思いを打ち明け、胸のつかえが下りたとみえて、その日はぐっすりと眠りにつき、徐々に快方に向かう。
算盤ずくで遊び半分の信仰を勧めたばかりに、一粒種の息子をとんだ目に遇わせたと、弟からひと通りの話を聞いて、佐兵衛は今さらのように臍を噛んだ。とりあえず要因が判明した。が、安心はできない。まさか狐狸に化かされたわけでもなかろうが、どこの誰とも見当がつかぬとなると、これは雲をつかむような話ではないか。
出入りの職人が召集され、手空きの店の者ともども手分けして、船場はもとより、大坂から京、堺、河内、大和、兵庫、紀州と娘をたずねて駆けずり回った。唯一相手の顔を見知っている丁稚の定吉は、それから毎日高津神社の絵馬堂前に陣取り、目を皿にして、せめて小間使いか乳母なりとも現れるのを待った。
いったん回復に向かった作治郎だったが、五日も経つと、今度は以前にも増して病状が悪化した。安請合いで喜ばせて結局相手が見つからぬとあっては、即座に命を落としかねない。必ず見つけてやると引き受けた以上、九郎兵衛の責任は重大だった。
「兄貴、こうなったら一か八かや。ひとつ思案がある。わしにまかせてもらえまいか」
九郎兵衛は堅いだけの兄と違って世俗に通じている。それが尋常な方法でなくとも、このままみすみす殺すよりはと、佐兵衛も渋々ながら承知した。
二
「おい、作治郎。喜べ。とうとう見つかったぞ」
「ええっ」
飛び込んで来た叔父を見て、瀕死の作治郎が息を吹き返した。
「見つかりましたか」
幽鬼のごとくやつれはてた半身を起こし、ぎらぎらした眼で叔父を凝視する。
「で、相手のお方はどこのどなたでござりました」
その凄まじさには、さすがの九郎兵衛もたじろいだが、気を取り直すと、発見までの経緯を話した。
「おまえが貰うた百人一首の陽成院の歌、あれが手掛かりになったのじゃ」
「はあ、あの歌が」
「わしも、ほいほい引き受けはしたものの、いっこうに見つからん。兄貴からはやいのやいのと責められる。正直言うて、おまえがこのまま逝ってしもたら、わしは甥殺しや」
「叔父貴」
「それがやなあ。昨日のこと、たまたま髪結床で陽成院の歌のいきさつを大声でしゃべってる男がいてたんや。さいわいその場に居合わせた手伝い(てったい)の熊五郎が問い詰めると、これが奇遇にも、相手の家に出入りしている大工やとわかった」
「へえ」
「熊五郎が店に走る。兄貴からさっそく報せを受けて、わしが先方へ確かめに出向いた。ええ加減な話で糠喜びさせては、おまえの寿命をますます縮めるだけや。きっちりとことの次第を見極めた上でないと」
「で、どこのどなたで」
「これがその、淡路町の米屋の娘やったんや」
「ええっ、淡路町というたら、目ぇと鼻の先」
「ほんに世間は狭いなあ。その狭い世間で、何のことはない。あちらさんも、おまえを探してござったのじゃ」
「と申しますと」
「先方は大きな米屋の箱入り娘。絵馬堂でおまえに陽成院の上の句を手渡してからというもの、病の床につきなさった。いやがるのを無理やり医者に診せると、これは薬では治らん。なんぞ思い詰めてなはることがあるに相違ないと、こうや」
「へえええ」
「その思いごと、聞き出そうとしても、誰にもおっしゃらん。この娘御と前から心安うにしてた女衆が今は河内の狭山に嫁入りしてる。で、その女衆が呼ばれて、なだめたりすかしたりしてようよう聞き出したのが、つくばねの峰よりおつるみなの川のくだり。作治郎、喜べ。あちらさんでも、どうやらおまえに思し召しとみえるぞ」
「ああ、そんなら今すぐ、淡路町まで」
立ち上がろうとする作治郎を九郎兵衛は制した。
「これ、はやまるな。わしとてすぐにも逢わせたいが、今も言うたように、あちらさんも床についてなさって頭も上がらん様子。おまえもその体で出かけるのは当分無理じゃ。お互い相手が知れたからには、安心して養生に励み、日を選んだ上で、必ず逢わせてやろうやないか」
現金なもので、三日もしないうちに作治郎は健康を取り戻していた。そればかりか、これほど全身に気力をみなぎらせたことはかつてない。自分が見舞いにさえ行けば、相手もすぐに本復するのではないかと、行動に出ようとさえした。だが、叔父は気を持たせるばかりで、なかなか相手に逢わせてくれない。
「これ、作治郎。よう考えてものを言わなあかんぞ。あちらの娘御がどれほどおまえを恋しがってござるか。それはおまえもわかってるはずじゃ。その恋しい男に、病みやつれて痩せ細り、風呂も入らんと垢臭うて、化粧気もない素顔を見られたいと願う娘がどこにいてる」
「はあ」
なるほどその通りなので、作治郎はすごすごと引っ込まざるをえない。
が、ついに吉日を選んで叔父が迎えに来る。この日を待ちわびた作治郎は、朝から着物や帯を選ぶのにさんざん迷い、何度も髪や爪の手入れをし、そわそわと落ち着かなかった。
若い二人の再会の場は難波新地に設けられた。改まって見合いというわけでもないから、親は付き添わず、作治郎は叔父の九郎兵衛と肩を並べて家を出た。
「叔父貴。何やら賑やかなあたりへ出てまいりましたな」
「そうやろ。おまえの快気祝いを兼ねて、景気のええ場所を選んだんやがな。おまえは慣れてるから何ともないやろけど、わしはあの薬臭い道修町はどうもあかん。往来を歩いてるだけで鼻が曲がる。そこへいくと、ここらは匂いからして華やいでるわ。さ、この家じゃ。ごめん」
「まあ、これは福松屋の旦さん。お待ちしておりました」
さほど大きな家ではなく、中から女将らしい中年女が顔を出した。
「久し振りに遊ばしてもらうで。ほら、これが話してたわしの甥じゃ」
「このお方が、例の。はあ、さようでございますかいな。まあまあ、若旦さん、ようおいでくださいました。今後ともどうぞ御贔屓に」
座敷に通されると、酒肴が運ばれる。
「叔父貴、相手のお方は」
「そう焦らんでもええ。じきにお見えになるがな」
飲み慣れない酒を仲居の酌でちびちびやっていると、「旦さん、おおきに」と艶やかな芸者衆がずらりと並んだ。普段なら豪勢に遊ぶのは手控える九郎兵衛だが、今回は讃岐屋という頼もしい後ろ盾があり、心おきなく飲めや歌えのどんちゃん騒ぎとなった。
「ちょっと、叔父貴。相手のお方はどうなってますのや」
「作治郎、茶屋に来てまで情けない声を出すな。おまえもやがては讃岐屋の大身代を継ぐ男や。商売のつきあいもあろうし、下戸では困るぞ。今日は兄貴の許しも得てある。さあ、盃を空けんかい」
「それでも、相手のお方は」
「相手のお方、相手のお方とうるさいなあ。心配するな。ちゃあんと別の座敷に待っていただいておるわ」
「それなら、早う、そこへ御案内いただきまひょう。こんなとこでうだうだ酒など」
「これ、作治郎。常日頃、本ばっかり読んでるくせして、もののあやちのわからんやつじゃな。わしは何も好き好んで酒を飲み、芸子を揚げてるわけやない。その昔、飢饉で米が不足したことがあった。貧者の中には飢える者が仰山出てな。これを哀れに思うて、いきなり飯を恵み与えるとどうなるか知ってるか」
「さあ」
「飢えかつえて弱った人間は米の飯を存分に噛み下す力がない。いきなりこわい飯など食わせたりしたら、いっきに呑み込もうとして、喉を詰まらせ死んでしまうのじゃ。今のおまえは飢えた人間と同じこと。いきなり相手に逢わせたりすると、思いが高まり過ぎて心の臓が止まってしまう。じゃによって、こうして綺麗どころをずらりと並べ、おまえの気持ちをやわらげているのやないか」
「ああ、そういうわけでござりましたか」
作治郎は無邪気に胸を撫で下ろした。
「どうや、酒で邪心を洗い、華やかな芸子衆で目を楽しませて、気分もなんぼか楽になったやろ」
「はい、そう言えば、胸のあたりもほんわりと」
「それでええ。先方も首を長うにしてお待ち兼ねじゃ。そろそろ御対面と参ろうか」
作治郎が通された座敷に待っていたのが、水もしたたるような美女。ただし、根の太いつぶし島田に飛び出さんばかりの櫛や簪、雪を欺くがごとく白く塗られた顔。一見して素人の町娘なんぞではないから、いくら世間知らずの作治郎にも、ここがどういう場所なのか見当がついた。
「どうも様子がおかしいと思うていたが、叔父貴、このお方はいったいどなたや。ここはいったいどういうところや」
「おまえも大坂の人間なら、南地五花街のひとつ難波新地がどういう場所か、知らんわけやあるまい」
「そんなら、高津さんで出会うた娘御は」
「悪う思うなよ。おまえから一件を打ち明けられ、大坂中を隈なく探してはみたものの、当てのない話。とうとう娘は見つからなんだ」
「なんやて。話が違うやないか」
「見つからなんだもんは仕様がない。けど、正直にほんまのことを言うてみい。望みの糸を断ち切られ、おまえはたちどころに死んでしまうやろ。そこで苦肉の作り話」
「そら、あんまりや」
「けど、嘘も方便。おかげで、おまえの病はけろっと治ってしもうた」
「あっ」
たしかに九郎兵衛の言う通り、作治郎は今や完全な健康体であった。道修町からこの難波新地まで、駕籠にも乗らず、足取り軽く歩いて来たのだ。九死に一生の大病人が何の効き目もないうどん粉を高価な妙薬と偽られて与えられ、気を持ち直して回復するようなものである。
「いっぺんは三途の川を渡り損ねたおまえに、この世の極楽浄土を味あわせたる。ほれ、この小輝(こてる)をよう見てみい。これこそ生きた観音様やぞ。おまえが高津さんで惚れた娘、菩薩か天女か知らんが、どっちがきれいや」
小輝と呼ばれた女は顔を上げ、作治郎を見てにっこりと微笑んだ。厚化粧とはいえ、すっきりした目元、絵馬堂での娘の面影と共通したものが確かに感じられる。作治郎が小輝の美しさに引き寄せられるのを見届けて、九郎兵衛はそっと座敷を出た。
さて、こうして作治郎は十八にして茶屋通いを始めたわけだが、現実の肉体を持った美女を抱くことによって、彼の淡い初恋はみごとに消え失せた。行きずりの名も知らぬ女にあれほど恋焦がれたのは、純真ともいえるが、同時に女に対する無知ゆえでもある。人には性欲というものがあり、それを一気に発散してしまうと、絵馬堂での一件は夢から覚めたように霞んでしまった。
考えてみれば、茶店の前で目と目が合ったのも一瞬のこと、言葉を交わしはしたものの、相手の声音すら思い出せない。彼が患うほどに執着していたのは、心の内で美化された夢まぼろしに過ぎないのだ。
恋から覚めた作治郎は現実に向かってたくましく歩み始めた。両親も祖母も叔父も、彼が命を失わずに済んだことに手を取り合って喜んだ。
作治郎は死ななかった。はたして、それは周囲が考えるほど幸福なことだったかどうかは別である。たとえ思いは遂げられなくとも、ひとりの女性を命がけで一途に愛することもまた、かけがえのない幸福なのだ。作治郎が生涯死ぬほど恋した相手は、後にも先にも、絵馬堂で出会った名も知らぬ娘ただひとりだけであった。
難波新地で馴染みとなった小輝は作治郎より二つ下の十六だが、美しさを鼻にかけることもなく、情は濃やかで、気配りも行き届き、作治郎を飽きさせなかった。ことさら淫蕩でもなければ男を手玉に取る毒婦でもない。諸般の事情で苦界に身を沈め、人並み以上の辛酸を嘗めているだけのことである。
若い二人は仮初の恋人として甘美な時を過ごした。肉体の悦楽は作治郎には初めて経験することばかりで、小輝の巧みな誘導により、回を重ねるごとに、一人前の男としての自信を強めるのだった。
奉公人の前でさえ、まともに口の利けなかった作治郎だが、小輝とふたりきりになると、酒の勢いもあり、能弁になった。家族や奉公人の人物評から、少年時代の思い出、好きな音曲、大坂中の神社仏閣へ参詣して見聞したこと、趣味で収集している滑稽本のことなど、話題は尽きない。小輝はさすがに聞き上手だった。こんなにも熱心に耳を傾けてくれる人間は今までいなかったので、時の経つのも忘れてしゃべり続けた。
作治郎が色町に入り浸るのを佐兵衛は苦々しく思いながらも、大事な跡取り息子の命を救うためになら巨万の富を惜しまないと公言した手前、黙認しているしかなかった。たかが青二才の女遊び。女郎は女郎に過ぎぬ。一時の迷い、そのうち目も覚めよう。
やがて、作治郎は一時の迷いから目覚めた。噂で小輝に相思相愛の情夫がいるのを耳にし、愕然となった。娼婦は浮気稼業、色を売るのが商売である。だから、小輝が他の客の座敷を勤めようと、気にしないだけの鷹揚さは持ち合わせているつもりだった。自分だけは特別で、小輝は自分の純情さにほだされ、商売抜きで尽くしてくれているとばかり信じていたのに。男を自惚れさせることこそ女郎の手管であり、自分もまた、操られ金を貢がされているお人好しのひとりに過ぎなかったとは。不思議なことに嫉妬も憤りもなく、素直に現実を受け止めた。
ここで親の前に両手をつき、心配かけてすまなかった、今後は改心して家業に精を出すという方向に行くなら、話はこれで終わってしまう。
作治郎は考えた。小輝ひとりが女でなし、難波新地ばかりが色町でもない。五花街というだけあって、南だけでも宗右衛門町、九郎右衛門町、櫓町、阪町、北には曾根崎新地もあり、遊ぶところは数知れない。しかも、大坂には京の島原や江戸の吉原に匹敵する格式の高い新町の廓がある。せっかく習い始めた色の道、とことん修業を積むとしよう。
三
放蕩に耽る以前の作治郎は、身代を守ろうとする父親の涙ぐましい努力によって巧妙に女性の誘惑から遠ざけられていた。周囲に恋の手ほどきをしてくれそうな多情な小間使いや艶めかしい縁者に恵まれず、遊里に誘ってくれる悪友もないまま、とうとう、十八の歳まで色の道に無縁だった。当時の風潮からすると、奥手、遅咲きであろう。
ともかくも、死の淵から這い上がり、作治郎は生まれ変わった。彼はもはや、内気で女と口も利けなかった青瓢箪ではない。もてる男として、自己を変革したいと願い、積極的に色町に通い詰める。当然ながら、小噺本の収集や社寺巡りと違って、費やす金額も桁違いとなった。作治郎の小遣い銭などたかが知れているが、豪商讃岐屋の若旦那と知っているから、どこでも信用が利く。叔父の九郎兵衛が幇間然として同道していることさえあった。着物は金のかかった品のいいものを常に身につけているし、顔は女形でも通用しそうな優男、性格も素直で悪擦れしていない。これに初々しい若さが加わると、まずどこへ行っても女にちやほやされた。年の瀬も押し迫った頃には、ひとかどの放蕩息子が出来上がる。
ただ、作治郎には悪趣味とも言えるので吹聴できないが、たったひとつ奇妙な癖があった。自分が情を交わした女との子細を丹念に書き記していたのだ。小輝の一件以後、ひとりの女に深入りすることなく、次々と場所を変えて遊んだが、小輝と別れる際、心覚えに記したのがきっかけで、それから後も出会った女たちの屋号と源氏名、容貌や体型、交わした言葉や体位、費やした金額まで、日づけ入りで丹念に書き止めた。これは遊女に溺れず、客観的に観察する訓練となった。
彼の記録癖、収集癖は今に始まったことではなく、幼い頃は絵草紙や滑稽本の収集家として、蔵書を分類し、目録を作って楽しんでいる。社寺の参拝を始めた時も、手帖を懐中に歩きまわっていた。女たちとの交流の記録もその延長線上であると言えなくもない。ただし、社寺参拝の記録と違い人目に触れては都合が悪いので、独自の符牒を考案するだけの配慮は怠らなかった。
放蕩を始めての最初の大晦日、讃岐屋では店も奥も一年の総決算と春を迎える準備で、朝からばたばたと薬臭い埃を立てて奉公人たちが立ち働いている。作治郎は家の騒々しさにも一向に平気で、昼近くまでゆっくりと寝て、朝食とも昼食ともつかぬ食事をすませた後は、離れに籠もり、彼なりに一年を締めくくっていた。手帖を取り出し、色男ぶりの復習である。記録を整理し、女たちの顔を思い浮かべながら、波瀾の多いこの一年を振り返った。手帖には難波新地の小輝を皮切りに女たちの源氏名がぎっしりと並んでいる。
「ほほう、せいだい気張ったつもりやが、あかんもんやなあ。夏、秋、冬と三季かかって、たった二十九人か。二十九ではなんや切りが悪い。あとひとりでぴったり三十と区切りがつくのやがなあ」
そのうち日も暮れかかり、女中のお鍋が行灯の火を入れに来る。顔色はその名の通り鍋底のごとく浅黒く、獰猛な猪を思わせる容貌で、山道などで出くわしたくない類である。世の中には随分と面白い造作もあるものだと、行灯に照らされた女中の顔を何気なく見つめていると、ふと目が合った。どういうわけか、お鍋はなかなか立ち去らない。
「なんや」
「へえ」
山出しの粗さはあるが、そこは若い女に違いなく、妙にもじもじしている。
「どないしたんや」
「へえ」
作治郎が覗き込むと、お鍋は浅黒い顔を伏せた。頬が赤らみ、鮮やかな赤銅色に変わる。息遣いが荒くなり、働き者らしい健康的な体臭が発散している。火鉢の上のやかんがちんちんと音をたてた。
「そや、これでぴったり三十。帳尻だけ合わせとこ」
翌日は元旦。商家はどこも大戸を下ろし、町々は火が消えたように静かだが、それに反して神社仏閣の賑わいは格別だった。高津神社の境内にも群衆がひしめき、参拝客を当て込んで露店が軒を並べている。初春を迎えめでたく十九となった作治郎は、参道の長い行列に加わっていた。自己変革のきっかけを与えてくれたありがたい神社に彼は初詣にやってきたのだ。
昨年の春、桜とともに散っていたかも知れない命がこうして無事に永らえたのは、両親の愛情でも医術の進歩でもない、茶屋遊びのおかげであると彼は考えた。
かろうじて命をとりとめたが、人は馬鹿げた理由で、あっけなく死ぬものだ。人生五十年というが、あと何年生きられるかわからない。せめて生きている間は楽しめるだけ楽しみたい。なるだけたくさんの相手と。
相手の数は。
参拝の順番がまわって、拝殿に手を合わせた作治郎の頭に一瞬閃いたのが、千人斬りの願いであった。太平の世の町人が志す千人斬りに、ぎらぎらした鋼鉄の抜き身は無用である。作治郎が胸に抱いた大志は、婦女千人と契りを結ぶ色事の野望だった。
「誓文祈願、なにとぞどうか……」
千人というのは十九歳の若者が意図する数字としては妥当なところだ。彼は昨年だけですでに三十人という数をこなしているから、百人斬りならわざわざ悲願するほどの数でもない。万人斬りとなると、毎日新しい女性と枕を並べても、一年三百数十日として、これを三十年近く続けなければならない。一日おきでも五、六十年はかかるだろう。発情した獣類でさえ毎日休みなしでは無理である。万人斬りは経済的にも肉体的にも物理的にも社会的にも不可能であると判断した。
千人斬りももちろん容易ではないが、まだ若いのだ。努力次第で望めない数字ではなかった。作治郎にも大坂商人の実利的な血が通っている。『養生訓』にいう交接の理想的な周期は、二十歳で四日に一度、三十で八日に一度、四十の者は十六日に一度となっている。単純計算で二十代に四日に一度として、閏月もあるから、年に九十回、十年で九百回。いや、一人一回で済まないこともあろう。人数が回数よりも少なくなるのは否めない。三十代で八日に一度として、年に四十四、五回。一人の回数をなるべく抑えれば、四十代でなんとか達成できそうだ。
相手はすべて絶世の美女と望みたいところだが、この世に美女がそんなにいるわけもない。大晦日に奥の座敷で情を交わしたお鍋のような女にも、なかなか味わいのあることを知ったので、素人でも機会があれば利用して、記録に変化をもたせるのも一興である。
ともかく、現在までにたった三十人だから、目標の千人までは、あと九百七十人の女を相手にしなければならないのだ。腎を養うためにも節度を守り、一滴の精液をも無駄にはできない。食生活にも気を配り、精のつく生玉子や鰻の蒲焼、泥鰌鍋、山芋、牛蒡などをとり、逆に精力を減退させるクワイなどは絶対に避けるべきだ。いざとなったら、店にある地黄丸(じおうがん)や女喜丹(にょきたん)を持ち出してもいい。
腰を鍛えるために、社寺巡りは再開しよう。遠出をするのも悪くない。一度、京の島原にでも足を伸ばそうか。千里の道も一歩からというが、残りの九百七十里、なんと遙かに険しくも楽しい道のりだろう、と正月早々親不孝な計画を練った。際立った才能も持たず何の苦労もなく過ごしてきた若者が、初めて見つけた人生の目標だった。
いくら大身代の豪商とはいえ、息子に湯水のごとく金銭をばらまかれてはたまらない。佐兵衛は度々叱りつけるが、どんなに意見しても、母と祖母が陰になってかばうので、放蕩息子はけろりとしている。とうとう十九歳の一年間で八十五人、通算百十五人にまで記録を伸ばした。
作治郎は決して世にいう色事師の類ではない。難攻不落の美女を征服するため手を変え品を変え果敢に挑む気力はない。格式の高い遊女の中には千両箱にも屈しない気位の持ち主もいる。ひとりの傾城に三十五度通って結局振られ、全財産を無くしたお大尽がいたそうだが、愚かな話だ。作治郎の持ち駒は当面豊富な軍資金と、豪商の息子としての信用だけだった。色町で遊びはすれど、手の届かない女には執着せず、分相応なところで素早く手を打った。人数さえ増えればひとまず満足なのだ。どんなに遊んでもひとりの女の色香に迷うことはなく、決して深入りしなかった。
「まあ、若旦さん。あっちこっちで浮気してなはんのやろ。知ってまっせ。ちょっとはひとりに決めなはったらどないでんねん」
次々と相手を変える客は、たとえ色町でも浮気者として評判がよくない。が、作治郎はひるまなかった。
「女かて、ひとりで何人もの男を相手にしてるやないか。おんなじことや」
新町の廓内だけでも二千人以上の女たちがひしめいていた。ひとりの女にこだわる義理がどこにあろう。
二十歳になっても放蕩は止まず、廓や色町の女はもとより、場末の酌婦も口説けば茣蓙を抱えた辻君まで買う。が、ついに家の女中、お鍋、お梅、お角、お熊、お亀、お寅、巨体のお六までもが嬉々として作治郎の伽の相手を勤めていたことが父に露見する。納得ずくとはいえ、主人の息子が女中に手を出すのは御法度、立派な不義である。
「これでは何のために不細工な女衆を集めてるのかわかりまへん」
ところが作治郎は平然としたものだ。女中たちに手を出したのは悪いことかも知れないが、主従関係を悪用して無理強いしたわけではない。女たちは喜んで相手をしてくれた。彼は不遜にも自分を源氏物語の主人公になぞらえ、女中たちをそれぞれ紫、藤壷、空蝉、夕顔などと呼んで可愛がったという。
「それにしても、解せんのは、なんでお鍋が紫なんや。顔色が紫色やからか。お梅が藤壷とはどうじゃ。肥壷ならわからんでもないが」
「名は体を現すと申します。名前だけでもきれいにつけたら、みんなきれいに思えてくるから面白い」
幼い頃から箸の上げ下げを厳しく躾られ、好き嫌いを言わず、食膳に出されたものは何ひとつ残さずきれいに食べ尽くすよう習慣づけられている。食事の作法を色事に拡大したまでのこと。並外れて珍奇な女中たちも、色気づいたせいか、そこはかとない愛嬌を見せ、以前ほど不気味な存在ではなくなっていた。父は大金を遣って揉み消しをはかり、女中たちには次々と暇を出した。
いっそ十八で患いついた時に死んでくれていればと、佐兵衛は本気で悔やんだものだ。この厄介な金食い虫を飼い続ければ、やがて讃岐屋は身上を潰すだろう。佐兵衛の実弟福松屋九郎兵衛を除くおもだった親戚が集まり、作治郎の処置について協議が行われた。九郎兵衛は息子の命の恩人ながら、悪の道に引き入れた張本人として、とっくに出入り差止めとなっている。
座敷牢を作って幽閉する案、銭のありがたみを教えるために南瓜の行商をさせる案などが出されたが、どれも手温い。これほどのどら息子は性根の叩き直しようがないので、勘当して讃岐屋との一切の縁を断ち切る以外に方法がないという決議がなされた。勘当と決まれば、その日から作治郎は讃岐屋とは赤の他人、人別帳から抹消され、一文無しの無宿人として家から放逐される。身分と人格を剥奪するもっとも厳しい処置である。
が、結果として、作治郎は勘当されなかった。心労が重なって祖母が倒れ、臨終の席で佐兵衛の手を握り、どうぞ勘当だけはしてやってくれるなと、遺言して死んだのだ。祖母の死によって勘当を免れた作治郎は、この年、少し自重したので、女の数は大幅に減って五十七人、通算で百七十二人となった。
翌年、二十一歳になると遅れを取り戻そうと一年で百三人、通算二百七十五人という無軌道ぶり。ただし、度々勘当を持ち出されるのもうるさいので、安い女郎ばかりを集中的に買った。次の二十二歳ではまた数はぐっと減少する。昨年は数字を増やすのに焦り過ぎ、腎を養う四日に一度という目安をはるかに上回り、そのうえ安いのばかり買ったため悪い病気に感染し、しばらく河内の別荘で養生しなければならなかったのだ。この年の冬、大坂では疫病のコロリが大流行し、多くの死者を出したが、市中の大騒動をよそに、作治郎は河内の百姓女を入れて無理やり二十五人をこなし、どうにか年内に三百人の大台に達することができた。
二十三歳の時に、また親戚が集まった。いっそ昨年のコロリで死んでくれたらよかったのに。
「なかなか思うようには、まいりまへんなあ」
やはり勘当以外に道はなかろう。が、祖母の遺言もある。作治郎が遊び歩くのは独り身の気楽さからで、出来のいい嫁を迎えれば、性根も座るだろうという話に落ち着き、本人の意向をただした。
「なるほど、みなさんのおっしゃる通り。それでは嫁を貰いまひょう。もしも、和泉屋のお花を女房にできるんやったら、心を入れ替え遊びはふっつりやめもいたしますが、それ以外の嫁ならば、決して迎える気はごわへん」
作治郎としては無理難題で父や親戚をやり込めたつもりだった。作治郎の言う和泉屋は伏見町でも老舗の呉服屋で、娘のお花は今年十七、その美貌は今小町として近隣に鳴り響く評判の美女であった。それほどの娘が悪名高い放蕩息子のところへ嫁いでくるわけがない。
ところが、佐兵衛はどう手をまわしたものか、この縁談をまとめてしまい、秋にはめでたく祝言となった。作治郎がこの年、相手にした五十二人の中のひとりに、とうとう花も恥じらう和泉屋のお花も加えられた。
翌年の暮れ、作治郎は不本意ながら、お花を離別した。お花は申し分のない嫁だった。美しいばかりではない。親元の躾が行き届いていたため、商人の女房としての礼儀作法はもとより、家事一通りから茶、琴、三味線、読み書き、算盤までこなした。気性も穏やかで、父や母にも優しく仕え、放蕩者の作治郎を心から愛しんでくれた。作治郎もまたお花を大事に扱った。彼がお花と別れる決心をしたのは、その年、情を交わした女が、師走になっても十七人を数えるのがやっとだったからだ。一年にわずか十七人とはあまりに少ないが、毎晩お花と過ごす楽しさに、つい色町が遠ざかってしまったのである。このままお花と連れ添えば、平凡な幸福は得られよう。だが、男としての念願は挫折する。彼は泣く泣くお花に離縁を申し渡し、恋女房は淋しく去って行った。
二十五歳で七十一人。二十六歳で六十三人。二十七歳で五十二人。
「これ、作治郎。そなたは気楽に毎日毎日銭を持って遊びに出て行くが、その銭はいったい誰が稼いだ銭やと思てるねん。世間に道楽息子というのはざらにいてる。親不孝な倅に泣かされてる家もたんと知ってる。ところがそなたの遊びは尋常やないぞ。うちになんぼ蓄えがあるというて、そなたのように、そう夜泊り日泊りが続いては、讃岐屋の身上もおしまいや。これ、何がおかしい。茶屋で遊ぶ銭などたかが知れてる。なんぼ遣うたかて、道修町の讃岐屋の暖簾はびくともせん。そう思てたかをくくってるな。お花のことにしてもそうじゃ。あれだけようでけた嫁はどこ探してもないわ。身を固めた上は、ちょっとは商売も覚え、店の役にも立つようになるかと楽しみにしてたが、そなたはほとほと薄情な男やな。わが子ながら情けない。あのお花な。今度、堺のほうへ嫁に行くことが決まったそうや。貞女は二夫に見えずというが、そなたのような極道に見込まれたばっかりに、あれもとんだ苦労をするなあ。どうぞ、幸せになってほしいと願うばかりじゃ。そなたにはもう愛想もこそも尽きた。この上は勘当以外に道はないが、その前にわしはひとつ、そなたに聞いておきたいことがある。いったい、なんで、それほどまでして遊ばなならんのじゃ」
「よう聞いてくれはりました。実は、わたしも遊びとうて遊んでるわけやない。これには深いわけがありますのや」
「遊びとうて遊んでるわけやないと。こら、面白いことを聞くもんじゃ。ふうん。ひとつ、そのわけを聞かせてもらおか」
「へえ。ほんならひとつ、そのわけ、聞いていただきまひょか。思い起こせば十年になります」
どがちゃか、どがちゃか、どがちゃか、どがちゃか。
二十八歳で九十九人。二十八歳での人数がとび抜けて多いのは、この年の春、苦労続きの父がぽっくり亡くなったからだ。道楽息子の根の深さ、妄念の恐ろしさに驚き呆れ、養子として守り続けてきた讃岐屋の暖簾をこれ以上維持することの馬鹿馬鹿しさを痛感し、精根尽きての無念の最期だった。商売上の付き合い以外では茶屋に行くこともなかった堅物の父。醜い女中を集めて作治郎を、いや自らを異性の誘惑から守ろうとした父。極道息子を勘当しようとして、ついに果たせなかった父。老舗の主人として迎えられ、讃岐屋に身を捧げて死んでいった父。父の喜びとは何だったのだろう。
家督を相続した作治郎は好きなだけ金を遣って、しかも、もはや文句を言ううるさい人間がいないのだから、家にいるより色町にいる時間のほうが長くなった。この年で通算は六百五十四人。十年でほぼ目標の三分の二に達した勘定だ。彼はずっと女たちの心覚えを手帖に書きつづっており、同じ女との重複を避けるのに役立った。
晴れて讃岐屋の主人佐兵衛となった作治郎は思案した。このまま商売を省みず、放蕩三昧に耽ったなら、いくら老舗の讃岐屋でも、身代はそうは長く続くまい。店が潰れてしまえば、自由になる金もなくなり、女たちはそっぽを向くに決まっている。彼は大坂の商人らしく算盤を弾いた。以後は節約を意識し、無暗に安女郎を買うのも控えた。作治郎時代ならともかく、讃岐屋佐兵衛となった以上、遊びひとつにしても店の信用を落とすような真似はできない。遊興の資金を生む店を潰さないために自然と商売に身を入れるようにもなった。それにも増して、若い頃のように肉体的な無理がきかなくなり、次から次へと女の数を増やしたいという情熱も薄れがちとなる。お花と離別した後は二度と妻帯せず、親戚の手前、家を絶やさないために遠縁の者を名前だけの養子としていた。そんなわけで、三十代以降の作治郎改め讃岐屋佐兵衛には、とりたてて面白い逸話は残されていない。
四
月日が流れ、彼が新町の吉田屋で栴檀太夫と契りを結んだのは四十七の歳だった。一流の太夫を相手に楽しもうとすれば、千両箱のひとつも空になる。裕福な大名か長者、豪商でなければ叶わぬ大尽遊びである。
ともかく、その名も高い栴檀太夫で九百九十九人まで漕ぎつけた。思えば長い道のりだった。決して順調というわけではない。世を上げての享楽の時代、天下太平の世相にはいつしか暗い影が差していた。この大坂の中心地で飢饉に苦しむ百姓たちが武装蜂起したのが十年前。驚いたことに、治安を守る側の町奉行所の元与力が百姓たちの先頭に立っていた。東町西町の両奉行が暴徒鎮圧に出陣の途中、共に落馬して笑い種になったが、佐兵衛は笑えなかった。元与力大塩平八郎率いる一味徒党は船場一帯を焼け野原にし、道修町の讃岐屋も焼け落ちた。店を元通り再建するのにどれだけ苦労したことか。思えばあの大塩焼(おおしおやけ)の頃から、相手にする女の数がめっきりと減ったのだ。
三、四年前からは商売も忙しく、若い頃の無茶が祟ってか体力も衰え、年にひとりか二人がやっととなっている。井原西鶴の書物には、五十年だか六十年だかの生涯に三千七百四十二人の女性を相手にしたという好色漢の記録が残っているが、どうせ作り話に決まっている。現実に四十七歳で九百九十九人ならまずまずだ。
いよいよ千人目に取りかかるわけだが、これは終幕を飾る記念すべき相手なので、安易には決めがたい。新町、島原の超一流の太夫を何人か候補に選んでいたが、まだ絞り切れていなかった。何も玄人に限ることもないのだが、四十を過ぎてからは万事金づく、素人相手の恋の駆け引きは面倒臭い。
もちろん、話のわかる素人で後腐れがないならば別だ。そういう娘もいないではない。四十の手習いで三味線の稽古に通ううち、十七の素人娘と知り合ったのは二年前のことだった。娘ながら、検校が一目置くほどの名手で、その腕前を誉めたのがきっかけとなり、これが同じ町内の同業で鵙屋(もずや)の娘と知れ、話がはずんで、そのまま深い仲になってしまった。小柄で肌の美しい娘だった。父親の安左衛門は顔を見知っている程度だが、佐兵衛とは同世代で、厄介なことにならなければと心配した。娘は少し目が不自由で、いつも若い丁稚あがりの奉公人が手を引いていたが、この男は美しい主人を崇拝しているらしく、こちらの魂胆を知ってか、いつも睨みつけるので、簡単には近づけない。とうとう娘とは後にも先にも、それ一度きりになった。多少の未練は残ったが、後々ややこしくならなければ素人も案外悪くない。
さて、五十までには間がある。あわてず気長に考えよう。とはいえ、いつまでも若くはいられないのだ。髪に白いものが混じり、ふっくらとした頬は痩せて、脂気がすっかり落ちてしまった。それでも彼は脚腰の鍛練を兼ねた社寺参りを未だに続けている。その日は思い出深い高津神社に参拝した。かつて十九の春、初詣で天の啓示を受け、婦女千人との情交を悲願したのは、ここだった。あれから二十八年、絵馬堂からの眺めは昔と少しも変わりない。茶店に腰かけ、のんびりと茶を飲んでいると、馴染んだ女たちの面影が脳裏をよぎる。
最初の女であった難波新地の小輝、三十人目のお鍋、百人目の国鶴、百四十二人目の綾衣、二百五十一人目の名も知らぬ辻君、二百八十三人目のお常、二百九十七人目の河内の百姓女、三百四十八人目の恋女房お花、四百十五人目の八重垣、五百七十人目の武家の妻女、六百三十三人目の岩橋、七百二十人目の有馬の湯女、八百六十人目の妙海尼、九百九十五人目の鵙屋お春、そして九百九十九人目の栴檀太夫まで、はっきりと記憶に残る女もあれば、手帖の記載を読み返しても、まったく思い出せない女もある。九百九十九人、覚えていない女のほうが多かった。高名な廓の太夫から場末の名もない酌婦、美しい町娘から醜い百姓の後家、いろんな女に慣れ親しんだおかげで、ことさら女を蔑み憎むことも、身も心も捧げて崇拝することもなくなった。女の肌の温もり、そのすべすべと柔らかな手触りは好ましいものだが、女は女であり、それだけのことだ。
人生五十年というが、自分の一生はなかなか捨てたものではなかったな。特別精力絶倫でもなく、女好きでもない自分がここまで来られたのも、高津神社のお導きかも知れぬ。十八で一度失いかけた命だが、その後は悪性の陰病にもさほど悩まされず、あとひとりで念願が達成する。
青空には手の届きそうな鱗雲が白く漂っている。高台からの景色を堪能して、席を立ち、歩き始めたとたん、「あの、もし」と声をかけられた。
振り返ると、二十二、三の女がにっこりと笑いかけている。
「あの、これ、お忘れやございまへんか」
見ると、女の差し出す手に佐兵衛の煙草入れがあった。
「ああ、たしかに。これは、おおきに、ありがとうさんでござります」
「ほな」
女は一礼して去って行く。身なりは粗末なのに、こざっぱりとした清潔感が漂っている。年頃は過ぎていそうだが、風体は未婚の様子。佐兵衛の心に甦ったのは、二十九年前の陽成院の一首だった。彼はすぐに女の跡をつけた。
女の名はお菊といい、高津橋の北詰を東へ入った裏長屋の住人と判明した。病気の老母と二人暮らしで、母の看病のかたわら、近所の仕立物など引き受けて細々と生計を立てている。それがために婚期を逃したのだ。
佐兵衛が貧しい長屋暮らしの娘を千人目の相手として選んだのは、彼女が二十九年前の絵馬堂における記憶を呼び覚ましたからだ。貧窮生活とは裏腹の、そこはかとない優雅さが彼女に具わっていたのも彼の欲求を刺激した。お菊のような女を最後の伴侶として過ごせたなら、波瀾の多かった自分の生涯も随分と穏やかに幕を閉じることになろう。
いくら貧乏人といえども、相手は素人だから、金で買うわけにはいかない。佐兵衛は人を介して縁談を持ちかけた。讃岐屋佐兵衛といえば誰知らぬ者もない分限者で、しかも妾で囲うのではなく、正式に本妻として迎えたいというのだ。老母を引き取り共に世話することも条件に加えた。相手にとっては福の神に到来されたようなものだ。
ところが、相手は拒絶した。しきたりのうるさい船場の御大家と裏長屋の住人では釣り合う道理がなく、みすみす娘に苦労をかけたくないというのが辞退の理由である。おそらく、佐兵衛の色町での悪名は鳴り響いているから、相手も二の足を踏むのだろう。今さら浮気をやめると言っても信用されるわけもない。
佐兵衛は引き下がらなかった。仲人を日参させ、進物を届け、最後には自分自身で長屋まで出向いて、思いの丈を訴えたが、母親は布団を被ったまま、顔さえ出さない。巨万の富や本妻の地位に心動かされないとは、この親子はよほど清廉で気丈な質とみえた。
佐兵衛としては、断られると、なおさら思いが募る。長い人生で無数の女を口説いて袖にされたことも数知れないが、諦めはよく、すぐに次の女に取りかかったものだ。ところが、今度ばかりは何としてもお菊を女房に迎えたい。それが叶わぬのなら、せめて一度でいい、肉欲だけでも満足させたいと思い詰める。彼女を千人目に選んだ以上、他のどんな女ででも大願を成就させるのは気が乗らなかった。
といって、今の佐兵衛には金以外に女を引きつける力がない。相手が金の誘惑に屈しないのだから、彼は煩悶するしかないのだ。なんとかお菊の心と体をとりこにしたいものと思い悩んだ末、商売柄、彼の頭に浮かんだのが、高津神社のすぐ近くにある黒焼き屋だった。
「どうぞ、御勘弁を」
黒焼き屋の主人は相手が道修町讃岐屋の当主と知るや苦笑し、額を撫でた。イモリの黒焼きは恋の妙薬として有名である。だが、その効用には民間信仰的な要素が強く、呪術の域を出ないことは専門家なら承知している。それを道修町の高名な薬種商が目の色を変えて求めようとしているのだから、話にならない。
店を出て、とぼとぼ行きかけると、後ろから声をかける者がある。
「もし、旦さん。耳寄りな話がおまっせ」
目つきの鋭い遊び人風だった。
「イモリもええけど、もっとよう効く薬がおますのや。ちょっと銭はかかりまっけどな」
どうせ眉唾だろうが、今は藁にもすがりたい気分になっている。
「ほう、そんなお薬がありますのか」
「おますとも。これをちょっと飲ますとな、どんな操の固いおなごでも、たちどころに乱れて、目の前にいる男やったら誰でもかまへん、身をまかさずにはおられんという正真正銘の惚れ薬でんがな」
遊び人はすらすらと言い慣れた口上をしゃべった。おそらく黒焼き屋のあたりに網を張り、身なりのいい人間が思い詰めて出てくるのを待ち受けているのだろう。人の弱みにつけ込む汚い商売もあったものだが、それでもかまわず、佐兵衛は男の後に従った。まさか、寂しい場所に誘い出し、追いはぎもすまい。
案内されたのは、四天王寺の近く、巫女町と呼ばれるあたり。死者の口寄せを生業とする女行者が多く住むので、そんな名がついている。
「この家だす」
遊び人は路地の奥を指差すと、にやりと笑い、小銭を受け取って姿を消した。小銭で文句を言わなかったのは、後で歩合をせしめる約束に違いない。思い詰めた客なら必ず中で大金を支払うと見越してのことだろう。
薄暗い室内に、ひとりの巫女がうずくまっている。年齢は五十から六十というところ。痩せさらばえた様は枯れ木のようだ。
「よう、おいでなされました。で、お相手はどのようなお方さんでござりますんかいな」
「詳しゅうにお話しせななりませんか」
「へえ、一口に惚れ薬と申しましても、相手によっても組み合わせによっても、匙加減が違います。旦さんのお相手が素人か玄人か、素人やったらおぼこか嫁はんか、いくつぐらいのお方か、痩せておいでか肥えておいでか、丈夫なお方かひ弱いお方か、いろいろお聞かせいただければ、ぴったりのお薬を差し上げますで」
佐兵衛はお菊について、知る限りの特徴を述べ、彼女が健康で気立てがよく、どんなに美しいかということまで強調した。
「旦さんは、おなごでは相当御苦労なさったお方やとお見受けいたしますが」
「ほう、わかりますかな」
「へえ。それほどのお方でも煩悩はお捨てになれんとみえますが、その娘御と添い遂げられさえすれば、長年の呪縛も解け、大願成就が叶うと、相に出ております」
「相も見なさるのか。たしかにおっしゃる通りじゃ」
「では、特にこのお薬を差し上げまひょう」
代金は五両だった。銀にして約三百匁、まやかし薬に途方もない大金をふっかけたものだが、もとより相場はなく、相手の風体次第で値を決めるのだろう。佐兵衛は値切りもせず、紙包みを受け取った。商売柄、薬の知識はあるが、白い粉末はうどん粉とほとんど変わりがない。
「それには味も臭いもござりませんゆえ、なんぞ飲物にでも混ぜて用いなされませ。じいわりと効いてまいります」
薬の効果については半信半疑だった。それでも一日も早く試してみたくて、佐兵衛は翌日、高津神社絵馬堂前の茶店でお菊を待ち受けた。彼女は感心にも、母の病気快癒を願い、参拝を日課としているのだ。
佐兵衛が呼び止めると、お菊は顔を曇らせた。断っても断っても、執拗につけまわされるのだから無理もない。
「なあ、お菊さん。二度と再びあんたさんの邪魔はいたしません。これが最後やと思うて、今少しだけ、話を聞いてもらえませんやろか」
年甲斐もなく哀願し、無理やりお菊に腰をかけさせ、抜け目なく茶と羊羹を注文する。
これが最後という言葉に安心してか、お菊も頑なな態度をゆるめた。そればかりか、彼女は佐兵衛を頭から嫌っているわけではなく、今回の縁談も身に余る話と喜んで受け止めていたと打ち明けたのである。
飲ませる前から効き目があるのかと、佐兵衛は驚いた。
反対しているのはお菊の母で、娘が佐兵衛といっしょになるぐらいなら、自分は死ぬとまで言い張ったのだ。
「なんぼ結構なお話でも、お母ちゃんの命とは引き換えになりまへん」
「ほう、母御がなあ。わしもえらい嫌われたもんじゃ」
お菊が語るには、老母はもともと裏長屋の住人ではないとのこと。堂島の大きな油商の箱入り娘として何不自由なく育ったのだが、娘時代に重病で一時気が触れたようになり、婚期も逃したので、忠義者の番頭に因果を含めてこれを婿にした。これがお菊の父親だが、この頃から家運が傾き、遣り手であったお菊の祖父が流行り病のコロリでぽっくりと亡くなる。父はなんとか店を盛り立てようと相場に手を出し、失敗して逐電する。昔からいた奉公人もひとり去り二人去りといなくなり、悪いことは重なるもので、よそからの貰い火で店は全焼。油屋だけにひとたまりもなかった。母は幼いお菊を連れ出すのが精一杯で着物一枚、一文の銭さえ持ち出せなかった。逃げ遅れた祖母は焼け死に、土地を処分した金は親切ごかしの親類に騙し取られ、とうとう長屋でのその日暮らしとなった。
お菊は幼い頃から貧しさに慣れているので平気だが、母は今の境遇を嘆くあまり、昔の病がぶり返し、脚腰も立たない状態でいる。母の不幸は娘時代の病気が元であり、病気にかかったのは、そもそも若い日に高津神社でひとりの若者と出会ったことが原因だというのだ。
「嘘みたいな話ですが、この茶店でどこぞの見も知らん若旦那に声をかけられ、百人一首の歌を取り交わしたのが元で、気の病にかかり、そのまま三年も寝込んだんやそうです」
「なんですと」
「ほんまに嘘みたい。それからの不幸続き、お母ちゃんは相手のお人を今でも忘れられへんみたいで、恨みがましゅうに言いますけど」
「今でも相手のお方を覚えておいでか」
「ええ、一生忘れられへんと言うてます」
「それはどこのどなたで」
「さあ、ようはわかりません。そやけど、お母ちゃんが病気になったおかげで、番頭してはったお父ちゃんといっしょになって、うちが生まれることができたんやから、うちはその人のこと恨むのはお門違いやと思てますの」
話し終えると、お菊は喉をうるおすため、湯呑み茶碗に手を伸ばした。佐兵衛はとっさにその手を払う。
「あっ」
湯呑みは地面を転がり、薄茶色の液体は湯気をたてながら地中に吸い込まれた。
「えらい粗相して、堪忍しておくれ」
「いいえ」
佐兵衛は粗忽を詫び、お菊は別段不審にも思わず、にっこりと笑って去って行った。もう二度と逢うことのない女。二十九年前に見た艶やかな後姿が一瞬甦り、お菊と重なった。彼は女が視界から消えても、しばらくは麻痺したように絵馬堂の前から動かなかった。
こひぞつもりて淵となりぬる
恋狂いの陽成院は乱行の果てに廃位させられたとか。二十九年前の借り物の歌、陽成院の呪縛から自分は未だ抜け出せないでいるのかも知れない。
後日、気にかかることがあり、再び巫女町を訪ねると、例の路地裏にはすでに空き家札が下がっていた。近所の話では、巫女の行方は知れぬが、かつて色町で遣り手婆をしていた女郎の成れの果てらしいとわかった。あの日はお菊のことばかりで頭が回らなかった。だが、痩せた巫女の眼光に以前馴染んだ女の面影を見たような気がしてならない。いったい誰だったのだろう。小輝、国鶴、綾衣、いや、手帖に記すためだけに金で買い、一夜で捨てた女のひとりだろうか。思えば夥しい出会いと別れを経験したものだ。それももう、確かめるすべはなかった。
讃岐屋佐兵衛は幕末維新の変動期を無事に生き延びて、明治の時世に八十二で天寿を全うしたが、九百九十九人目以降の艶聞は伝わっていない。
本稿は同人誌「川」に寄稿したものに加筆。