頼迅庵の新書・専門書ブックレビュー59
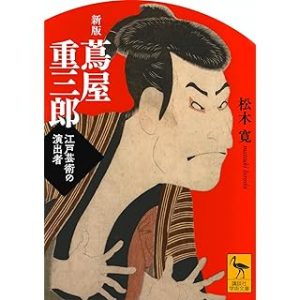 『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(松木寛、講談社学術文庫2840)
『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(松木寛、講談社学術文庫2840)
2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』の主人公は蔦屋重三郎です。
本書は、その蔦屋重三郎(寛延3年(1750)生まれ)の生涯を美術史の側から取り上げたものです。以下、その内容を簡単にまとめてみましょう。
蔦屋重三郎は、安永2年(1773)新吉原大門口五十間道の左側に店を構えます。翌安永3年の『一日千本』という遊女評判記の出版から寛政8年(1796)に亡くなるまで江戸の出版会に旋風を起こしました。
書肆として活躍したのが、田沼時代から寛政の改革の時代で、その制約を受けるのは当然ですが、それでも鱗形屋という大版元の小売業から始まって、ついには日本橋通油町に店を構えるまでになります。このとき蔦屋重三郎は、押しも押されもせぬ一流版元になっていました。
書肆は、書物問屋と地本問屋にわかれます。当時、日本橋界隈の書物問屋には、須原屋茂兵衛、同市兵衛、前川六左衛門、地本問屋は松会三四郎、鱗形屋三左衛門、山形屋市郎右衛門ら歴代の名補が店を連ねていたといいます。
書物問屋とは、「物の本」と称される堅い内容の書籍を扱う書肆のことで、儒学書、仏教関係書、歴史書、医学書などを対象とします。
それに対して、地本問屋とは、草双紙や絵双紙など、江戸の地で出版された書籍(これを「地本」といいました)を扱う書肆でした。
江戸大衆文学の流れの一つに赤本、黒本、黄表紙、合本という系譜がありました。これらはかな書きの絵入り本で、その名前は表紙の色によっています。
赤本が延宝頃から寛延頃まで、黒本・青本が延享頃から安永4年まで、童話や民譚あるいは、歌舞伎や浄瑠璃の筋書、伝説や軍記物、敵討、怪談などに題材をとり、その絵解きに主眼が置かれた稚拙な内容の作品だったといいます。
そんな草双紙の現状に満足しなかった鱗形屋孫兵衛と恋川春町は、洒落本(※1)の写実的な内容を求める流行の風潮を機敏に感じていました。
そこで発表されたのが、恋川春町による『金々先生栄華夢』です。これは大成功を収め、江戸文学史上画期的な作品となりました。
黄表紙文学は、春町と鱗形屋の創案になるといっても良いでしょう。通と滑稽を表裏一体とする洒落本の発想と手法の上に、草双紙的要素(挿絵(絵画)を取り込む)を取り込んでいました。本書では、文学と絵画を合体させた「視覚的文学」の成立と呼んでいます。安永・天明の文学界は、黄表紙時代に突入したのです。
さらに鱗形屋は、春町の友人で朋誠堂喜三二を起用して大成功を収めます。鱗形屋の小売りだった重三郎もそれなりに売れていました。
しかし、鱗形屋は重版事件を起こしたり、主家の重宝を質入れする用人の仲介を行ったりして当主孫兵衛が所払いになるなど、安永8年から営業不振に陥ります。
このとき重三郎は、朋誠堂喜三二(文)、北尾重政・政演(画)という一流の布陣で、安永9年一気に十五種類の黄表紙などを刊行しました。それまでの四年間の実績が20種程度といいますから賭けに出たといっても良いかも知れません。
そして、これが重三郎の飛躍の契機となりました。その要因はどこにあったのでしょうか。本書では、鱗形屋事件という千載一遇の事件にぶつかった「時の運」、朋誠堂喜三二(文)、北尾重政(画)らと深い交流を結べた「人の運」を握ることが出来たことに求めています。
蔦屋重三郎が日本橋通油町に店を構えたのは、天明3年(1783)9月のことでした。わずか10年で一流の版元になっているのです。
その要因はどこにあったのでしょうか。本書では、経営の生命線を独創性に充ちた斬新な企画とこれを実現できる力量に恵まれた有能な人材の二つをあげています。前者は重三郎自身に関わることですが、後者はその豊富な人材ネットワークといってもよいものです。例えば、喜三二と春町は莫逆の友であり、春町は鳥山石燕の弟子でした。この石燕の弟子に歌麿がいましたが、石燕は北尾重政と仲が良く、歌麿は重政を慕って弟子同然だったようです。こうした縁で、歌麿は重三郎のもとで出版することとなります。
また、北尾政演は、重政の弟子で絵師として出発していますが、後に山東京伝という名で戯作者となって成功しています。
重三郎は、喜三二(文)と北尾重政(画)を全面に押し立てながら、片や狂歌師大田南畝の本も出しています。天明期は、その大田南畝などの狂歌師と北尾派の画を合わせた狂歌集が飛ぶように売れたのです。
この天明期には、黄表紙や浮世絵も売れていましたが、田沼政治の重商主義による好景気も幸いしたことでしょう。
そんな中、黄表紙は政治風刺の方向へと向かっていきました。
田沼政権下の政治風刺は、庶民から喝采を持って迎えられましたが、やがて、政権が松平定信に移ります。
定信は、寛政元年4月に『鸚鵡返文武二道』が寛政の改革を批判したとして作者春町を召喚しようとしました。しかしながら、春町はその召喚に応じず、7月に病死してしまいます。(※2)
幕府は出版統制に踏み切り、重三郎が出版した本を違反としました。そのため、重三郎、山東京伝、月行事2人が罪に問われてしまいます。
その後、重三郎は美人画で喜多川歌麿、役者絵で東洲斎写楽を売り出しました。
現在でも東洲斎写楽は謎の人物ですが、彼の実績は3期にわけられます。第1期、第2期と異なり第3期の作品は評価が高くないのですが、本書ではその理由といくつかの作品は偽物と断定しています。その理由と推理方法は、ぜひ本書をお読みいただきたいと思います。美術史家からしい目の付け所となっています。
最後に蔦屋重三郎から作品を出版した有名な作者・絵師を上げてみましょう。
朋誠堂喜三二、恋川春町、大田南畝、山東京伝(北尾政演)、北尾重政、喜多川歌麿、東洲斎写楽、勝川春朗(後の葛飾北斎)、十返舎一九、滝沢馬琴
江戸の文学史、美術史に名を残す錚々たる名前が挙げられます。天明から寛政へという時代が産んだ寵児ともいえるかもしれませんが、出版という形で、その時代を蔦屋重三郎が造ったといえるかもしれません。
文と画を併せて売っていた本が、やがて文は読本としてその物語を楽しみ、画は美人絵や役者絵を楽しむ方向へと分化していきました。
紙の出版が衰え、電子出版が伸びている昨今、この時代から学ぶことはないのでしょうか。
あるいは、現代に蔦屋重三郎は現れないのでしょうか。
最後に紹介する本は、小説ではありませんが、滝沢馬琴の『近世物之本江戸作者部類』 (岩波文庫)です。(↓)
https://amzn.to/3QY3vaa
江戸の100名余りの戯作者を馬琴らしい辛口で評したものです。
※1 洒落本とは、遊女と客の駆け引きを描写したり、野暮な客を笑いのめしたりという内容のもので、粋(いき)を理想とし、遊所(遊郭)での遊びについて書かれたものがほとんどでした。ただし、話を楽しむためだけでなく、実用的な遊び方指南や一種のガイド本として読まれました。
※2 恋川春町は、駿河国小島藩1万石滝脇松平家の重臣でした。そのため、幕府からの召喚に病気として応じず、自殺したという説もあります。
