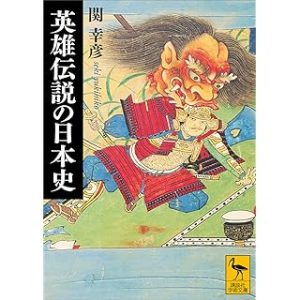頼迅庵の新書・専門書ブックレビュー54
前近代の英雄といえば誰を思い出すでしょうか。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など戦国武将をまず思い浮かべることでしょう。
では、中世の英雄といえばどうでしょうか。平将門、源義家・義経、平清盛、足利尊氏あたりでしょうか。
本書は主に中世の英雄に係る伝説の歴史を取り上げています。
いつものように目次を見てみましょう。
第一章 再生する英雄たち 江戸の中の中世
第二章 道真と将門 敗者の復活
第三章 田村麻呂と頼光 武威の来歴
第四章 為朝と義経 異域の射程
第五章 伝説の記憶 歴史観の祖型
第一章では、江戸時代に再生される中世の英雄たちについて述べられています。
江戸時代に人気となった中世の英雄は、多く『平家物語』『太平記』にそのルーツを持つとようです。特に浄瑠璃、歌舞伎、講談、落語等で取り上げられる英雄、つまり作品化された英雄たちは、修羅物と呼ばれる謡曲の諸作品と有形無形の関係にあるのですが、そのほとんどが負け戦、敗者の物語であるといいます。
確かに判官贔屓という言葉に表されているように敗者義経への思いを日本人は強く持っていますが、それは義経のみにとどまらないようです。
さらに、義経の判官物と並ぶものが、曽我物と呼ばれる敵討ちをテーマにした物語です。敵討ちといえば、曽我物と人気を二分したものが忠臣蔵です。曽我物が親の敵を忠臣蔵が主君の敵を討つ物語ですが、親の敵か主君の敵かが、中世と近世を分かつ分水嶺らしいのです。
では、中世の伝説と近世の伝説との違いはどこにあるのでしょうか。中世の伝説の多くは、神仏を背負い、神仏と同居することで伝説の構想が成立し、一方、近世のそれは神仏を意識的に分離し、徹頭徹尾人間の浮世世界へと中世の人物を感情移入することで成立していると著者はいいます。
併せて、庶民の教育に往来物と呼ばれるテキストが使われたことが、上記の英雄たちを身近に感じさせた功績は大きいといいます。
第二章では、敗者の復活として菅原道真と平将門を取り上げています。
右大臣から太宰権帥として太宰府に左遷された道真は、なぜに天神様として祀られるようになったのでしょうか。その理由は将門の天慶の乱にあるといいます。それ以前から、道真を讒言した藤原時平の死や清涼殿の落雷事件などを通じて、それが道真の霊の仕業とされて怖れられていました。
将門は坂東で新皇を称して、明らかに朝廷に謀反(反逆)を起こしました。だが、その新皇を称する端緒は、『将門記』によると上野の国府で八幡大菩薩の使者と称する巫女が登場し帝位を授けるのですが、八幡神とともに天神すなわち菅原道真が登場するのです。
京都の天皇に対し新皇の創出とはどういうことなのでしょうか。王朝の交替を肯定しているのでしょうか。否、『将門記』は、新王朝の樹立ではなく、坂東地域の分与という意識が強かったと著者は分析します。ゆえに、本来の天皇=「本皇」の存在を認めたうえで、将門は自らを「新皇」と称したのです。これにお墨付きを与える神は、天照大神ではなく八幡神こそ相応しいと『将門記』の作者の意図を読んでいます。
ここでなぜ天神=菅原道真までが味方したのか。それは、自己(道真)を敗者に追い込んだ王権への復讐、そのための反逆者への与同という論理だったといいます。怨霊は王権に勝利するどころか、保証を与える存在にまでなっていたのです。
道真伝説は、その後近世になって中世的な怨霊あるいは御霊信仰の対象から解放されることとなります。
一方、将門はいわば反逆者(謀反人)です。当初、源頼朝も反逆者とみられていたようですが、平家を追い落として武家の首長となることによって、将門はいわば東国武家の正当性の「保証人」になったのです。
第三章では、坂上田村麻呂と源頼光を通して武家の来歴が語られます。そこには、大きく2つありました。一つは、田村麻呂を祖として東夷を「征伐」するという史観です。ここから、源頼義・義家の前九年合戦は、武門源家誕生の神話に欠くことのできないものとなり、源頼朝の奥州藤原氏の追討によって完成するといいます。頼朝の任じられた征夷大将軍が、まさにそのことを物語っています。
もう一つは、武力の霊的な威力に関わる問題です。これは頼光を祖とする大内守護、つまり王権の基盤たる京都を物怪、怨霊、邪気、鬼神から守ること、すなわち「辟邪の武」です。しかしながら、中世の現実は、東国的な武威を選択することで、国家の軍事権門の地位を幕府に与えることとなりました。
第四章は、源為朝と義経を通じて異域の射程について述べられています。為朝の琉球伝説、義経のエゾ逃避からジンギスカン伝説を通じて、日本の周縁部を取り込んでいく過程、つまり明治になってエゾ地=北海道から琉球までの日本という国家、国土の形成へとつながっていくのです。
第五章は、伝説の記憶が歴史観の祖型を形作ることについて述べられています。
以上、今回は駆け足で本作の要約を述べてきましたが、著者はあとがきにあるように日本人の歴史観なり歴史認識の祖型をどうすれば抽出できるか考えることからはじまったと述べています。
文章は読みやすく、自身の歴史観を考えるうえでの参考となるように思われます。