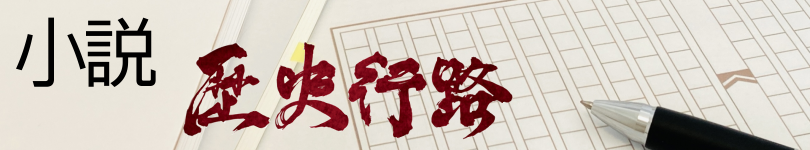西山ガラシャ
1
尾張の西方、鵜多須(うたす)の地に、偏屈者の代官がいた。名を岡田喜太郞という。三十五歳になった喜太郞が目下望むところは、立身出世だ。
文久元年(一八六一年)の桜が散る頃、陣屋の西を流れる佐屋川の水面を見つめながら、喜太郞はしみじみと胸の内なる声を聞いた。
「名古屋城下に戻り、大代官になりたいものだ。いや、一足飛びに勘定奉行でもよい」
鵜多須などという辺境の地に何年も追いやられているのは、なんとしても合点がいかぬことであった。
尾張徳川家の領地には十一の代官所があり、代官の任に着く者は、数年おきに各地の代官所へ異動させられる。名古屋城の南にある大代官所を筆頭に、清須、鳴海、北方(きたかた)、横須賀、佐屋、水野、小牧、上有知(こうずち)、太田、そして喜太郞のいる鵜多須の十一カ所だ。
喜太郞はすでに九年も鵜多須の地におり、このまま一生を鵜多須の地で過ごすことにならぬかと不安にもなる。今はかりそめ、この先に必ずや己の人生は花開くと信じ続けている。
鵜多須代官所には十人ほどが詰めている。代官の喜太郞を筆頭に、手代が五名、並手代が一名、同心三名だ。
喜太郞の下には、猫八という名の手代がいる。人間に裏表がなく、上下の関係などわきまえずに思うがまま喋る点を、喜太郞はいたく気に入っている。
「猫八!」
呼べばすぐ来る。
「なんでしょう」
ひょうひょうとした猫八は首が長く、顔も長い。
「わしは、変わり者だと世間から思われておるようだ」
喜太郞の言葉に、猫八が深く頷く。
「おっしゃるとおりかと存じますが」
猫八が肯定するなら、何事も真実だと思わねばならぬ。
「つまり嫌われ者か」
「否定はいたしません」
「なぜわしは人に嫌われるのか」
「話し方がぶっきらぼう、且つ、つっけんどんで、村人ともあまり話をせず、温情もかけませぬ。そのあたりに起因しておりましょう」
本音を聞きたいがために、猫八には遠慮なく喋らせている。
「温情とは何か。村人に温情をかける代官などおるか」
喜太郞の問いに、猫八はすぐさま答えた。
「おりますとも。聞いた話によれば、美濃の太田の代官などは、困窮した村人が納めるべき年貢を、なんと代官自身が肩代わりをして納めておると聞きました。村から一人も餓死者を出さぬための策であるとか」
「あとさきを考えずに行動する奴だ」
太田代官の弓削勘三郎(ゆげかんざぶろう)の大きな顔が浮かんだ。もともと調子のいい男である。
「次に太田代官所に着任することになる者は、ひどく難儀をするはめになる」
太田代官所にだけは移りたくない。
「しかしながら喜太郞様。もし鵜多須代官所の管内で餓死者が出た場合には、喜太郞様の目指す出世など、叶わぬ夢になりますよ」
「餓死する者など、鵜多須におらぬわ。見ればわかる」
鵜多須はのんびりした土地だ。村人どうしは互いに助け合い、暢気に暮らしている。喧嘩や揉め事すら、ほとんどない。だから喜太郞には物足りない。
「餓死はせずとも、村人たちは、至極つましい暮らしをしております。代官が情けをかけてくれたなら、きっと感動します。村人と上手くやっていこう、寄り添おうとする姿勢に、村の人たちは喜ぶのです」
猫八の考えに、賛同できなかった。
「村人に迎合するつもりはござらん」
同様にお上に対しても、へつらわぬ。だが出世だけはしたい。
「喜太郞様は、いまのままでよいのだと思います。ただ、喜太郞様の、算盤なしで何桁でも勘定できる才が、まったく活かされておらぬのは、もったいない。才を活かさざるは、尾張国の損失につながります」
「勘定奉行にでも、なりたいものだ」
喜太郞の漏らした言葉が聞こえたか否か、もう一人の手代、熊五郎が現れたために猫八が振り返った。熊吉が文を届けにきた。
「御家老、竹腰(たけのこし)志摩守からでございます」
文を開くと、話があるので登城せよと書いてある。
猫八が遠慮するそぶりもなく、横から文を覗き込んで声を上げた。
「喜太郞様。もしかして、もしかすると、城で昇進の話があるのでは? 九年に及んだ鵜多須での暮らしも終わりかもしれません。それがし、喜太郞様には地の果てまでもついてまいりますよ。次はどこの代官所でしょうね。鳴海か清須か、はたまた小牧でしょうか。美濃の太田だったりして」
猫八が一人で、はしゃぎはじめた、
その隣で熊五郎が、低い声で呟いた。
「今のように安穏と暮らせるのは、鵜多須だからかもしれません。江戸や京は物騒な事件も多く、その余波が尾張にも及びはじめております。巻き込まれることなく静かに暮らすのも一計」
喜太郞は熊五郎を睨んだ。
「いや。わしは、世の荒波を真っ向から受けて立ちたい!」
淀んで滞留していた血が、急に体内を駆け巡りはじめた気がした。
遠くを見れば、代官所の南にある神明社の森が、夕陽を反射してまぶしく見えている。蝉の鳴き声が急ににぎやかに耳に響いてきた。
同年三月十四日。喜太郞は、名古屋城の二之丸へ出向き、家老の竹腰志摩守と対面した。
帝(孝明天皇)の妹である皇女和宮が江戸へ下る話を聞かされた。将軍の徳川家茂との婚儀、すなわち公武合体の話である。
「それは、めでたいことでございまする」
雲上人の話であり、「めでたい」という言葉が適切なのかどうかも判断しかねたが、慶事なので言葉を選んだ。
家老の竹腰も、めでたいなどとは微塵も思っておらぬ様子で眉を寄せた。
「困ったものじゃ」
皇女和宮が江戸へ向かう花嫁行列は、中山道を通行する。
中山道六十九次のうちの二十次が、尾張徳川家の領地内だ。京から江戸までの全行程の三分の一に迫る距離である。領地内での責任は、当然、尾張徳川家が負う。
「和宮様御下向の途上、何事かあれば、わしは腹を切らねばならぬ」
竹腰の顔が、すでに疲弊しているように見えた。
「何事か、とは、いかような物事を指すのでしょうか」
「昨年の江戸城桜田門外の変事のような、浪士による御通行の妨害などである。駕籠に向けて、ぶすり」
竹腰は目に見えぬ槍を、目に見えぬ駕籠に突き立てた。
尾張家には、御土居下衆なる隠密の組織があり、貴人の通行とあらば、中山道沿いの宿から林の中まで、闇に紛れて徹底して検分するはずだ。今から悪い想像をしても、埒が明かぬ。
皇女和宮の話が一区切りつくと、喜太郞の身の振り方の話になった。
「そなた、鵜多須代官所にはすでに長くおろう。この先、何か望むところはござろうか」
待ち構えていた話題であった。もし他所へ移る話が家老の口から出なければ、自ら望むところを述べようと決めていた。
「それがしは、のどかな土地柄が性に合いませぬ。できうれば、城に近く、なるべく仕事の多い役を望みます」
喜太郞の頭には、勘定奉行の四文字が浮かんだが、さすがに口に出すのをためらった。
「ならば適任。にわかに忙しくなる名古屋大代官所の、大代官を命ずる」
喜太郞は素早い答えに驚いたが、竹腰にも腹積もりがあったのだろう。
勘定奉行でなくとも名古屋大代官所ならば、よしとする。
(昇進だ!)
喜太郞は、悟られぬよう口を真一文字に結んだまま、胸の内では快哉を叫んだ。
竹腰は念を押すように言葉を続けた。
「大代官として、和宮様御通行の陣頭指揮をとるように」
「はは。謹んで拝命仕ります」
畳に頭が着くくらい平伏した。
(ついに鵜多須から脱出できる!)
「重ねて申すが、皇女和宮様の御身に何かあれば、それがしは切腹。大代官も同様にして、首が飛ぶであろう」
「覚悟をもって、任にあたりまする」
暇で身を腐らせることを思えば、よほど良い話であった。
2
文久元年四月十八日(西暦一八六一年五月二十七日)
岡田喜太郞は、名古屋大代官に着任した。
手代の猫八は喜太郞とともに名古屋へ引っ越してきた。熊八や他の手代、同心らは鵜多須に残ったので、新しい部下を任用した。
猫八は引っ越してきてすぐに、検分と称し、名古屋じゅうを歩き回って町の様子を喜太郞の耳に逐一入れる。陽射しの強い日も、かまわず歩き回っていた。
六月十五日。
さすがに猫八の額が汗でまみれていた。
「天馬会所の水谷与右衛門(みずたによえもん)なる役人が、和宮様の御通行で、荷物運びの人数が足りるかどうか、ひどく案じておるようで、あちこちの村の百姓に声を掛けまくっておりました」
「十月下旬の御通行を、六月から案じて、どうなる」
「人手が足りなくて、天馬会所のせいにされるのが嫌なのでしょう。人集めがどれほど大変かを、声高に話していましたからね」
猫八は、鵜多須にいた頃より生き生きとしている。喜太郞と同じく、辺境の地より町が合っているらしい。
「しかし天馬会所の役人より上手(うわて)なのが百姓どもで、荷物運びに従事し得られる賃金で、善光寺詣でをしようと画策している者が少なからずおります。中山道沿いで仕事をしたら、そのまま名古屋へ戻らず、ついでに信濃の善光寺詣でに行きたいらしいのです」
「善光寺の何がいいのか」
喜太郞は、善光寺どころか伊勢神宮へ行こうとする人の気持ちが解せぬ。
「え。喜太郞様だって、じつは行きたいでしょう?」
「これっぽっちも、行きとうないわ」
「神仏に祈れば、喜太郞様が常々望むところの出世も叶えられるかもしれませんよ。あ、もう出世はされたのでした。名古屋大代官になったのですから。しかし、まもなく更なる出世がしたくなるかもしれません」
勘定奉行になる野望は捨ててはいないどころか、ますます欲求が高まっている。
「侍の出世と、神仏との因果はござらん」
「どうでしょうかね。案外と出世も巡り合わせ、運の巡り合わせを司るのが神仏だと思うておりますが」
猫八の持論には賛同できぬものが多いが、考え方の一つとして、黙って聞くことにしている。さらに、初対面の町の人ともすぐに打ち解けられる猫八の人懐こさは、喜太郞からすれば尊敬に値する。
猫八の話を聞いている間に、大代官所の入り口付近で人の声がするのが聞こえた。
「なにやら騒がしくないか」
「来客でしょうか」
猫八が廊下を振り返った。
すると、新しく名古屋で雇った新人の手代の犬吉が、慣れぬ様子で伝えにきた。
「伝馬会社の水谷与右衛門と申す役人ほか、村役人が五名、代官様にお目通り願いたいとのことでございます」
猫八が「おっ」と声をあげた。
「喜太郞様、噂をすれば何とやら、でございますよ。水谷与右衛門が、十月の人集めが心配で夜も眠れず、陳情に来たに違いありません」
「広間で会う。通せ」
喜太郞は、水谷与右衛門の言い分を存分に聞いてやろうと思った。
代官所の畳の間に、天馬会所の与右衛門と、村役人たちが座った。喜太郞の姿を見るとすぐに声が上がった。
「お代官様!」
「喜太郎である」
役名で呼ばれるのが嫌いである。
「喜太郎様」
「意見があるなら、しかと聞く」
すると、はじめて見る細面の男が口火を切った。
「名古屋札の辻、伝馬会所の水谷与右衛門でございます」
なるほど慎重そうな石橋を叩いて渡る質の男に見えたが、なかなかのやり手にも見えた。
「噂によりますれば、和宮様ご婚儀に伴い、二万五千人ほどの大行列が、四陣に分かれて中山道をお通りになると聞きました」
「噂でござらん。すでに決まっておる」
喜太郞は、はっきりと答えた。
「であれば、継ぎ立て人馬も、夥しい数が必要となり、概算では、鵜沼宿から本山宿までの二十宿の間に、のべ五万人の荷物運搬の人手が必要でございます」
「それで?」
喜太郞は、与右衛門の頭のてっぺんから膝の形まで舐めるように眺めながら話を聞いた。
「手前ども問屋が、いくら手を尽くしたところで、五万の人数など、とうてい集められません。中山道の宿場町でも、助郷の協力を得たところで、集められる人数はせいぜい数千人。いかように対処されるのか、早々にお決めいただきたいところであります」
「早々に」という言葉が喜太郞の胸に引っかかった。与右衛門なる男、代官を責め立てているつもりなのか。やたら、対応を急げと急かしているように感じる。焦る必要など、どこにあろうか。
「五万人が必要と申したな」
「いかにも」
「五万人は、わしが集めたる!」
喜太郞の言葉に、与右衛門も村役人も唖然とした様子で、一瞬の沈黙があった。
しばしの静寂を破り、与右衛門が再び口を開いた。
「いくらお代官様でも、五万人はご無理では」
「喜太郞という名がある」
「失礼いたしました。いくら名高い喜太郞様であっても、万の人数を集めるのはご無理かと存じます」
勝手に、無理だと決めつけられた。不快である。
「わしには人集めはできぬと思うておるのか」
「半端な数の人数ではありません。五万です」
「五万だろうが、十万だろうが、何万人でもわしが集めたる!」
語気が強くなった。
与右衛門が一瞬、口を閉ざした。疑う顔をしている。
「では、どのように人集めをなさるのか、教えていただきたく存じます」
与右衛門の言葉に、村役人たちが声を重ねた。
「知りたいところです」
「ご教示いただきたい」
喜太郞は、目の前に座る面々の顔をひととおり眺めてから、言葉を発した。
「五万人が必要であるなら、各村から、何人の人間を差し出せば尾張じゅうで五万人を集められるかを逆算すればよいだけのこと。村の石高に応じて、差し出させる人数を割り振る」
与右衛門は、いまだ理解しておらぬ様子で、喜太郞を見つめている。
喜太郞は続けた。
「六十二万五石と控えめに公表しておる尾張は、実際のところ九十万石強だが、計算の都合上、百万石とする。では、村高百石につき、何人の人間を差し出せば、尾張全体で五万人が集まるか」
突然、説明を質問に切り替えた。
「水谷与右衛門と申したな。質問を繰り返す。村高百石につき、何人の人を差し出せば、百万石の尾張に五万人が集まるか、と訊いておる」
喜太郞の質問に、与右衛門は急に頭の動きが止まったかのような顔をした。
「勘定ができぬらしい」
喜太郎は待ちきれずに、自ら回答を告げた。
「五人である! 村高百石につき、五人の人間を差し出せば、百万石の尾張では五万人が集められる。大きな村からは大勢の人数を、小さな村からは少人数を差し出す。村の石高に比例して集めれば、文句も出ぬ。尾張全域、すべて平等に、人を出させる」
喜太郎の説明を誰もがしんとして聞いていた。中には理解できぬといった顔をしている者もある。
「仮に、領内に村高四百石の村があるとする。五万人を集めるために、村高四百石の村からは、何人を差し出せぱよいか。与右衛門、答えよ」
質問を飛ばした。
「百石に付き五人ですから、村高四百石なら、四を掛けて、二十人でござります」
「ようやく、頭が働いてきたとみえる。石高による動員の方法が、わかったか」
与右衛門の顔がまだ曇ったままであったから、解せぬ部分を残しているらしい。
「石高で割り振って、本当に人数が集まるのでしょうか。集められぬ村もあるのでは?」
「はて。年貢米ですら集まるのだ。年貢米は、凶作であれば米を差し出すのが厳しい時もあろう。だが、人は常におる。必ず集められる」
与右衛門ほか、村役人たちは、ようやく落ち着いてきた様子である。
「代官様、いや喜太郞様。ようわかりました。ではもう一つ、ご相談がござります」
与右衛門が、さらに前に身を乗り出した。
「なんだ」
「中山道の宿では、御小休みにしても、御宿泊にしても、布団や茶碗などの用品が足りないと案じておりました」
喜太郎は、与右衛門に聞き返した。
「布団や茶碗のほかに、何が要るか」
「枕や膳椀、鍋、盆……」
与右衛門は、ぽつりぽつりと発声した。
「待て。記しておく」
喜太郎は、猫八に記録させた。
与右衛門は繰り返した。
「布団、枕、膳椀、鍋、盆、湯次、飯次、杓子、草履、草鞋、猪口、桶、飼葉、薪、提灯」
「それでおぬしは、宿で必要な備品も、わしに集めよと言いたいのか」
「いえ。宿場町の役人が、尾張家で必要備品を一括で買い上げして配ってくだされば、いちばん有り難いと申しておりましたのでお耳に入れたまでであります。難しければ、多くの村から集める方法も良いのではと、思います」
「買い上げできる物は買い、できぬ分は、村から借りることとする。話は終わった。それでよいか」
喜太郞は無駄話が嫌いだ。用件が済めば、さっさと終わらせたい。立ち上がろうとした。
与右衛門ほか、村役人が頭を下げた。
「まことに有り難うございました」
一件落着だ。皆が帰ってから、猫八が喜太郞に呟いた。
「喜太郞様、鵜多須にいる頃とは、別人のようでございますね。まるで水を得た魚のようで」
「猫八も、鵜多須の頃より顔色がいい」
「いえ。それがしは鵜多須の地も、名古屋と同じくらい好きですよよ」
喜太郞の脳裏に、鵜多須の田畑や、神明社の大きな森が浮かんだが、なんの郷愁もなかった。
3
文久元年八月一日(西暦一八六一年九月五日)
領内各地にいる代官を、名古屋大代官所に集めた。喜太郞を含めて十一人だ。
家老の竹腰志摩守が現れ、冒頭に挨拶をした。
「遠くからのご参集、誠にご苦労でござった。既にご周知のとおり、皇女和宮様の御下向につき、尾張家は領内の中山道筋の警固並びに六泊七昼食の世話を、公儀から命ぜられた。我々は準備に取りかからねばならぬ。すべては、名古屋大代官に任せてあるから、大代官から話してもらう」
十人の代官の顔が、一斉に喜太郎を見た。代官の中にも、「準備が遅い」と案じている者がいると聞く。喜太郎は、廊下に控えていた猫八を呼び、大きな紙を拡げた。
中山道の鵜沼から本山までの各宿場の名前が書いてあり、宿の名前の上には、丸、三角、二重丸の印がある。
「図は、尾張徳川家が担当する二十の宿場であり、宿泊地は二重丸、昼食は丸印、小休みの宿には、三角の印が記してござる」
代官たちは膝を前に進め、顔を突き出して図を眺めている。
図の記載は次のとおりだ。
○鵜沼-◎太田-△伏見-○御嵩-△細久手-◎大湫-○大井-◎中津川-△落合-△馬籠-◯妻籠-◎三留野-△野尻-◯須原-◎上松-○福島-△宮越-◎藪原-△奈良井-○贄川-本山宿(戸田松平家御領分)
「ご覧のとおり、宿泊地は二重丸の太田、大湫、中津川、三留野、上松、薮原の六宿。昼食は丸印の、鵜沼、御嵩、大井、妻籠、須原、福島、贄川の七宿である。この予定に合わせ、夜具、食器類の調達が不可欠である。ところが、通行人の数は、二万五千人と見積もられており、当然、宿近隣の村からの調達では間に合わぬ。尾張一円から必要数を調達し、中山道の宿へ運ばなければならぬ。そこで、結論を申し上げますれば、貴代官所管下の村々から、今から配布いたします数の人馬、並びに物品を揃え、定められた場所まで差し出して頂きたい」
喜太郎は、準備していた資料を猫八ほか手代たちに配らせた。
それぞれの代官所が集めるべき人馬や備品の数が、各代官に手渡された。備品とは、布団、枕、飯椀、汁碗、盆、皿、猪口、大釜、鍋、六枚折り屏風、湯桶、草履等、多岐に渡っている。
昨日のあいだに、大代官所の手代、同心をすべて集めて計算させた数字である。喜太郞が目で再確認し、修正すべきところは直したので数字の間違いは一つもない。
各代官の目は紙上に並んだ数字をひたすら目で追っている。
場は、静寂に包まれた。
険しい顔付きになる者、無表情の者、首を傾げる者がいる。
喜太郎は沈黙を打ち破って、説明を始めた。
「異例の大通行に対応するため、日頃、中山道の宿場の助郷となってはおらぬ村も、今回は全村、《加助郷》の村に指定し、すべての村から人馬を差し出し、御通行の継ぎ立てに従事していただく。差し出すべき備品並びに人馬数については、石高により割り振った。必要数を、貴代官所の陣屋に集めていただき、当方より触れ当て次第、差し出してもらう」
喜太郞は早口でまくしたてた。
浮かぬ顔をした代官が多いなかで、太田代官所の弓削勘三郎が余裕の表情をして、言葉を発した。調子が狂うほど、ゆっくりとしゃべる男である。
「まぁ、人や備品は、村役人に集めさせるからいいとして。わが太田宿の本陣が、宿泊所に割り当てられておる」
「ご不満か」
「皇女和宮様がご宿泊になるのであれば、ぜひ、尾張家からどんと金を出してもらって、豪勢に建て替えをしたい。特に、門が重要である。本陣は、門の立派さで決まると言っていい」
喜太郞は、鼻白む思いで弓削の意見を聞いた。
この欲どしい感じの男が、村人の年貢米を自ら肩代わりして領内から餓死者を出るのを防いでいる人気者とは、まことに信じがたい。
すると隣に座っていた家老の竹腰志摩守が、口を開いた。
「ええよ」
実に軽い返事だったから、ますます調子が狂った。
喜太郞は、竹腰を見たあとで、弓削の顔を眺めた。
にわかに弓削の顔に笑顔が広がる。
「志摩守様、まことに、ありがとうございます」
弓削が、大袈裟に平伏した。
「和宮様にお泊まりいただく以上、『さすがは尾張徳川様の御領地だ』と言われる本陣でなければのう」
竹腰が、ますます弓削を喜ばせる言葉を吐いた。
そもそも尾張徳川家は、何をおいても体面を大事にする。弓削は我が意を得たり、といったしたり顔で、ぐいと膝を前にいざらせた。
「まことにもって、志摩守様がおっしゃるとおり。わが太田の本陣は、樋は壊れ、瓦屋根は崩れそうで、さらには門が貧相ときております。公方様に嫁がれる貴人にお泊まりいただくには、実に心もとない。御三家筆頭の尾張家の体面が保てるよう、畳、襖も、すべて最高級なものに取り替えさせていただきます」
弓削と家老の言葉を聞いて、ほかの代官たちが、次々に、本陣、脇本陣、旅籠屋のあちこちを修繕したいと言い出しはじめた。
収拾がつかなくなり、喜太郞は、はなはだ閉口した。
早く場をお開きにしたい喜太郞の思いとはうらはらに、無駄話が延々と続いた。
喜太郞のいる大代官所は、百八十の村を管轄している。百八十の村を、四つの村あるいは六つの村に分け、三十七組を作った。
組ごとに総代を指名した。総代はおもに庄屋である。三十七人の庄屋を、連日のように呼んで人と物を集めるように命じた。
「そなたの庄内城北組から集めるべき数は、書き付けのとおりである」
喜太郞が庄屋に紙を渡したとき、庄内城北組の総代は、紙上に目を落としたまま硬直していた。
書き付けは、以下の通りだ。
布団 二百四十七枚
飯汁椀 五百三十五枚
平皿 六十九人前
屏風 八枚
人足 九十一人
****
数の多さに驚きすぎたのか、総代が口もきけぬようになっていたから、喜太郞は逆算のやり方を教えた。
「庄内城北組には、六つの村がある。組頭であるそなたがやるべきことは、村高により必要な数を割り振り、村役人に伝えることだけだ。物や人は、各村の役人に集めさせればよい」
いまなお、組の総代はよくわかっていないようだった。
「村高百石につき、布団は二枚差し出す。庄内城北組のいちばん大きな村は下飯田村で、村高は千五百三十四石。よって、下飯田村が差し出す布団の数は、六十二枚である」
算盤もなしで喜太郞がすらすらと数を申し渡したので、組頭はめんくらっていた。
「?」
勘定の得意な喜太郞からすれば、なぜ三桁ほどの勘定も即座にわかってもらえぬのか、もどかしい。だが、猫八に言わせれば、算盤なしで勘定ができるほうが変人であるというから、庄屋が普通なのだろう。
「紙を持ち帰り、家でゆっくり考えよ」
「そうさせていただきます」
庄屋がすごすごと帰っていった。
4
文久元年十月十五日(西暦一八六一年十一月十七日)
喜太郞は陣頭指揮をとるために、中津川へ入った。中山道の、江戸から数えれば四十五番目の宿場町である。京よりおよそ五十一里、江戸まで八十四里の位置にある。名古屋からは十六里で、二日かけてやってきた。
喜太郞は、『名古屋大代官所・特別出張所』の新しい看板の前で歩を止めた。仮小屋の入り口である。十月二十日に和宮様が京を出発される。中津川には十月二十九日にお泊まりになる予定である。
喜太郎の後ろに続いていた大代官所の猫八ら手代四人と、同心の四人も、立ち止まった。
喜太郎は、右手で看板に触れた。
木の看板は、かたことと、小さな音を立てて揺れた。
「ゆるんでおる」
斜め後ろにいた猫八を見据えながら、低い声で呟いた。
猫八は、急に慌てたような表情をした。喜太郞の張り詰めた気持ちが伝わったようだ。
「後ほど、びしっと固定しておきます。喜太郞様は緩んだものが嫌いですからね」
喜太郎の文句の持って行き場は、常に猫八だ。
仮小屋の二階へ上がった。本陣の近くに見える大泉寺の屋根や、寺の境内の木々を眺めた。
すると、階下から猫八が、声を掛けてきた。
「喜太郎様。お荷物は、どちらに置けばよろしいですか」
「二階へ持ってきてくれ」
「では、只今お持ちします」
音を立てて、猫八が荷物を運んできた。
「村役人の請書がこちらに入っております」
猫八が荷物の箱を開けている。箱を開けると、ぎゅうぎゅう詰めに入っていた請書の書状が、急に膨張したかのように盛り上がった。
上から数枚の紙がばらけて床に散らばった。
喜太郎は、請書の数枚を手に取った。
一方、猫八は外の景色の見える場所に立っている。
「喜太郎様。実に山並みがきれいですねぇ。中津川は、空も青くて、実にすがすがしい」
喜太郎は、旅気分の猫八の言葉など無視して、何枚かの請書の文面を、次々と眺めた。
どの請書も同じ文面である。一律の文面で請書を書かせたらしい。
「文面がすべて同じ請書は、どこの代官所が集めたものか」
喜太郎の言葉を聞いて、猫八が喜太郎の側に寄った。
「北方代官所で集められた請書でござりますよ。村から一人でも規範破りの者が出た場合には、村人全員が連帯で責任を負い、どのようなお咎めをも御受けします……という類いの文章、どこか古臭いように感じました」
喜太郎は、猫八を睨んだ。
「どこが古臭いのだ。むしろ、請書の正しい在り方だ。この一文を盛り込ませなかった我ら名古屋の大代官所のほうにこそ、落ち度があるわ」
「喜太郞様。もっと村人たちを信用しましょうよ。北方代官が古くさいんですよ。北方代官所の陣屋の前にある御触れ書きに、何と書いてあるかご存じですか」
「知らぬ」
「《木曽川徒渡りの者、斬り捨てにす》でございますよ。しかも、《斬り捨て》の文字だけ、異常に大きく書いてあるのです。まさに圧政です」
「ならば、猫八が北方代官ならば、どうするのだ。木曽川を下って材木を夜中に盗み、どこかで勝手に売り捌いて儲けようとする悪人は、どう取り締まればよいか」
「悪事を働く者は捕まえて、長い間、牢にでもぶち込んでおけば、それで充分な見せしめになりましょう。《斬り捨てにす》などという大げさな文言は嫌ですね。村人全員が、連帯で責任を負う従来の考え方も、いずれは消えていくと思います」
喜太郎は、猫八の意見が新しいのか、あるいは詰めが甘いのか、判断つきかねた。どちらかと言えば甘いように感じた。
「もしも、われら大代官所の館内の村人が、今回の和宮様御用において、問題を起こしたらどうするのか」
喜太郞の言葉に、猫八が首を傾けた。
「たとえば、どのような問題でございますか」
「荷物持ちの人間どもが、我等に反発して、誰一人として来ぬ、とか」
喜太郎は有り得ないとは思いつつも、問題を想定してみる。
すかさず猫八は、けらけらと笑った。
「喜太郎様。そうなったら、喜太郎様の出世願望は、即、途絶えますね」
「そんな程度で済めばよい。それこそ斬り捨てになる。お前も同罪」
喜太郎は、人差し指を猫八の胸の前に突き立てた。
「え。わっしも、死罪でございますか」
「当然であろう。国の一大行事が上手く進まなんだら、われらは、死罪であるわ」
言い終えぬうちに、階下から声が聞こえた。
「喜太郎様。中津川の宿役人が挨拶に来られました」
同心の大きな声が響き渡った。
「ふむ。下へ参る」
喜太郎は、階下に向けて、はっきりとした声で答えた。
挨拶に来た宿役人の一人は、笊に山盛り一杯の栗の実を携えていた。
「茹でてありますので、すぐにでも召し上がっていただけます」
猫八が嬉々として、差し出された栗の実の山を受け取っていた。
「遠慮のう、頂きます」
栗の笊を抱えた猫八の、子供のような無邪気な表情に、喜太郎は呆れた。
喜太郎は客二人と対峙した。一人は中津川の宿役人、もう一人は隣の落合宿から来た問屋だった。
「大代官様のご到着を、今か今かとお待ち申し上げておりました」
中津川の宿役人の顔が、疲労しているように見える。
近隣の助郷村の庄屋たちは、毎日のように招集され、打ち合わせと準備に明け暮れているという噂も耳に入っている。実際、宿場町の者どもは、ぐったり疲れている。
「準備状況は、いかがか。仮小屋建設といい、道の敷砂といい、ほぼ万端のようにお見受けするが」
喜太郎は尋ねた。
二人は同時に膝を動かして、喜太郎との距離を詰めた。
「整っておりますのは道と箱物だけで、まさに綱渡りのような状況です。果たして無事に綱を渡り切れるものか、憂慮すべき問題が生じております」
宿役人たちは、単なる挨拶に来た訳ではなかった。
喜太郎が中津川に到着して一刻も経たたぬうちに、すでに問題が持ち込まれている。
「して、どのような問題が生じておる?」
喜太郎は、二人の顔を交互に眺めた。
「荷運びの人手が六千人ほど足りぬ事態となっております」
予想していた事態でもある。村役人は続けた。
「十月三日に、御公儀の道中奉行より、最終的に通達をいただきました人馬必要数は、一宿、人足一万四千人、馬二千疋、馬士を二千人も準備せよという、想定よりも多い数でした。中津川宿は、落合宿と組合宿となっておりますので、中津川と落合宿を合わせますと、二万八千人の人足が必要でございます。宿の定助郷村から千三百人、御公儀が臨時で割り当てました臨時の助郷村から、六千五百人。それとは別に、大代官様の命にて尾州領各村から繰り込こんでいただいた人足が一万四千人でございますが、未だ六千人ほどの人が不足しています」
常に問題は、人手の足りなさだ。
「臨時の助郷村から六千五百人とは、意外と少ない数ではござらぬか。御公儀の道中奉行の指令で、信濃国の二百六十村、遠くは、伊勢国や越前国の村まで、臨時で助郷村に加えたと聞きましたがの」
落合宿の問屋が、更に喜太郎との距離を詰めた。
「遠国の人馬差し出し要請は、軒並み金銭代納となってしまいました。助郷制度の決まりを楯にとり、人馬を差し出せぬ代わりに、金銭を支払うと、皆が主張してきておるのでございます」
「つまり遠過ぎて、人を差し出せぬという訳か」
喜太郎には、策がある。
そもそも中津川へ出張所を設けた目的の一つは、人馬と備品の数を、調整するためである。
現場を見てから、足りない人馬や物を補う方策を取るのである。
無駄を省くために、やみくもに人馬を派遣するのではなく、《触れ当て次第、差し出させる》という、時をずらして数を調整する方法を、最初から考えてある。そのために飛脚網も組んである。
だが、不足の六千人という数は、意外に大きく感じた。
喜太郎は、猫八を振り返った。
「人の出動の要請は、まずは、われら大代官所管轄下の村からであるな。まだ触れ当てておらぬ村は、どこか」
猫八は懐から、書き付けを取り出した。多数の村の名が書いてある。
飛脚が翌日夕刻には名古屋へ伝達できると考えると、今から名古屋近郊の村に触れ当てたとしても、充分に間に合う。
猫八は書き付けを見ながら、村名を並べ立てた。
「如意村、砂子村、下ノ一色村、栄町村……」
「六千人になるように計算して、総代の村役人に触れ当て、中津川出発隊に組み入れよ」
喜太郎の言葉に、猫八は短く返事をした。
中津川村の役人は安堵していた。
「至極、助かりましてございます。ありがとうございます」
目前の客二人は、有り難そうに平伏した。
喜太郎が名古屋近在へ不足人馬を触れ当てた噂は、翌日には、木曽の山奥である福島や藪原、奈良井まで聞こえていったようで、連日、木曽の山から関係者が下って来ては、喜太郎の出張所に駆け込んできた。
人手が足りぬ、夜具が足りぬと、懇願に来る。
そのたびに喜太郎は、小牧、鳴海、清洲、佐屋といった各代官所に飛脚を送り、必要数を知らせるのであった。
猫八が、ずっと戸外を眺めていた。人の動きを見ているようであった。
「来ましたよ、来ましたよ。喜太郎様。荷運びの村人たちが大挙してやって来ます。道が混み合っておりまする。おお。なんと、わが大代官所管轄の村の幟(のぼり)が翻っておりますよ。川名村、御器所村、山崎村、それから、名古屋新田の文字が見えます。その次に、勝川村、古井村の旗も続いております。中津川まではるばる、よう来てくださいましたなぁ」
猫八は興奮して、一人で喋っている。
「うれしいなぁ。こうして村人たちが来てくれるなんて」
猫八という男、本当に気がいい男であると喜太郞は感心する。
「幟まで作るとは、まるで戦じゃな」
十月二十九日。
ついに和宮様ご一行の、京からの大行列が近づいてきた。
和宮様の外に、ご生母の勧行院、勅使の橋本宰相、右中将の橋本美麗がおられるはずである。
中津川本陣の主である市岡長右衛門が、門に立ち、貴賓を迎える支度をしている。
代官所の手代と同心たちは、行列に従いてくる荷物持ちの人たちを待ち構えていた。
牛に引かれた唐庇青糸車が、ひと際ぐんと目立ち、五十人ほどの屈強な侍が牛車の周りを取り囲んでいた。江戸の講武所から、選りすぐりの剣客が任命されたと聞いている。さらに外側を尾張徳川家の警固隊が行列に沿って進んできた。
中津川の林の中には、御土居下衆をはじめ数多くの同心が、ネズミ一匹逃さぬ構えで、見まわっているに違いなかった。
手代たちが疲れた荷物持ちの人たちを、問屋の世話役と一緒に介抱している。握り飯を与え、休ませていた。/p>
5
第一陣、第二陣とは桁違いの人数の、和宮様本隊の行列が三留野に到着し始めた。
雨が降っている。
煌びやかなはずの牛車や、金細工の施された黒漆の乗り物が、驟雨に霞んでいた。
問屋の前にある会所には、継ぎ送りをする荷物が、次々と運ばれてきた。
荷を置いた直後に、足元がふらついて、よろける者や、倒れ込む者がいて、場は混乱を極めている。混雑が甚だしく、人や荷物が擦れ違うのも、やっとである。
与右衛門は、疲れた人たちを介抱し、飲み水を与え、休憩場に連れて行く。人の世話が終われば、馬の世話もある。荷物の整理作業も必要だ。
四十八棟ある人夫小屋は、三留野に到着した人々と、明日から出発する人たちとで溢れかえっていた。その中に、荷物運搬の仕事を終えたら善光寺詣でを企てている川名村の源太がいた。畑仕事に慣れた身体とはいえ、荷物を担いで山道をあがる苦難は、体に堪えたらしい。床にころがって、ぼやいている。
「明日も須原まで運べといわれた。話が違う。おまけに、こんな人で溢れた仮小屋では眠られぬ。配られる握り飯は、いったいいつこしらえたのか、古い握り飯しかありつけないので、腹の具合も悪い」
海老のように背中を丸めて横になっている。
「源太さん、大丈夫か、腹が痛むのか」
源太とともにやってきた百姓の昭三郎が、源太に声をかけていた。
「あと一日の辛抱だ。明日、須原まで行けば、われらは解放される。荷物運びは終わるさ。そのあとは、善光寺へ。あと一日、なんとか頑張ろう」
そのわずか一刻あとで、異変が生じた。
「おい。見てみろ。隣の小屋から、続々と人が出て行くぞ」
小屋の中から、外を見ている人がいた。
「人が逃げて行く」
「何? 皆、脱出するのか。雨の中を、出て行くのか」
別の男が入口に駆け寄って行く。
「夜のうちに俺らも脱出せねば、また明日は使い倒されて殺されるやもしれぬ。明日になれば、さらに先まで荷物を運べと命じられるに決まっとる」
もはや小屋の中で、静から寝ている者など皆無だった。多くの人間が限界の状態にいた。
与右衛門のいる小屋からも、逃げだそうとする者がいた。
源太が起き上がった。腹痛がおさまったらしい。
「待て。逃げてもどうせ、山の中で捕まるだけだ。侍が警固している」
源太の真面目な性格が、与右衛門にも伝わった。
「ならば、お前が一人で荷物を持てばいい。荷物を背負って、須原でも、上松でも、なんなら江戸まで行け」
「われらは、お国のために仕事をしておるんじゃぞ」
「偉そうに。おまえ、何様じゃ」
「まあまあ、喧嘩はせずに」
仲裁に入った昭三郎が、今度は標的となった。
「邪魔だ」
昭三郎は、男に突き飛ばされた。
源太は我慢できず、昭三郎を突き飛ばした相手につかみかかる。周りの人間が寄ってたかって集まり、もみくちゃになった。
結果、源太は腹を蹴飛ばされてうずくまった。
「何をしておるんじゃ! しずまれ!」
与右衛門が大声を上げた。
「大丈夫か」
与右衛門が源太を介抱するため屈んだとたん、背中を誰かに蹴られた。
「おまえ、うるさいんだよ。会所の役人かなにか知らんが、百姓をなめやがって」
蹴られて地面に伏せると、起き上がった源太になぐさめられた。
「大丈夫か。あと一日がんばって任務を全うしよう。与右衛門さんも、善光寺に行こうよ」
与右衛門は、善光寺という言葉だけ聞こえて、意識を失った。
靄の中を歩いている感覚だけがあった。
白くて音のない世界を、ぽつりぽつりと歩いていた。
※
靄が切れ、視界が広がった。
広大な、寺の境内に出ていた。
夜が明けたばかりで辺りはまだ薄暗く、静まり返っている。そのうちに、砂利を踏みしめる音が聞こえた。一人の清冽な僧が、真っ直ぐに歩いてくる。一礼し、透き通るような声を上げている。
「今から本堂へご案内いたします。数珠を手にして、従いて来てください」
夢の中に源太がいた。与右衛門は従いていっていいのか、逡巡している。このまま、あの世に連れていかれるのではないか。
だが、いくつかの宿坊からは、次々と参詣者たちが出て来て、静かに整然と並んで、案内役の僧に従っている。
参詣者たちの中に、見知った顔が何人かいた。昭三郎の姿を見つけたので、呼びかけようとしたが、遠すぎて、声が届く距離ではない。善光寺の境内なのだと知った。
源太たちは、参詣者たちの行列に交じって、どんどん先へ進んでいく。
本堂にて、大勧進貫主と大本願上人の読経が始まった。
途中から、数百人いる参詣者たちも読経を始め、大合唱となった。
参詣者たちは、一心不乱に経を読む。広い本堂ばかりか、天にも届くような大合唱で、厳粛な空気に包まれる。
源太が体を震わせて法悦に浸っている姿を見た。感動に打ちひしがれる。
やがて、遠くから鐘の音が響いた。
静けさの中に、さらにもう一度、鐘が鳴らされた。
霞の中から荘厳な音が響いている。
「与右衛門さん、与右衛門さん」
別の世界から、声が聞こえた。
※
「あ。気がついたか」
目の前に、源太の顔があった。
「源太さん、善光寺の読経は感動的であったのぅ」
「え? これから行くんじゃろ。善光寺に行くから、辛い荷物持ちもがんばれる。しっかりしてくれ」
「あ、まだ善光寺には行っておらなんだか」
「与右衛門さんも一緒に行くかい?」
「いや。夢の中で行けたから、もういいよ」
「そうか。わしをかばってくれてありがとう。与右衛門さんがかばってくれなければ、死んでいたかもしれん」
6
十一月五日
喜太郞の仕事は、尾張家領地内のもっとも東、贄川宿と本山宿の間の橋で終了する。贄川宿は京より七十三里、江戸へ六十一里の距離にある。
境の橋の真ん中に、尾張徳川家領と、戸田松平家領地の境界がある。
人夫たちは本山宿まで進むが、尾張家による警固は境橋までだ。
最終の行列である第四陣の岩倉右少将様方の乗り物が境橋を渡って行く様子を、喜太郎と猫八は、行列のいちばん最後について見守っていた。
四陣に分かれた行列の中で、いちばん小規模である。
境橋の東側には、松平丹波守様の家臣たちが、びっしりと並んで立っていた。
輿や駕籠に乗った貴賓たちが次から次と境橋を通過していく情景を見たとき、喜太郎は、何事もなく御一行が尾張領を通り過ぎた事実を、静かに悟った。
猫八が宙に向かって呟き始めた。
「信濃松本の松平丹波守様。どうか御領内で、和宮様御一行の行列を、宜しくお願い申し上げます」
猫八が深々と長いお辞儀をしていた。さらにそのまま座り込んで、頭を地面に付けている。
無事に引き渡せる喜びを、全身で表す猫八だ。
「第三陣におられる和宮様は、すでに松平丹波守様の御領地は抜けて、その先の諏訪因幡守様の御領地へ到着しただろう」
喜太郎は、淡々と告げた。
「尾張家が六泊七昼食もの道中を受け持ったのに、戸田松平家は、たった一泊のご担当でござるか。不公平でござるな」
猫八が、顔を傾けて喜太郎を見た。
喜太郎は、今更ながらに道中の長さを思った。鵜沼宿から贄川宿まで、六泊七昼食分の道中はじつに長い。
7
十一月七日。中津川の仮小屋の名古屋大代官出張所の片付けをしていた。
喜太郞のもとへ猫八が近づいてきた。
「さきほど会所の与右衛門が、和宮様のお歌の写しを持ってこられました」
水谷与右衛門が、人夫たちの暴動に巻き込まれて怪我をした話は喜太郞の耳にも入っていた。
「与右衛門は、大丈夫か」
「腹や背中を蹴られて気を失ったようですが、復活したようです」
「難儀なことであったな」
「喜太郞様。和宮様の歌には、ご興味ありませんか」
喜太郞は貴人の歌を解する自信がなかった。勘定は得意だが、詩歌管弦の類いは苦手である。
だが、猫八から渡されるまま、歌の写しだという書き付けを開いた。猫八が補足した。
「三留野の本陣で手に入れたものだそうです。写し書きの、そのまた写し書きですが」
喜太郞は、紙片を開いた。
*
「旅衣 ぬれまさりけり 渡りゆく 心も細き 木曽のかけ橋」
*
一度、そしてもう一度、歌の字面を追った。
喜太郞は、不覚にも涙が目にたまるのを感じた。
大仕事が無事に終わり、安堵して気が緩んだせいかもしれなかった。目に溜まった涙が、頬をつたった。
「喜太郞様・・・・・・」
「すべてが終わり、はじめて和宮様のお気持ちに思いを馳せた」
喜太郞の本音である。
「わっしも、です」
「和宮様は、江戸への旅が心細く、泣いておられたのだ」
「お辛いですね」
喜太郞は何度も歌の文字を追った。涙が止まらなかった。お顔も拝見できぬ貴人の、心細さを思った。
喜太郞の勘定の才は、名古屋城で広く知れ渡ることとなった。
七年後の慶応四年(一八六八年)に喜太郞は勘定奉行に任じられたが、まもなく明治維新を迎えた。
(完)
202③年4月17日改訂版