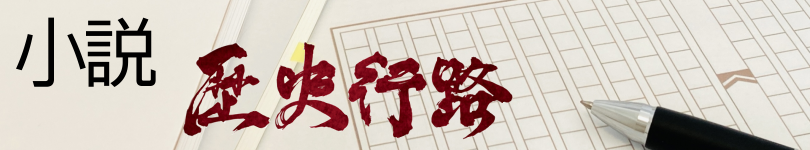平野 周
「空が濁っとるでにゃあか」
前田犬千代は、土手道から子の方角(北)を見て思わず声をあげた。
辺りはすくすくと伸びた稲田が広がって、風に稲の葉が揺れている、
天文十九年、夏――。
犬千代の目前には、その稲田を裂くように東海道が真っ直ぐに走っていた。そこを二十騎ほどの騎馬が駆けている。
雨が少なく、例年になく乾いた季節であった。風も強い。その騎馬の一団によるもうもうと舞う土煙によって、
――青い空が濁っている
ように感じた、と気づくのにそう時は掛からなかった。
「なんだら、ありゃあ?」
同時に、その一団の異様な風体に目を見張った。特に一団の頭と思しき先頭を疾駆する男は際立っていた。髪は大きな茶筅に結い、黄蘗色の帷子に朽葉色の半袴、腰には朱鞘の大刀ばかりでなく、いくつかの瓢箪と何か物の入った袋を吊っている。
「ひゃっほう~」
思わず奇声が出た。
「婆娑羅じゃ。婆娑羅じゃ」
二度繰り返した。よく分からないが、何か愉快な感じなのである。血が騒いで小躍りした。もう一度奇声を発しつつ、飛び上がって右手を天に突き出す。
その声が聞こえたのか、先頭を疾駆する男が犬千代の方を向いて、にっ、と笑ったように見えた。
犬千代は一瞬にして魅せられた。
「待ってちょう」
思わず騎馬の一団を追って駆けだしたい衝動に駆られていた。
だが彼我の距離は、およそ百間。そのうえ、一団は騎馬である。あっという間に犬千代の前を通り過ぎていった。
「ええのぅ~」
羨望が一気に沸きあがってきた。あの一団に加わりたいと痛烈に思ったのである。
犬千代は騎馬の一団が視界から消えても、その後ろ姿を追ってしばらく立ち尽くしたままだった。
犬千代(後の前田利家)は、このとき十三歳。元服前の小童である。
「孫四郎どん」
己を呼ぶ声に、はっ、と我に返った犬千代は、声のした方を見た。
呼んだのは、前田家に仕える弥一という下男である。
「殿さまが、お呼びだがね」
「親父どのがきゃ?」
はて何の用か、と訝りながら足を出し掛けたが、
「お、そうだぎゃ。いま街道を駆けて行った一団を知っておるきゃ」
「二十人ほどの婆娑羅の一団きゃ?」
犬千代が肯くと、
「ありゃあ、那古野の虚け殿だわ」
「虚け殿……?」
「ほうれ。先年元服した、那古野の織田三郎信長殿だぎゃ」
「おう。聞いたことがあるげな」
犬千代は先頭を走っていた男を思い出している。戦国の世に異装異形で疾駆するなど確かに変わり者ではありそうだ。
だが、弥一の言うように虚けとは思わなかった。むしろ大いに興味を惹かれたのである。
「あのお方が、織田三郎殿かや」
犬千代は信長の一団が去った後をもう一度見た。
「それより、殿さまが……」
「おお。そうじゃった」
犬千代は大急ぎで荒子の城に帰った。
「遅いぞ、四郎」
怒った声をあげたのは、普段温厚な兄蔵人利久である。不味い、客だな、と覚った犬千代は素直に謝ったが、
「にゃんだ。津田殿でねえか」
客間の正面に座っているのが、津田孫三郎と知って、思わず安堵の声をあげた。
実名を信家という。守山城主である。前田家が仕える林佐渡守秀貞の主筋である織田弾正忠家の重臣でもあった。
武勇に優れ、小豆坂七本槍に上げられている。利家が初めて槍の手ほどきを受けた人物でもあった。気さくな質で、何かと荒子の前田家を気に掛けてくれている。
「これ。今日は古渡殿の使いで見えられておるがや」
たしなめたのは、父縫殿助利昌だった。古渡殿とは、織田弾正忠家の当主備後守信秀のことである。
「孫四郎。大きゅうなったな」
「直に六尺に届くでなも」
犬千代は大きな声で答えて、そっぽを向いた。正直言って、孫四郎と呼ばれるのは好きではない。
元服前とはいえ、ここ一年でずんと背が伸びた犬千代は、五尺六寸(一七〇センチメートル)には達しているだろう。とっくに父や兄の背丈を越している。そのため、犬千代という幼名では具合が悪いと思ったのか、誰言うとなく孫四郎と呼ばれていた。利昌の四男だから四郎に異存はないが、「孫」が気に入らないのである。
前田家はもともと美濃国斎藤氏の一族で、安八郡前田村の出だという。尾張国に移ってきた事情は、犬千代もよく知らない。本家は、代々与十郎を名乗ったが、一族のうち主膳利隆が力を蓄えて隆盛となった。
利隆は背も高く美丈夫であったらしい。利隆を知る者たちは、犬千代に亡き利隆の像を重ねているのだろう。
利隆は犬千代の祖父である。故に孫四郎なのだが、
「親父殿より祖父様の方が、名が高い」
ことが犬千代は嫌なのである。
分家の荒子前田家の隆盛は、当然、本家筋の前田与十郎家には面白くない。利隆と違い温厚な利昌は、何かと本家を立てるようにしている。その苦労を知るだけに、犬千代は内心面白くないのだった。
「はっはっは。まだまだ、伸びそうだのう。来年辺り元服しても可笑しくない。どうだ、犬千代。織田三郎殿に仕えてみぬか」
「何と……!」
犬千代は思わず信家を見た。
「三郎殿は、武略に秀でた織田備後守殿の後嗣。小姓として仕えるに不足はないぞ」
犬千代は先ほど見た婆娑羅者の姿を思い返した。砂塵を巻き上げて走り去った騎馬の先頭を疾駆していた男である。
「承知なも」
頬が緩んでいる。
「これ。四郎」
二つ返事で受けた犬千代を、兄利久が吃驚したように制した。
その夜犬千代は、その利久と父利昌からしたたかに怒られた。
「三郎殿のところには、すでに藤八が出仕することになっておる」
「藤八がきゃ」
「おおよ。兄弟で同じお方に仕えて何とするがや」
藤八とは、犬千代の弟の五郎のことである。
「だけんど、藤八は佐脇家の者でねえか」
犬千代は口を尖らせた。兄弟で仕えても家が違うから良いではないかと思うのである。
五郎は養子にいって佐脇藤八郎良之と名乗っている。弟ながら、すでに元服を済ませていた。
「そりゃあ、ぬしらは六人兄弟。四番目から先は誰に仕えようとわしは構わんげな」
利昌が突き放したような言い方をするのは、犬千代が信長の元に出仕するのに反対なのである。その理由は、
「三郎殿より弟御の勘十郎殿がええと思うでなも」
「そうだぎゃ」
兄利久も勘十郎信行(信勝)を押している。
信長と信行は同母兄弟だが、性格は正反対であった。小姓を引き連れ、馬を乗り回す信長を動とするなら、静といってよい。
虚け殿と評判の信長と異なり、信行は物静かで挙措も礼儀正しく優雅であるらしい。そのうえ、林佐渡守も密かに信行派であるという。
「勘十郎殿にせい」
利昌と利久は、再三にわたって勧めたが、犬千代は、
「嫌じゃ。三郎殿がええ」
と言ってきかなかった。しかつめらしく城の中で控える信行の側より、婆娑羅な格好で疾駆する信長の方が楽しいと思う。
「勝手にせい」
利昌と利久は、根負けしたのか、ついに説得を諦めた。
翌、天文二十年正月(一月)――。
犬千代は那古野へ行った。信長に出仕するためである。
津田信家に付き添われ、大広間に赴いた犬千代は、やや緊張していたが、肝心の信長が居なかった。
「はて? 三郎殿はいずこへ行かれた」
「それがしにも分からぬ」
信家の問いに、守役の平手中務丞政秀が憮然としている。
「まさか、いつものように……」
信家が言い終わらぬうちに、
「おみゃあが、お犬かや。わしが三郎信長でや」
下座からどすどすという音とともに姿を現した信長は、昨年東海道を疾駆していたときの姿そのままだった。
「へ、お犬……!」
犬千代は面食らってしまったが、
「気に入った」
そう言って信長は、手にした餅を犬千代に放って、
「早う来い」
くるりと背を向けて、再びどすどすという音とともに去って行った。
「あ! 待ってちょう」
餅を掴んだ犬千代は、慌てて立ち上がると、信長の後を追う。
「はっはっは」
大広間には、津田信家の小気味よい笑い声が響いている。
外には信長と似た姿形の小姓達が待っていた。その中には、弟の佐脇藤八郎の顔もある。白い歯をみせて、嬉しそうに笑っていた。
「行くぞ」
一声、信長は馬に跨り、真っ先に駆け出していた。
慌てて犬千代は馬を探した。
こうして信長に出仕することとなったのだが、
「お犬きゃあ……」
正直言って犬千代は、そう呼ばれるのが好きではない。明らかに衆道を思わせるからだ。犬千代は信長の四つ年下だった。
こっそりと津田信家に相談すると、
「はっはっは。早う元服せい」
と、あっさり言われてしまった。
この年八月、犬千代は元服した。
「呼び慣れた孫四郎にせえ」
「嫌じゃ、又四郎がええ」
兄利久の声を無視して、通称を又四郎としたのには二つの理由がある。一つは父利昌の意を体して本家へ遠慮したもの。そしてもう一つは、時に孫三郎と呼ばれる信長に遠慮したものである。犬千代は妙に律儀なところがあった。
ところが、実名(諱)は利家となった。始め家久とするつもりだったのだが、
「前田の家名を上げるのは、犬千代かも知れぬぞ」
と言って、津田信家がひっくり返したのである。〈利〉は荒子前田家の通字で、〈家〉は烏帽子親の信家からもらったものである。本来なら〈家〉が上になるはずなのだ。
「お犬。馬を責めるぞ」
だが、信長の呼称は改まらなかった。
数居る小姓の中でも、特に信長は犬千代こと利家を気に入り、遠駆けのみならず、どこへ行くにも連れ回した。
利家も信長と一緒に居るのが楽しくてしかたない。
この年、又四郎利家は、信長の小姓として初陣している。尾張下四郡を支配する織田大和守家(清洲織田氏)の織田彦五郎勝秀と信長の間に起こった萱津の戦いである。そのとき利家は、信家に学んだ槍を振るい、敵の首一つを挙げる功を立てている。
利家が歩くと那古野城下の者たちが一斉に振り向く。
(へへっ。見とる、見とる)
利家には、その者たちの視線がむしろ心地よい。
「わしが、槍の又四郎でなも」
内心得意になって、小さくそう呟くと、大きく胸を反った。
利家が信長に仕えた翌年、備後守信秀が亡くなった。後を継いだ信長は、通称を上総介と改めた。
ちなみに利家は、
「よし。ならば、わしも」
とばかりに「又左衛門」と改めた。又四郞よりも、ぐっと大人びた響きがある。
これで「お犬」と呼ばれなくなるかと思ったが甘かった。相変わらず信長は、
「お犬、お犬」
と呼んで、側近く使った。
もっとも、総じて信長と小姓衆、そして小姓同士は仲が良かった。それというのも、信長自ら婆娑羅な格好で、先頭を切って馬を駆る、礫を使う、左右に分かれて戦の真似事をやる、ときには盗賊退治までやってのけた。
小姓衆同士だけでなく馬廻衆ともすぐに打ち解けた。年を経て小姓から馬廻りに転じた者も多かったからである。互いに腹蔵なく言い合い、ときに喧嘩もするが、すぐに仲も直る。彼らは信長一人を、
「御大将」
と呼んで、主君と仰ぎ直接信長と心情的に結びついていた。
若く力が漲る年頃である。利家にとって、小気味良いことこの上ない。若さを思う存分発散し、
「これほど楽しいものはない」
というのが、利家の実感であった。
あの日見た婆娑羅の集団は、やはり利家が思った通り、心弾むわくわくした集団だったのである。信行の小姓たちが、城の中で畏まってしかつめらしく仕えているという噂を聞くにつけ、信行に出仕しなくて良かったと心底から思うのだった。
信長たちは、傍から見れば確かに不良集団だったが、そこには暗黙のルールがあった。
領民の育てた作物を盗んだり、田畑を荒らしたりしないことである。
利家が出仕してしばらく経った頃――。
「喉が渇きましたずら」
佐脇藤八が、瓜をちぎって差し出した。信長の好物と知っていたからである。
だが、信長は烈火の如く怒った。差し出した藤八を打擲した後で、
「瓜の一つがと思うな。その瓜が銭になり、尾張国が栄える」
と言って、信長はその瓜の持ち主に銭を払った。その者が丹精込めて瓜を作り、それを売り歩いて銭を稼いでいるのを知っていたのだろう。
利家も小さいころから領民の生業を見聞きしている。早くから佐脇家に養子に出され、大切に育てられた藤八とは、そこが異なった。信長の行いは、当然のことだと思ったのである。
ただし、信長の食い方は褒められたものではない。町中でも人目憚らずかぶりついた。
この頃から少しずつ信長の周りは、ごっこではなく本物の戦が増えていった。とはいえ、馬を駆け、槍を振るい、命を懸ける戦は、利家にとって、ぞくぞくわくわくするものだった。信長のために働いていると思うと気が昂ぶるのである。
「虚け殿」
と、呼ばれた信長は、自ら戦場を駆け、声を嗄らし、槍を振るう。側には利家等小姓衆がぴたりと寄り添い勇猛果敢に戦った。
「織田上総介信長、侮るべからず」
清須城へ移った頃から周囲の評価は一変しつつある。
次第に尾張の実力者にのし上がっていく信長に、焦りを抱いたのが林佐渡守だった。佐渡守は、虚けと呼ばれた信長を嫌い、密かに勘十郎信行を当主に立てようと考えていたのである。
弘治二年五月、ついに佐渡守は叛旗を翻した。このとき、前田家は佐渡守に従っている。
十八歳になった利家は、あれからさらに背が伸びて、今では六尺を越える堂々たる偉丈夫である。信長を真似て朱塗りにした三間半の槍も縦横に使いこなせるようになっていた。
腕を撫していた利家は、信長に従い信行の家老柴田権六、林佐渡守の弟美作守の軍勢とぶつかった。八月二十四日のことで、
「稲生の戦い」
と、呼ばれるものである。このとき利家は、信行方の宮井勘兵衛という剛の者に、右目下を矢で射抜かれながらも討ち取るという大手柄を立てた。
合戦は信長方の勝利に終わり、利家は知行百貫を加増された。信行は末盛城に逼塞することとなる。
弟を討たれた林佐渡守は、気落ちしたのか早々に降伏し、佐渡守に従った前田家も大きな咎めはなかった。それを聞いて利家は、ほっと胸を撫で下ろし、益々信長に心服し傾斜していった。
だが、この頃から信長が、小姓衆と過ごす日々が少なくなっていった。
「退屈でなも」
利家は無聊をかこつようになった。
信長は織田弾正忠家の当主として、表向きの用事が増えたのである。婆娑羅で疾駆し、戦遊びをすることはもうなかった。まして、寝床でふざけることなど論外である。代わりに、拾阿弥という者を同朋として側近く召し使うようになった。
拾阿弥は、特に優れた芸能を持っているわけではない。信長の好きな茶の湯の手配や給仕、来訪者の案内接待をはじめ、身の回りの雑用に重用しているだけだと思う。
「かつては、わしらが行っていたことだぎゃ。なんで、拾阿弥に任せるづら」
当主となった信長と城下に屋敷を持って知行をもらうようになった小姓衆は、もはやかつての婆娑羅の集団でいることはできない。馬廻りになった者もいるし、嫁をもらった者もいるのだ。
頭ではわかっているのだが、
「寂しいずら」
利家の率直な気持ちだった。
そんなことを思っていると、やがて、拾阿弥に対して嫉妬に近い感情が湧いてくるのである。
こうした心情の変化は、はっきりそうだと言わなくても、相手には微妙に伝わるものなのかもしれない。
永禄二年が明けたある日、利家は佩刀を置いて厠に立った。帰って来ると小柄はあるが、笄がない。もともと笄は、刀の鞘に差して、頭のかゆい時とかに使うものだった。女性の飾りになったのは、江戸時代になってからのことである。
不審に思って辺りを見ると、拾阿弥の後ろ姿が見えた。他に人は見当たらない。
「待て」
かっ、と熱くなった利家は、拾阿弥を呼び止めた。
「何か御用でござりましょうか」
拾阿弥は立ち止まって振り向いた。顔に薄笑いが張り付いている、ように利家には見えた。
「おみゃー、わしの笄を取ったな」
声は押さえたが、怒気が漲るのはやむを得ない。
「さて、何の事でござりましょう」
「とぼけるなや」
さっ、と駆け寄った利家は、拾阿弥の襟を取って、中に手を入れようとした。笄を隠していると思ったのだ。だが拾阿弥は、
「無体なことはおやめください。手前が取ったところを見たのですか」
身を引いて遮るように言った。
「むっ……」
利家は思わず手が止まった。確かに、直接目撃したわけではない。状況から判断しただけである。身体の熱が急速に冷めていく。
「どうしたのだ」
そこに、偶然信長が通り合わせた。利家は内心安堵した。信長が拾阿弥を懲らしめてくれると思ったのだ。
「殿、聞いてくださりませ。又左殿の笄を手前が取ったと言うのです」
利家が口を開く前に、拾阿弥が縋らんばかりに信長に訴えた。
「取ったのか」
信長はあっさりと訊いた。
「滅相もない」
拾阿弥は手を振って否定した。
「取るところを見たのか、又左」
信長は利家に訊いた。
「いんや。と言うても、拾阿の他に誰も居らんがや」
信長なら信じてくれると思った。
「だからと言うて、手前を疑うとは、何という了見の狭さ」
拾阿弥は甲高い声で抗議するように言った。
「許してやれ、お犬」
信長はそう言って、拾阿弥を従えて去っていった。
その後ろ姿を見送りながら、利家は言いしれぬ寂しさに捕らわれていた。お犬、という呼び方も、拾阿弥の前では、何か汚されたような感じがしたのである。
やがて、
「槍の又左は、存外度量の狭い男」
という噂が立った。証拠も無いのに人を疑い、笄一つで憤激するというのである。
利家は面目を失い、悶々とした日を過ごした。
そんな利家に同情したのか、こっそりと真実を知らせてくれる者がいた。噂の元は拾阿弥で、ばかりか利家が使っていた笄を密かに隠し持っているというのだ。
「真かや!」
「間違いないがね」
その者の手引きで、利家は密かに拾阿弥の部屋に忍び込み、盗まれた笄を見つけた。
「拾阿のたあけ(戯け)め」
激怒した利家は、笄を掴むと拾阿弥を探し回る。
「居った」
ちょうど二の丸の櫓下を通るところだった。櫓の上には信長が、柴田権六勝家と卯の方角(東)を見ながら何事かを話し込んでいる。
「待て! 拾阿」
利家は激しい声で呼び止めた。その剣幕に異変を感じたのか、周りの者たちが一斉に利家を見た。その視線を感じ、信長と勝家も気付いて下を見ていると確信した。
「これに覚えがあるきゃ!」
利家は盗まれた笄を左手で示した。右手は刀の柄に掛かっている。
拾阿弥が、ひえっ、と叫んで、腰を抜かしたようにその場にへたり込んだ。驚愕の表情を見て、腰抜けが御大将の側に侍るのは許せぬ、と刀を抜いた。
「お犬、待て」
信長の止める声も聞かず、利家は拾阿弥を一刀のもとに斬り捨てた。
「お犬!」
信長は叫んで、櫓から一気に下に降り立った。勝家が後に続く。
「笄を盗んだんは、この者に違いないきゃ」
そう言って利家は、血に濡れた刀を引き、その場に片膝をついた。信長ならば自分の取った行為を分かってくれるはずである。
「ならばというて、ぬしが一存で成敗して良いというか」
「覚悟は出来ておるなも」
利家は下を向いて、やや首を伸ばした。絶対に斬るはずがない、と確信して。
「よし。望み通り、わしが成敗してくれる」
信長は近くの者から刀を奪うように抜いた。
「お待ちくだされ、殿」
勝家が慌てて止める。
「止めるな、権六」
「又左は一徹者で短気。責められるところはありましょうが、それでも数々の手柄のある者。それに免じて……」
「増長しておるのだ」
その言葉を聞いて、利家はやや顔をあげて信長を見た。
目が合った。利家の身体に冷たいものが走る。本気だ、と思った。利家の顔が下がる。これまで、と観念した。信長に斬られるなら本望だ、と思う。
「ではありましょうが、なにとぞご成敗だけはご容赦を」
勝家の必死の嘆願が続いた。その嘆願が効いたのか、
「ならば、成敗は勘弁してつかわす」
ほっ、とした。
(やはり御大将は、われのことを……)
と思ったとき、
「早々に清洲を去ね」
信長は忌々しそうに言って刀を返すと、足早にその場を去って行った。
「又佐。短慮はならぬぞ」
言い置いて勝家が信長の後を追う。
去り行く信長の後ろ姿を見て、利家はある名状し難い喪失感に襲われた。それを敢えて例えるなら、
「臍の緒が切れたような」
としか形容できなかっただろう。
信長とともに寝床でふざけ合い、婆娑羅で疾駆し、槍を縦横に振るう、そんなわくわくぞくぞくする濃密な日々は、二度と訪れることはないのではないか。そう思うと、
「御大将との主従も、これでわやだがね」
利家は全てが、もうどうでもよくなったのである。
そのまま、身一つで清州を去った。
(了)