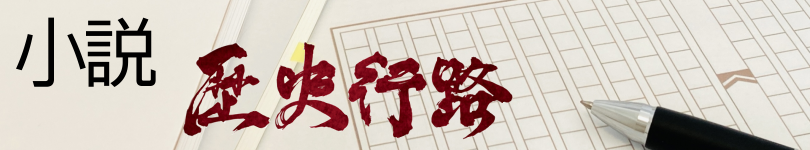平野 周
室町時代に起きた「長尾景春の乱」は、主に西関東を戦場として、文明八年から文明十二年まで足掛け五年に及ぶ内乱となった。
この乱は、関東における下剋上の走りともいわれている。
一
「困ったことだ……」
思わず独り言が出た。
江戸城静勝軒の居室から見える江戸湾は、ゆったりと凪いでいる。空は青く、雲一つ無い快晴であった。遠く房総の山脈もくっきりとした稜線が続いている。このように我が心も晴れ晴れとせぬものか、と太田道灌は思った。
道灌を悩ませているのは、山内上杉家の家宰職についてである。それまで家宰の職にあった長尾景信が亡くなったのが、昨年(文明五年)の六月二十三日(陰暦)。十余年に渡って上杉家を支えてきた。五十代という、まだまだこれからというときの突然の死で、それだけに、景信の死を惜しむ者は多く、この一年未だにその後任が定まらないのである。
山内上杉家の当主は顕定といった。まだ二十歳という若さである。
雲がでてきたようだ。ちぎった綿のように、ゆっくりと西から東へ流れていく。打ち寄せる波の音が、少し早くなったような気がした。
「景春どのか、忠景どのか……」
候補者は二人いる。一人は景信の嫡子で景春といい、今年二十三歳。そしてもう一人は、景信の弟で忠景という。今年四十七歳、働き盛りである。二人は叔父甥の関係でもあった。
忠景は兄の景信をよく支えてきた。当主顕定は、そんな忠景を推している。だが、山内上杉家に従う国衆の多くは、景春を推していた。景春の父、祖父と二代続けて家宰の職にあったからで、順当な流れといえよう。
――むしろ、忠景どのにという御屋形さま(顕定)の意中が、不思議でならぬわい
と、いう者が多い。
「無理もあるまい」
道灌も顕定の気持ちが分からぬわけではない。
今関東は、利根川を挟んで東に古河公方足利成氏、西に関東管領上杉顕定が対峙する形になっている。互いに引くに引けぬ立場にあり、合戦によって決着をつけなければ収まらない状況にあった。
十三歳で当主となったそんな顕定を景信はずっと守り立ててきた。顕定とすれば、同じく若い景春よりも、この間景信に従い、支え続けてきた忠景の経験と知識こそ必要としているのだろう。
だが、と道灌は思う。忠景に景信を継ぐだけの器量があるのだろうかと。
この間忠景は、兄景信を補佐してきた。兄を立て、兄に従い、兄の意を受け入れてきたのである。そのことがより慎重な人柄を形成し、いざというときの決断力に欠けるのではないか、と道灌には思えるのだった。
家宰は大局を見て判断しなければならない。ときに主君の意を押さえて、自ら火中の栗を拾う覚悟がなければならない。まして今は対立の時代である。合戦を辞せぬ果断な決断をしなければならないときは多いだろう。
対して景春は、決断力がある。若いが人望もある。
「景春どのの力を軽視しているのではないだろうか」
しょせん合戦は、兵の行うものである。軍勢を集められなければ勝てない。若さは未熟の裏返しだが、その分大きな伸び代を含んでいる。
景春は自分より二十歳ほど若いが、その能力は侮れない、と道灌は思っていた。経験を積めば父や祖父を越える人物になるのではないだろうか。
雲が大きくせり出して、やがて陽が隠れた。と見る間に、雲の流れが速くなり、白から薄墨色へ、そして、黒色が刻々と深くなっていく。
「われが乗り出すべきか」
調停にということである。早く決めねば、上杉家の命運を左右しかねない、とも思うのだった。
景信の後継者問題は、上杉側の動揺を呼び、そこにつけいる形で足利成氏の侵攻を許してしまった。昨年十一月のことで、拠点の五十子陣が襲われ、道灌の直接の主人上杉政真が戦死するという不幸に見舞われている。五十子陣が足利成氏軍に襲われたということも初めてのことだった。
政真は、上杉家の有力な一族で、扇谷上杉家の当主である。子がなかったため、叔父定正を後継者と定めた。それを気に父道真に代わって道灌が、扇谷上杉家の執事職を引き継ぐこととなる。道灌の地位も上杉家の中で上昇していたのである。
「うん……」
いつの間にか江戸湾に暗雲が垂れ込めていた。
気がつけば、空は黒一色に染まっている。浪が急いている、と思う間もなく、ざっ、と雨が来た。
視界が一気に暗くなって、雨脚が激しくなった。浪の動きも打ち返しが大きくなっている。
「夕立にしてはきつい」
ばらばらと雨滴が打ち込んでくる。今にも驟雨そのものが、道灌に挑むように迫ってくるような気がした。
「まさか、景春どのが謀反を……」
いや、それはあるまい、とすぐに不安を打ち消したが、
「そうなれば、嵐では収まらぬ」
最悪の事態を否定できずに、道灌は戸をぴたりと閉めた。胸の内に湧き上がる強い不安の念とともに。
二
二日後――。
「木戸三河守どのがお見えでござります」
取り次ぎの者の声がした。
「それでは、それがしはこれにて……」
打ち合わせを中断して、立ち上がろうとする斉藤新左衛門に、
「良いではないか。こなたもいっしょに」
と、制して道灌は、木戸三河守孝範を迎えた。
「おう。お揃いでござるか」
にこやかに会所に入ってきた孝範は、気軽に道灌の近くに座った。近習のいないことを知って、新左衛門が円座を手配する。
「豊島の入江の住み心地は、如何でござろうや?」
道灌が訊いた。
「ようござる。衆庶は三河島と呼ぶようになりましたわい」
そう言って孝範は、はは、と明るく笑った。衆庶という漢語を使うところが、いかにも孝範らしい。武人だが知識人でもある。
「三河守さまの島でござりますか」
と、言ったのは新左衛門で、感心の意が込められているようだ。いわゆる島ではない。島という語には限定地の意があり、そこが孝範の所領を表す地名として相応しいと感じたからであろう。
「それにしても、よく思い切られましたな」
孝範は伊豆にいる堀越公方の奉公衆であった。本来なら堀越の御所で近侍すべきなのだが、
「公方さまを見限ってござるわ」
と、道灌には、はっきりと言って、豊島の入江つまり三河島に隠棲してしまったのである。
堀越公方は、足利成氏に代わって関東を治めるべく京の幕府から遣わされた人物であった。山内上杉顕定の主君でもあり、当然、道灌にとっても主筋に当たる。
だが、風雲急を告げる関東に入って、それを鎮める意思も器量も無く、そのうえ京から従ってきた者たちが不和で、孝範はあっさりと愛想をつかした。
孝範は武人であり知識人であると同時に、京の歌壇でその名を知られた歌人でもあった。
「この後は、一人静かに歌など詠んで暮らしたい」
孝範は己の才が、このまま活かせぬのを不満に思っていたし、同時にそうした者にありがちな厭世観もたっぷりと持ち合わせた人物だった。
だが道灌は、孝範の才をこのまま埋もれさすのはもったいないと考えていたのである。
「今日お呼びだてしたのは他でもござらぬ。当城で歌合を開こうかと思いましてな」
「おお。それは重畳。是非に」
道灌の誘いに、孝範は相好を崩した。
歌合とは、遊戯の一つだが、優劣を競うものでもある。賽子、双六から囲碁、将棋はいうに及ばず闘茶、香合、詩合などなど、人は常に優劣を求め、勝負を決したい性質があるようだ。
歌合は和歌の知識を必要とし、それ自体が高い教養を持つ者でなければ、主催はおろか参加も叶わない。そこで歌われた和歌の水準が高ければ高いほど歌壇の評価に直結し、主催者のみならず、参加者の名も上がることとなる。
「父上の河越での歌合を見て、いつかはわれもと思うておりました」
「河越千句でござるな」
「はは。近頃はそのように呼ばれておりますな」
道灌の父道真が、川越城で歌合を行ったのは、文明二年正月十日のことで、そこでは千句という膨大な歌が詠まれた。この歌合は、歌壇の評価も高く、いまだ語り草になっているほどである。
孝範はその歌合に参加していないが、話を聞いて、
「次は、ぜひそれがしも」
と、自薦するとともに、
「いや、道灌どのが催されれば良いのだ」
と、強く勧められてもいたのだった。
「して、どなたを判者に?」
「それをご相談したかったのでござる」
判者とは、歌の優劣を判定する者のことである。歌合は、左右に分かれて一首ずつ組み合わせて、つど判者が優劣を判断する。高度な知識や経験を必要とし、並の者には務まらない。併せて、名声や権威も必要となる。歌合の要となる人物であった。
「とはいいながら、意中の人はござろう」
孝範は探るように訊いた。
「心敬どのに」
道灌は答えて頬を緩めた。
「おお、それは重畳」
孝範もまた我が意を得たりという表情である。
心敬とは号で、名を蓮海といい、その名の通り僧侶である。紀州の産、比叡山で修行し、権大僧都にまで上った人物で、正徹に和歌を学び、長らく京歌壇の中心人物として活躍した。応永十三年生まれの今年六十九歳になる。『心敬僧都十体和歌』など多くの著作を持ち、飯尾宗祇や猪苗代兼載の師でもある。文字通り歌壇の第一人者であった。
その心敬は、品河の商人鈴木道胤の招きを受けて関東に下って来た。応仁の乱を避けるためである。道真主催の川越千句にも参加していた。
京の戦乱が長引いていることから、相模国の浄業寺にしばらく滞在することにしたという。三年ほど前のことになる。浄業寺は、大山山麓の石蔵という地にあった。
「それでは、早速にご使者を立てましょう」
二人の話を聞いていた新左衛門は、その意を知り先回りしたが、
「いや。われが参ろうと思う」
「殿がご自身で参る、ということでございますか」
新左衛門は、やや驚いて訊ねた。
「それがようござる」
すかさず孝範が賛意を表した。
「そなたは、供をしてくれ」
道灌が命じると、はっ、と新左衛門が頭を下げた。
「方人は如何なさる」
歌合に参加して歌を詠む者のことを方人という。
「ここに名を記してござる。他に良き人物がござれば」
道灌は懐から紙片を取り出して孝範に渡した。方人の名が記してあるようだ。
「拝見」
と断って、孝範が紙片を見ると、そこには道真や鈴木道胤の名がなかった。
道灌と孝範は、一つ違いで同世代である。人選を見て孝範は、道灌の意を覚った。同時に、自身もまたこれを機に関東歌壇の世代交代を印象づけたいという昂揚を覚えた。
にっ、と笑って、
「よきかな。ここで開くのでござろう?」
「江戸湾を眺望しての歌合を、と考えております」
静勝軒は、道灌得意の建物で、平河の台地に築かれた江戸城の南側、江戸湾を一望できる絶好の位置にある。
江戸城も落成してすでに十七年。関東の名城として名がとどろいていた。ばかりか、静勝軒を始め、泊船亭、含雪斎、梅林などなどその風雅な造りも風流人士にとって、つとに知られたところとなっている。
「ますます、よきかな。十五人は欲しいところでござるな」
「さ候」
頬を崩した道灌は、だが、自信を持って大きく肯いた。
三
文明六年六月十七日(陰暦)、江戸城で歌合が行われた。
道灌にすれば念願の主催である。入念に準備してこの日を迎えた。
――関東歌壇に道灌あり
と、知らしめる機会にしようと考えてのことで、気合いの入れ方も一方ならぬものがあった。
「心敬さまがお見えです」
新左衛門が、心敬に寄り添って静勝軒の一室に案内してきた。高齢を考慮して、前日に迎えに行き、宿館で一泊してもらったものである。
「いやあ、筑波山が見事でござった。平川(後の隅田川)の蛇行も風雅に感じられましたぞ」
心敬は宿泊の礼を述べた後で、江戸周辺の感想を述べた。丸い穏やかな面立ちで、出家とはいえ頭部の後ろには髷がある。
「ありがたきお褒めの言葉。本日はよろしくお願い奉る」
道灌が自ら上座に案内すると、
「この城はほんに立派でござるな」
着座した心敬は、感に堪えぬように言って、
「築城から何年経ちましたかな」
と、訊いた。心敬は心底から江戸城を満喫したようだ。
「もう、十七年になりまする」
道灌は嬉しそうに答えた。
「そんなになりますか」
先に座に着いていた音誉上人が、感心したように言った。音誉は増上寺の長老で、
「城が出来たときは、びっくりしたものですが、近頃は風景に馴染み、拙僧も毎朝当城を眺めるのが楽しみですわい」
と、続けて、ふぉっ、ふおっ、とゆっくりと笑った。そのときである。
「や! 皆さまお揃いでござりますか。おお、心敬さまも……」
そう言って、ばつが悪そうに入ってきたのは卜厳である。道灌を慕い、自ら家臣となった僧侶で、六尺に近い大男だが、童顔でどこか憎めぬ愛嬌があった。そのため、道灌の使者を務めることが多く、昨日から糟屋館の主人扇谷上杉定正のもとに使いしていたものである。
「ご坊で全員揃いましたわい」
と言ったのは、奥山好継で河越に領地を持つ道灌の被官である。剃髪して宗善と名乗っていた。宗善にすれば、主人である道灌が、初めて主催する歌合である。非難の響きはない。いよいよ始まるか、という期待の籠もった声であった。
参加者は他に、道灌の弟資常、資忠とその子資雄、叔父資俊、珠阿、快承、宗信、瑞泉坊、恵仲、長治の合計十七名。判者は心敬で、その左側やや後ろに講師の平尹盛が座っている。
講師とは歌を詠み上げる者で、判者を務める者の弟子が、勉強のために行うことがある。尹盛は堀越公方の奉公衆だが、京に在った頃から心敬のもとへ足繁く通って師事していた。勉強のためというより、心敬の気心をよく知ることから心敬が指名したものである。
上座の心敬の左右には、孝範、道灌、音誉上人等々が交互に丸くなるように座っている。
「拙僧はここでござるな」
と、言って卜厳は、空いているところに座った。ちょうど心敬の真ん前になる形である。
「では、時刻もちょうど良いようでござれば、始めましょう」
季節は晩夏だが、関東は今が最も暑い時期である。陽の出ている時刻が長く、とにかくその間が異様に暑い。
今日も空は快晴で雲一つない。風が入るように静勝軒の戸はすべて開け放ってあった。潮騒は遠く静かである。磯の香りも強くない。
道灌が主催の挨拶を軽く述べて、心敬が心得を伝える。
「入れ札ですか」
座が一瞬どよめいた。歌の優劣を判者の判断ではなく出詠者の投票によって決めるというのである。歌合で入れ札とは極めて珍しい。
「ほっ、ほっ。武家風でよろしかろう」
心敬が満足げに言うと、座が静まり、反対する者はいなかった。
「始めに講師と拙僧の勝負から参りましょうかな」
心敬は柔らかく言って、外へ目を転じた。凪いだ江戸湾が遠く見晴るかせる。
そのとき一陣の涼風が、部屋を駆け抜けた。
「良い日和じゃ。直に秋に入るとはいえ、まだまだ夕立の恋しい頃でもありましょう。題は『海上の夕立』で参りましょう」
穏やかながら、心敬はきっぱりと言った。歌合では、〈季題〉といって春夏秋冬に関わるものが圧倒的である。
その題が判者の口から宣せられたとき、道灌と孝範は、すかさず夕立についての心象を探った。
道灌は目を閉じた。浮かんでくるのは、先日静勝軒で見た夕立の光景である。あのときも江戸湾は凪いでいた。だが突然、天気が急変して烈しい夕立となったのである。あのときは長尾景春のことを考えていた。
ややあって、
「よろしいか」
と、いう心敬の言葉で皆が思い思いに短冊へ筆を走らせる。
一番勝負は、左が平尹盛、右が心敬で、互いに歌い慣れた技巧的なものであった。歌合の場では、通称は用いない。短冊に書くには長すぎるからである。そのため、諱や号、短く縮めた略称を使う。尹盛は〈平盛〉という略称を用いている。結果は、平盛の勝ちとなった。
道灌、孝範は二番勝負である。
読師が、二人の短冊を受け取って講師の平盛に渡す。読師とは、歌の書かれた短冊や懐紙を講師に渡す役だが、誤読した際には訂正する役目も負う。
「では……」
咳払いを一つして、平盛が披講した。
まず、左の孝範の歌。
潮を吹く 沖の鯨の わざならで 一すぢくもる 夕立の空
(潮を吹き上げる沖の鯨の仕業であろうか。(空は)その一吹きで曇ってしまい、夕立となってしまった)
聞いた者たちの脳裏に、大きな鯨が、潮を吹いて海面で大きく飛び上がる光景が浮かんだ。
夕立と見紛うほどの潮を吹く巨鯨とは、どれほどの大きさであろうか。その雄大な様子に皆が感心しきりのとき、続いて道灌の歌が詠み上げられた。
うなばらや 水巻く龍の 雲の浪 はやくもかへす 夕立の雨
(海原を見よ。龍が海水を巻き上げたような雲が、浪のように動いて瞬く間に海へ落ちていくような夕立の雨ではないか)
「おお!」
座がどよめいた。海水を巻いて昇天し、そのまま空で波打つように動き回る豪壮な一匹の龍の動きが想像できたからである。
二つともに技巧を排した鮮烈な心象(イメージ)が特徴的で、同時に躍動の感じられる雄壮な歌であった。
「では」
心敬が促した。参加者が勝利した者を紙片に書く。それを道灌の近習が回収して回った。
それを受け取って平盛が、紙片を左右に分けて判者の心敬に渡した。
「勝利は道灌どの」
心敬が宣した。
「おお」
と、再び座がどよめいたが、それは驚きというよりも賛意の響きであった。
「いずれもお見事でござった。夕立を鯨の潮の吹き上げで詠むとは、壮大にして鮮烈な印象。まさに江戸湾に相応しい。さりながら、鯨という実在の生き物ではなく、この世ならぬ龍の昇天で夕立を詠むなど、これまた雄大豪放、いかにも武家の歌らしいというべきか。互いに眼前に浮かぶが如き、生き生きとした躍動溢れる歌でござったが、その大きさの違いで、みなさまが道灌どのの勝ちとすることに異存ござらぬ」
判者として心敬は、そう評したが、道灌は主催者の自分に花を持たせてくれたのではないか、と思っていた。歌は何を詠んでも良いが、やはり空想上の龍を詠んだことに内心忸怩たるものがあったからである。
だが道灌は、どうしても龍を詠みたかったのである。海上の夕立という題をもらったとき、先日の江戸湾を眺めたときの夕立の場面を思い出した。そのとき、脳裏にあったのは、山内上杉家の家宰職を巡る景春と忠景のことである。
その想いは、余の者には分かるまい、と道灌は思った。顕定の意が、忠景にある以上忠景の優位は動かないだろう。問題は忠景に決したとき、何かとてつもないことが起こるような漠然とした不安に捕らわれたのである。それが龍のイメージとなって表れたのだった。
四
「お見事でござりましたな」
と言って、孝範が寄ってきた。
歌合は終わって、すでに宴に移っている。歌合に限らず、催しものの後に酒宴を張ることは、いつの時代にも変わらぬ恒例といってよいだろう。
結句、歌合は一番から八番までが海上の夕立、九番から十六番までが深山納涼、十七番から二十四番までが連夜待恋の二季一雑、二十四番に渡って行われた。十七名のうち三名が二首詠んでいる。
判者の心敬は、
「歌の心を敬いなされよ」
最後にそう言って、寝室に引き取った。高齢ゆえ酒宴を遠慮したのである。
翌日、心敬は石蔵の浄業寺に帰るのだが、翌る年の四月十二日にその地で没することとなる。いつか戦乱が終息し、京へ帰る日を願い続けていたという。だが、ついにその願いが叶うことはなかった。江戸での歌合は、心敬にとって最後の輝きであったかもしれない。
音誉上人も高齢ゆえ、同じく宴席を断って増上寺へと帰っていった。
残った者たちは、こもごも昼の歌合のことや関東の情勢を話題に賑やかに語らっている。瓶子を持った女の動きが忙しい。
ぐっ、と一息に杯を干した道灌は、
「なんの。われの歌は、龍というこの世ならぬ生き物を歌った、いわばまやかしでござる」
「龍とは、買いかぶりではござりませぬか?」
「……!」
孝範の言葉は柔らかいものだったが、道灌はその意を覚って、驚いて孝範の目を見た。
「外に出ましょうかな」
孝範がやんわりと誘った。
二人は静勝軒を出てぶらぶらと歩いた。星が輝き、酒に酔った頬に心地よい風が吹きすぎていく。
すぐに江戸湾を間近に望むところに出た。期せずして二人の足が向いたということであろう。潮の香りが強くなった。遠く江戸湾の浪が、星明かりに煌めいている。
「関東に夕立がくるのは、早ければ今年。遅くとも明年のうちには」
「ご存じであったか」
と、道灌は言ったが、山内上杉家の家宰職を巡る争いは、誰もが知るところである。
「夕立次第では、堀越もずぶ濡れになることがありえますからな」
堀越公方が調停に乗り出すのではないか、と一瞬道灌は思ったが、同時に閃くものがあった。
「まさかご貴殿は……」
海上の夕立とは、山内上杉家の家宰職が忠景に決した後の景春の謀反のことを比喩したものではなかったか、と。
「道灌どのもそのように考えたのでござろう」
その通りである。そして、道灌は景春を〈龍〉と思い描いた。畏れたわけではないが、景春の若さと父、祖父二代に渡る家宰の力は侮れないと思ったのだ。〈臥竜〉と形容すべきだっただろうか。
「さりながら、龍とは買いかぶりでござろう」
孝範はもう一度そう言って、
「関東の国人にいかに人望があろうとも、せいぜいが、鯨ではござらぬか」
と、力を込めた。
「巨獣には違いないが、捕らえることは可能だと」
「いかにも。そして、船頭は道灌どの」
孝範はきっぱりと言った。
道灌は目を江戸湾の彼方に転じた。星明かりのもととはいえ、水平線はくっきりと分かる。
われにできるだろうか。仮に合戦となっても景春に負けることはない、という自負はある。道灌が畏れるのは、龍との戦いが長引き、古河の足利成氏が介入してくることである。夕立が嵐に発展すること、つまり、果てしない合戦の連鎖であった。
そして何よりも忠景の能力であった。年齢こそ家宰に相応しいが、その他は全て景信に劣っている、と道灌には思えるのである。それでも上杉顕定の信頼は厚いのだ。
仲裁案がないわけではない。忠景が家宰職に就任すると同時に武蔵国守護代職を景春に譲るという案である。そのことによって、忠景の次の家宰職を景春にすると暗に示すことができる。それなれば、景春を推す国人たちも矛を収めるだろう。
だが、忠景にその気は無く、顕定も望んでいないと道灌は見ていた。最後は合戦で決着をつけなければ治まらないだろう。
そのとき、星が一つ流れた。
はっ、として道灌は、孝範の目を見た。
「力をお貸し願えまいか」
今までの話で、孝範の力を覚ったのである。むろん、歌の能力ではない。武人としての先見の明、そして軍略の才を。
堀越公方のもとを去ったのも、己の力を活かせない境遇に不満を抱いているためだったことを思い出していた。
「はは。戦は道灌どのの得意とするところ」
その通りである。戦は野戦または攻城戦となるだろう。そのとき江戸城に道灌はいない。斉藤新左衛門や卜巌は、自らの帷幄に欲しい。嫡男の資忠はまだ若く、太田の一族のうちにもこれはという人物は見当たらない。
やがて、道灌の胸の内にあったもやもやが吹っ切れて腹が決まった。たとえ嵐になってもわれが収めればよいのだ。
「江戸城をお守り願えまいか。われが関東の野で戦うとき、この城をお預けする将が居らぬのです」
「道灌どの……」
一族でもなく、家臣でもなく、他人に城を預けるということは、よほどの信頼がなければできないことである。孝範は道灌の信頼がそこまでのものと知って、感極まって次の言葉が出てこなかった。
「われの留守をお任せできるのは、孝範どのをおいてござらぬ」
江戸城は、上杉方の最前線の城である。利根川を挟んで、古河公方方の名門千葉氏と睨み合っている。北の古豪豊島氏一族の動きも不穏である。道灌が留守と知れば、いつ攻められてもおかしくない。
道灌は孝範の手を取って、
「お願い申す」
と、強く言った。
「お引き受けいたしましょう」
孝範もまたその手を強く握り返して道灌を見た。
この後二人の友情は固く、道灌が広大な関東の沃野を縦横に疾駆しているとき、江戸城には常に木戸孝範の姿があった。
(了)
(参考文献)
「武士はなぜ歌を詠むか」(小川剛生、角川選書)
「太田道灌と長尾景春 中世武士選書43」(黒田基樹、戎光祥出版)
「下剋上」(黒田基樹、講談社現代新書)