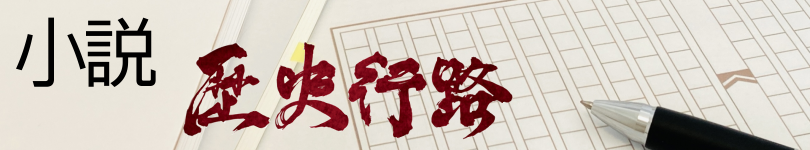山上 安見子
(1)
「なぜ、わたしは、こんな目にあっているのだろうか。ただ、思いのままに笑っただけなのに」
如月も末近いある日、利休は聚楽第近くの利休屋敷で、眠れぬまま朝を迎えた。障子の向こうがほの白い。満開の椿の香りが座敷にまで漂ってくる。清冽な香りに、利休の目が冴える。
横になったまま、自分の腹を撫でてみる。日頃節制しているせいか、この年齢にしてはたるみもなくすべすべとした暖かい肌が、掌を押し返す。
「ここに刀を突き立てて、そのまま一気にかっ捌くのだ」
もうとうに七十を越えた自分は、いつの日にかは病を得、家族に看取られながら逝くことになるのだろう。そのように漠然とおもっていたが、まさか武士でもない自分が切腹をすることになるとは、夢にだに思わなかった。
秀吉の小狡そうな顔が目に浮かぶ。お点前に集中していると見せかけて、こちらの表情をうかがっている。利休に教えを乞うと見せかけて、肚の中では、たかがお茶頭風情が偉そうにと小馬鹿にしている。それはお互いさまでは、あるのだが。
あの黄金の茶室。設計には、利休もたしかに力を貸した。茶入れ、水差し、建水、火箸。全て黄金でしつらえた。それどころか、畳縁も、襖も、天井も、障子の桟までも、すべて金色にまぶしく輝いている。
「下卑ている。やりすぎだ」
利休は心中密かに、思っていた。しかし、口に出すことは誰もがうらやむ今の地位、天下人のおしもおされぬ茶頭からの失脚を、意味する。
「ここに、後陽成帝をお迎えして茶会をする。点前は利休殿にお願いしたい」
利休はかしこまり、深々とお辞儀をした。
「帝の御前でお点前をする。それは確かに大変な名誉だ。しかし天皇はじめ、公家の方々は、このきらきらしい黄金の茶室を見て、なんと思われるだろうか」
それは想像に難くない。人目がなくなったところで堂上貴族たちが、目引き袖引きしての忍び笑いを、漏らすことであろう。利休は重い気分になる。
ついに後陽成帝を聚楽第にお迎えした時の秀吉の表情。猿回しの親方にご褒美をもらった時の、小猿そのものだった。あのとき俺は慎ましく目を伏せてはいたけれど、あまりのくだらなさに吹き出しそうだったわ。
秀吉が、台子の点前をしている利休の表情を盗み見ていることには、もちろん気づいていた。
しかし、利休は分厚い唇の端にも、大きな二重の目尻にも、ほんのわずかな表情の切れ端すらも漏らさぬよう、表情を固め続けた。
利休はつつがなく、亭主役をつとめた。公家衆は大げさに黄金の茶室を褒めそやしたが、本心は分かっている。どうせ田舎者の成金趣味とでも思っているのだろう。
ご一行が帰られた後、秀吉と利休は二人きりで跡見の茶席をもった。
「どうじゃこの黄金の茶室は。おぬしの侘び茶の対極をいってみたのだが、これはこれで面白かろう」
「さようですな。これはこれで、面白うございます」
「まことに、そう思っておるのか」
「嘘は申しませぬ」
そう。わたしは嘘は言ってはいない。しかし黄金色に照り映えたわたしの顔は、茶道の真髄である侘び錆びた美しさとは、無縁であったであろう。侘び茶とは、一切の無駄を削ぎ落とした冷え冷えとした美を、求めることなのだ。
究極を言えば、茶道具は世間が珍重する唐物だの東山御物だの、そんなことはどうでもよい。あり合わせの茶道具もどきで間に合わせれば、それで良いのだ。たとえそれが、道端に転がっていた欠け茶碗であっても、犬の水飲みであっても。
必要なのは、取り合わせの面白さ、それから自らをへりくだり、客をもてなす心なのだ。
そう考えると、黄金の茶道具であっても別に構わない。だから、これはこれで良いと、言ったのだ。嘘はついておらぬ。
利休の究めてきた茶道は、ついには「茶禅一味」にいきついていた。「茶禅一味」とは、茶も禅も、突き詰めていけば同じく人間形成の道であるとの意である。
権力者におもねり、感情を隠し、お追従を言わねばならない今の立場は、利休にはもはや堪え難いものとなっていた。
「殿下の茶は……」
その先は、どうしても言葉にできなかった。宗二は命をかけて天下人秀吉に直言し、死をもって己れの美学をつらぬいたのだ。
廊下から、軽い足音が聞こえる。遠慮がちに障子が明けられた。妻のりくだ。
「朝餉の支度ができました。おめしあがりくださいませ」
溜め息と共に、囁くような声でりくが語りかける。ふだんなら謡で鍛えたりくの声は、か細いながらもよく響くのだが、今朝は声にも張りがない。
「ああ」
利休も生返事しかできない。数時間後には、わたしはもうこの世には、いないのだから。朝餉を食べてもしかたない。切腹した後、腸から見苦しく流れ出たらどうするのだ。
りくは唇をかみしめたまま利休の返事を待っている。泣くまいと堪えている。俺が切腹した後、この女はどうするのだろう。まさか、秀吉はりくまで殺したりはしないだろう。
いやわからぬ。この頃の秀吉の目は、時折狂気の混じった残忍な光を、帯びることがある
(2)
聚楽第のすぐ近くにある、利休造作の不審庵は、秀吉のお気に入りだった。侘びた草庵風のしつらえは、秀吉が子ども時代を過ごした尾張の田舎舎を、思い起こさせるらしい。
本心を言えば、秀吉には豪壮華麗な造りの聚楽第はどこか居心地悪く、この田舎家を模した質素な庵に安らぎを覚えているのではなかろうか。利休はそんな気もしている。
その日は、もう大晦日も近い寒い日だった。冬の擦れた夕陽が、明かり取りの障子を通して、薄暗い不審庵を弱々しく照らしていた。
内部は手燭の灯りだけではほの暗く、正客の座に座った秀吉の表情は、ほとんど見えない。
秀吉は陰鬱な気分であるらしい。晩年に思いがけなく授かった鶴松の成長が思わしくない。ひ弱で病気ばかりしている。豊臣家を支える中心人物の弟秀長の病も長い。そして、何よりも秀吉にのしかかっているのは、大明国征服という途方もないまぼろしなのだ。
そのまぼろしは少しずつ輪郭が縁取られ、形作られて、いつしか秀吉の確信に変わった。
島津も北条も討ち果たした後、日本国内はほぼ秀吉のものとなった。応仁の乱に始まる長い争乱の時代は収まり、やっと平穏が訪れた。皆、ほっと胸を撫で下ろしている。百姓たちは、安心して田畑を耕し始めた。商人たちも活発に商いを始めている。
しかし、百年以上続いた争乱の時代は、刀を持つものたちの心に、荒ぶる気質を抜きがたく刻印している。何かに立ちむかって、戦わずにはいられないのだ。
それは、日本の隅々まで充満している。事あらば鎧刀、鉄砲弓矢を携えて決起したい荒くれどもが、焼け落ちた城跡や、うち捨てられた骸が折り重なる古戦場の、ここかしこに跋扈している。
その爆発しそうな不満をそらすため、彼らの鬱憤の矛先を、まず朝鮮国へ、そして明国へと向けようとしているのが、秀吉の企みである。
しかしながら、事は秀吉の思惑通りには運ばない。莫大な戦費、食糧や兵力の確保。そして、当然のことながら、強大な大明国に勝つ見込みは全くない。
秀吉子飼いの加藤や福島を除いては、そんな壮大な夢物語に、まともにつきあおうとする大名などいない。口先をあわせてはいても、実際には動こうとはしないのだ。秀吉は焦っていた。
利休は、真っ赤に熾った炭に触れないように、香を置いた。この季節にふさわしい、『黒坊』である。みっしりと重く鋭い香りが、秀吉の鼻孔をくすぐる。
床の花籠には、庭の白椿が無造作に投げ入れてある。
秀吉は、正客の座に胡座をかいて座っている。
「すまんが、今日は許してくれ。寒さでちと膝が痛んでおる」
「どうぞお楽に」
利休は茶道口から、順々に道具畳にお道具を運んでいった。今日は、黒楽の茶碗を使う。銘は「悪女」。楽長次郎に命じて焼かせた。薄暗い茶室の中の、ほのかな灯りが、艶やかな地肌にわずかに照り映える。楽茶碗はそこにあるだけで、幽かな光と人肌の温もりを茶室全体に放っていた。
秀吉は黙り込んだまま、じっと利休の点前を見つめていた。しかし、その目が見つめるものは、利休であって利休ではない。利休を包む釜の湯気のような、何かしら不可思議なもの。人知を越え、大自然を司る力とでも呼べばいいのだろうか。
それは秀吉を天下人と言われるまでに出世させてくれた、摩訶不思議な運命の流れだった。
ある時期まで、それは確かに秀吉と共にあった。その力は、一介の足軽に過ぎなかった秀吉を、天下人までのし上げてくれた。しかし、気がつくとそれはこつ然と消えていた。
ほとんど秀吉の意のままに操れたこの世が、急に生きにくくなり、何かしら大いなるものからの悪意さえも感じられる。秀吉は、惑っていた。
沈黙を破って、秀吉のしわがれた声がした。
「のう、利休。唐入りの事、どう思う」
利休の手はよどみなく動き、茶筅を振り続ける。振りながらも頭の中は、どう返答すべきか忙しく考えを巡らせている。
「どう、と仰せられても。手前にはまつりごとのことは分かりませぬ」
無難な答えが口から出た。
「私の仕事は、ただ旨い茶を点てることのみでございます」
炉に懸けた鬼霰の釜が、音を立てて鳴り始めた。始めはただしゅんしゅんと勢いのある音だったが、一旦お煮えがつくと、ヒューと、物哀しげな音に変わる。それは、この世ならぬあの世から吹く風のように、どこか禍々しい。
「わしはこの音はすかぬ」
秀吉は、なみなみと点てられたお薄を、ふうふうと息を吹きかけながら、のみ干した。
「そして、おぬしも分かっているだろうが、実はわしは茶の道も好かぬ。お点前の順番などどうでも良い。道具やお棚の扱いが、いちいち違うのも面倒でたまらぬ。ただ、熱い湯で旨い茶を点てればよいだけのことではないか」
利休の頬は動かない。ただ、半眼にした目を秀吉の膝のあたりに、さりげなく落とした。さあなんと答えようか。
利休は秀吉に分からぬよう、素早く瞬きをした後、小さく息を吸い込む。再び炭火の勢を増した炉から、煉り香の香りが重く立ち昇ってくる。
「あれほど見事な腕前を持ちながら、茶道がお嫌いとは。勿体ないことでございますな」
良かった。無難な答えが出てきた。
「世辞を言うではない」
利休の答えを、意地悪く待っていた秀吉の目が、なおも利休の横顔の表情を探っている。
「太閤様の腕前はさながら、野に伏す虎の如しでございます」
「どういう意味じゃ」
「お点前をなさっているときには、内に深く沈積し動かざる水のごときご様子であっても、ひとたび天下に事が起これば、刀を手に瞬時に躍り上がる力を秘めておられる。天晴れ日の本一の、武士のお点前ぶりでございます」
秀吉の目がふと緩む。満更でもないらしい。
「それに」
「なんだ利休。申してみよ」
「私はこの頃、つくづくと思うのです。殿下のおっしゃるように、茶の湯とは、ただ湯をわかし、茶をたてて飲むだけのことだと。それだけが茶の湯ではないかと」
「なんじゃ、わしの言ったとおりではないか」
「さすがに、天下様。茶の湯の真髄を捉えておられます」
その後の秀吉は終始機嫌が良く、薄茶の稽古を始めた。珍しく自ら進んで薄茶を点て、利休にすすめた。
「結構な、お点前でございます」
「そうか。うまいか」
「美味しゅうございます」
「こうして茶を点てていると、心の憂さも晴れる気がする。なかなか、茶の湯も良いものじゃなあ」
「はい。なかなかに、良きものにございます」
ひとしきり、誰彼の噂話をしたのち、秀吉はやっと退出した。茶室の片付けをしながら、利休の表情は、苦々しげになる。
「一体、いつまであの猿めに、おべんちゃらを言わないといけないのだ」
「あやつの点前なぞ、田舎臭くてみておられぬわ。つい、この前までは信長の草履取りとして、地べたに這いつくばっておったくせに」
秀吉の使った茶巾には、緑色の粘いものがべっとりと、ついている。
「お湯でのすすぎが足りぬのだ。ゆっくりと手のひらで茶碗の中の湯を回し、客の飲み残した茶を湯に含ませる。それから建水に湯をこぼす。それが、短気なあやつにはできぬ」
利休は金だらいに張った水で、手荒く茶巾をゆすぐ。
「一番の欠点は、茶の点て方が半端なことだ。茶がダマになって茶碗の縁にこびりついている。なんとも、田舎ぶりの茶よのう」
口元に思わず苦笑いが浮かぶが、利休はあわてて分厚い唇を引きしめた。
(3)
そこここに椿が咲き始めたころ、利休は久しぶりに堺へ戻った。聚楽第での茶事の予定は当分ない。利休は秀吉との心の戦さに疲れ果てていた。家の蒸し風呂で朝風呂を楽しむ。利休はゆっくり手足を伸ばした。朝の日差しが湯気の向こうにチラチラと揺れる。
利休はこんなにも疲労困憊している自分を、我ながら不憫に思った。
『このごろ、茶を点てても一つも面白くない、四六時中、太閤が配下の大名を連れてやってくる。茶室の中でまつりごとの密談をする。
会津の蒲生は一揆に手を焼いているとか、影で糸を引いてるのは伊達だとか。
俺は聞かないフリをするが、太閤はわざと俺の意見を聞きたがる。
俺は、一揆の裏にいるのは三成だと思っている。蒲生と伊達を罠にはめようとしているのだ。
しかし、下手なことを言いでもしたら、即刻ご不興を被り、どんな目に会わされるか知れない。ああ、いやだ。点前だけに集中したい。静かに茶の道に精進したい』
利休は屋敷内にある茶室に向かった。
この茶室は、にじり口、藁をすき込んだ壁、掛け軸を掛けられないほど低い天井、小さめな障子窓など、山崎の待庵を模してしつらえている。
利休は、自分がこれまで関わってきたどれよりも、この茶室を好んでいる。この茶室の薄暗い一隅で誰の目も気にせず、無心に茶を点てる時間が一番心安らぐ。
一自服しよう。そうすれば、聚楽第でのややこしいあれこれを忘れられる。利休は、とにかく茶室に座りたかった。
茶室の周りを見慣れない少女が掃除をしている。まだほんの十くらいだろうか。漆黒の髪を耳の下で切り揃え、テキパキと箒を動かしている。手足はすんなりと長く、均整のとれた体つきをしている。
少女は利休の気配に気づくと掃除の手を休め、利休を見つめた。鼻筋の通った顔立ちの、その瞳にはわずかに青みがかっている。南蛮人の血が混じっているのだろうか。白い頬にはほんのりとそばかすが浮いていた。
「誰だ、お前は」
「ミツ」
少女の声は凛と涼しく、利休の耳に心地よく響いた。
「初めてみる顔だがいつから、ここに」
「三日前から。セミナリオの司教様がお世話してくださいました」
「そうか」
ミツの言葉には不思議な響きが混じっている。バテレンの神父たちが話す片言の日本語の響きだ。
利休はなおも少女を見つめる。ここ堺は世界に開けた貿易港で、様々な国の船が行き交っている。この少女はどうやら、南蛮船の船員の血をひいているらしい。
「父や母はどうした」
「わかりません。赤子のときにセミナリオの戸口に捨てられていたそうです」
少女の顔に辛さが滲む。今までどんなに悲しい思いをしてきたか、利休には察せられた。少女は口をつぐんだ。
「お前は、茶の湯を知っているか」
利休は、この少女ともっと話してみたくなっていた。若い頃、ミツに顔立ちがよく似た亜麻色の髪の青い目の少女を堺の町のどこかで見かけた気がする。その少女は宣教師が持ち込んだ聖母マリアの周りに舞う天使たちの絵によく似ていた。ミツにもその面影がある。
「知っております。濃い緑色の飲み物を皆で回し飲みするのでございましょう。神父様も時々、信徒の方たちと一緒にのんでおられました」
「それは、お濃茶だな。お前は、飲んだことはないのか」
「ありませぬ。私はそんな身分ではございませんから」
「では、馳走してやるから、ついておいで。回し飲みせず、一人で飲む薄茶だがな」
利休は茶室のにじり口から、這いのぼる。この時代の日本人にしては大柄な利休は、ずいぶんと身を縮めないとくぐれない。
「飲ましてやるから入っておいで」
驚いて動けなくなっている少女を、利休は重ねて誘った。
「本当に、私が入ってよいのですか」
「わしが、よいと言っているのだ。いいから来なさい」
少女は箒を置いて、おそるおそるにじり口から入ってきた。
早春の眩しい日差しの中にいたミツの目は茶室内部の仄暗さに一瞬見えなくなったのか、怯えたようにうずくまってしまった。
「そこへすわれ」
利休は怖がらせないように、優しく声をかけた。ミツは手探りで床の前まで進み、体を直して正座をした。
「ほほう、正座ができるのか」
「はい。すこしなら」
利休は黙したまま茶筅を動かした。茶釜にはお煮えがつき、朝のまだ冷たい空気に白い蒸気が筋となって立ち上っている。利休は茶筅を振る手を止めた。
「そこの振り出しに入っているこんぺいとうをお食べ。南蛮伝来の菓子だ。甘くて美味しいぞ」
ミツは振り出しを手探りで回し、掌にこんぺいとうを受けた。なにやらイガイガが角のように立っているが、かまわず口の中に入れた。甘い。こんなに美味しいものがこの世にあるのか。口の中に広がるこの味は痺れるほど甘い。
「美味しいか」
ミツはこっくりとうなずいた。利休は黒びかりがするほど漆黒の、ぼってりとした茶碗を手に取った。茶釜の湯を注ぎ、手のひらで回しながら、ゆったりと温める。その仕草は、まるで誰かの面影を愛おしむようだ。
「この茶碗はわしが、長次郎という男に命じて焼かせたものだ。どういうわけかは分からぬが、誰いうともなく『悪女』という銘がついた。多分、あのお方のことだろう。
この茶碗は少し肉厚の剛いなりをしているが、手のひらに取ると以外に素直に馴染むのだ。
わしはあのお方は悪女とは言えぬのではないかと思っておる。なかなかに心の優しい方だ」
ミツには、あの方とは誰のことかはわからない。ただ、ご主人様が心を寄せている高貴な女性のことだろうかと、思いながら黙って聞いている。
茶筅の音が絶えた。ただ、釜鳴の音だけが低く響いている。利休の目は虚空を眺め、誰かの面影を追っているかのようだ。
「あのう」
利休は、我にかえった。利休の手が再び動き、茶筅を振る。薄茶が点ちあがった。
「さあ、一服飲んでみなさい」
ミツは恐る恐る茶碗を手に取り、薄緑色の液体を飲んでみた。
「苦い。でも、甘い」
「そうか。苦いが、甘いか」
利休は声を立てて笑った。つられてミツも笑った。二人の屈託のない笑い声が、茶室に満ちた。
その後は長い沈黙が続いた。利休は放心したように炉の釜を見つめている。炭火がよく熾って、釜の湯はしゅんしゅん煮えたぎり、遠くの松林を風が吹き抜けていくような釜鳴りが、二畳の茶室に静かに響いている。
利休はなおも、放心している。ミツは居心地が悪くなった。この家の主人の命とは言え、与えられた仕事を放り出して茶室に上がり込んで茶をいただいている。朋輩に見つけられたら何を言われるか分からない。
「あのう。ご主人様」
ミツはおそるおそる声をかけた。利休ははっと、目を上げた。ここはどこなのだろう。利休は一瞬分からないようだった。そして、自分の居場所を悟り、安堵の溜め息を小さくもらした。
「ああ。おまえだったか。わしの相手をしてくれて、すまぬのう。もう仕事にもどってよいぞ」
ミツはにじり口からするりと抜け出し、ぴょこんとおじぎをすると、箒を持って再び掃除を始めた。掃きながら小さく歌を歌っている。セミナリオで聞き覚えた聖歌らしかった。その清らかな歌声を聴きながら、利休は暗い目のまま、長い間茶室に座り続けていた。
(4)
思い惑う心のまま、利休は再び聚楽第の利休屋敷に戻った。煌びやかな聚楽第のすぐ近くではあっても、そこだけはまるで趣の違う空間に思える。
青葉が萌える五月になっても、利休屋敷には、薄暗い影がたゆとうている。山深くにある禅寺のように深い沈黙に沈み込んでいる。灰色、薄墨色、黒。くすんだ色調の不審庵は、今の利休の心模様そのままだった。
辺りに誰も居ないのを見計らって、利休は表情を繕うのをやめる。人前では唇の端を押し下げ、無表情を装っている。無論、家人の前でも。気を許した何気ない言葉が外に漏れ、悪意を纏って拡散していくのが怖いのだ。
聚楽第では、うなずき一つ、表情一つ、相づち一つがとんでもない命取りになる可能性がある。
今日は茶事の予定がない。利休は早々に不審庵の中に逃げ込んだ。点前畳に座り、風呂釜の炭火をぼんやりと眺めていた。いつのまにか長い時間がたったらしい。妻のりきの慌てた声が聞こえて来た。
「関白様です」
ほとんど同時に、にじり口から秀吉の顔が覗いた。不意をついてやったぞとでもいうように、少し得意げな表情である。
「利休、かまわぬか」
利休は慎ましく目を伏せる。
「いよいよ九州の名護屋に、築城を始めたぞ。唐入りのためにな。能舞台も、茶室もしつらえる。誰も見たこともないような豪奢な城を普請する。利休も来るな」
秀吉の目が鋭く利休の表情を探っている。利休は、唇を引き締め黙って頷いた。
他に選択の余地はない。最高権力者の命令は絶対である。秀吉の全身から殺気に似たものが抜けるのが分かる。拒めば命はなかっただろう。
「そこから朝鮮を経て明国に至る。彼の国には焼き物の名物もたんとあろう。青磁に天目、牧谿の水墨画も手に入れようぞ。それをつかって大明国の都で茶会をしよう」
「楽しみにございますなあ」
利休は、しいて楽しげな声を出す。
秀吉は、何回もうなずいた。
「わしの夢はそれだけではない。明国の次には、天竺や南蛮までもわが領土とするのだ。そして、我が子秀頼にその国を継がせる」
利休は驚いた。秀吉の目が曜変天目の、あの玉虫色に輝いているではないか。遠い昔、安土城で初めて会った頃のように。亡き信長公を憧れの眼差しで見つめていた藤吉郎時代に戻ったように。
「帰る」
秀吉は不意に立ち上がり、にじり口を蹲って一旦外に出たが、ふいに思いついたように顔をのぞかせた。
「来いよ、必ず来いよ」
どこか子供じみた口調で念を押し、慌ただしく歩き出した。
「大明征伐か。なんと途方もないことを思いついたものだ」
利休は、小声で一人ごとを言い、口元をつぼめ少し笑った。笑い声が漏れた。そのうちに笑いが笑いを呼び、利休は笑い続けた。笑いはなかなか収まらなかった。
「天竺に、南蛮だと。馬鹿げたことを。何を考えておられるのやら。馬鹿じゃ。うつけじゃ」
利休は独り言を言いながら、なおも笑った。独り言は、やがて大きくなった。しまいには涙を流しながら大笑いをした。狂気さえも感じられる利休の笑い声は、うす暗い茶室に不吉に響いた。
ようやくに笑いが少し収まったとき、不審庵の外で何者かが動く気配がした。利休の背に冷たいものが流れた。
『誰かが、聞いていた』
その嫌な感じを振り払うように、利休は茶を点て、一人喫した。
数日後、大徳寺の古渓老師が訪ねて来た。
「巷では、悪い噂がながれているそうだ」
利休はギクリと生唾を飲み込んだ。
「利休殿が、唐御陣に反対しているそうな、と。それどころか、成功するはずがないといいふらしているそうな、と」
利休は全身が震えた。
『やはり、誰かがあのとき様子を窺っていたのか』
用心深い利休の、ほんのちょっとした気の弛みだった。独り言を言いつつ笑っただけだった。その様子を大げさなものにして流しているのは、大方あの男だろう。
「太閤殿は、たいそうお腹立ちらしい」
利休は言葉を発せなかった。この場も誰かに盗み聞きされているかもしれない。利休はただ黙ってうなずいた。古渓老師も利休の気持ちを察した。
「疑いは、そのうち晴れようぞ。わしの時もそうであった。きっと、天が味方してくれる」
「私は、そのようなことは申しては、おりません。ただ……」
「ただ、どうされた」
「ただ、いつまでも戦がなくならないこの世のあまりの愚かさに、呵々大笑したまで」
「笑われたか」
「笑いました」
和尚も相好を崩す。
「ただ、笑ったまでのこと」
「たったそれだけのことなのか」
「はい。それだけのこと」
「しかしのう」
古渓和尚は真顔に戻った。
「時節柄、以後はくれぐれもご油断なきようにな」
「承知」
利休は、深々と頷いた。
しかしながら、その夜から利休は眠れなくなった。天井の節穴から誰かが覗き見をしているのではないか。障子の向こうで誰かが立ち聞きをしているのではないか。
寝苦しい夜更け、ふと気がつくと暗闇の向こうから、秀吉が幾分茶目っけの混じった目でこちらを見ている。
『さあどうする利休』
秀吉は利休の惑乱ぶりを楽しんでいるかのようだった。
利休は思い惑った。どうすれば、自分を取り巻く悪意から逃れられるのか。秀吉の誤解を解けるのか。
不意に生まれ育った堺の海の深い碧が、鮮やかに脳裏によみがえった。
「帰ろう。堺へ。堺の海を眺めたら、少しは気が晴れるかもしれぬ。海が穏やかな今時分は、はるばる南蛮船がやってきているかもしれない」
利休は病気療養のためと称して、再び堺の自宅に戻った。
(5)
堺は今日も賑やかだった。物売りの声、謡の練習をする声、大道芸人たちの鉦や太鼓。行き交う異国人たちの言葉。
生まれ育った堺に帰ってくると、利休は表情を繕うのをやめ、呆然と何かに戸惑う老人の顔になった。巨大な権力の前に身を竦める哀れな男の顔になった。肩を落として、賑わう通りをとぼとぼと歩く。信長、秀吉の茶頭として権勢を振るった男の姿はどこにもなかった。
肩をいからせ、仕官の口を探して歩き回る浪人たち。浮かれ女、芸人、乞食坊主。明や朝鮮から渡って来た者。呂宋人、シャム人。それより遥か遠くからやって来た南蛮人たちが、耳慣れぬ言葉を大声でいい交わしている。
店には絹、緞子、繻子の豪奢な小袖。外国の果物、ギヤマンの器。唐渡りと称する茶道具屋。どこの国からやってきたのか一目ではわからない男たち、女たち。
そんな雑踏の中を利休は人ごみに流されあてもなく歩いた。歩き回るうちに、今、自分に見えている光景が現実なのか、それともうつつなのか、わからなくなってきた。
ここは堺なのか、日本なのか。それとも、天竺か南蛮か。もしかしたら異界に紛れ込んでしまったのか。生まれ育った堺の地なのだが、今の利休は異境を彷徨っているような頼りない心持ちがしていた。
「ご主人様」
可愛らしい声がすぐ近くで聞こえてきた。ミツだった。
「何回呼んでも、気がつかれませんでした。どうされたのですか」
利休の体から急に力が抜けた。
「ミツか」
そう言うなり、利休は立ちくらみを起こして、その場にしゃがみ込んでしまった。そのまま、利休は気を失った。
気がつくと、利休はセミナリオの中に横たわっていた。ステンドグラスを通して、早春の日差しがとりどりの色に染まって降り注いでいる。
幼子イエス、ミツによく似た天使を従えた慈母マリア。受難のイエス、復活のイエス。堺生まれの利休は、若い頃友に誘われセミナリオに通ったことがある。遠くポルトガルからやって来たパードレが、イエスの生涯を語ってくれたのう。そんなことをぼんやりと思い出しながら、利休はまどろんでいた。
ミツが、葡萄酒を持って来た。濃い牡丹色のギヤマンのグラスが光りを浴びてきらきらと輝く。
「うつくしいのう」
意識が少しはっきりしてきた。セミナリオの中には利休とミツしかいない。ミツは心配そうに利休を見つめている。
「わしは、倒れたのか」
ミツがうなずく。
「この教会のすぐ近くだったから、みんなでここへ運んで来た」
心配げに利休を見つめるミツの大きな瞳は、深い海の色が、たゆとう。天目茶碗の色に似ていて、美しい。
「パードレが店にも、使いを出した。すぐに誰か来るそうだ」
「ありがとう。よくやってくれたのう。すまぬが、一人にしてくれ」
ミツはこくりとうなずくと、教会の奥へと姿を消した。
一人になった利休は教会の内部を見渡した。漆喰の壁、明かり取りの天窓、重厚な宗教画。静謐だが、祈りの籠った空間。
利休はここにも美を見出していた。草深い田舎の草庵ふうの二畳の茶室にも、全て黄金ずくめの茶室にも、異国風の教会のしつらえにも、それぞれの美がある。
正面には大きな十字架。イエスは磔にされたまま、首を垂れている。天窓からの光りが筋となって降り注ぎ、イエスを生あるものであるかのように、浮かび上がらせていた。
『これを工夫して茶室に活かせないだろうか』
侘びた薄暗い茶室も趣深いが、すがすがと光りの差し込む茶室も良いではないか。利休の頭に次々と案が浮かぶ。
その光りの中、透明なギヤマンの切子の茶碗で茶を点てる。ギヤマン茶碗は、命あるもののように、輝くだろう。
そうだ、明かり取りの窓に日本の雪景色をステンドグラスにしてはめてみようか。秀吉様はどんなにか喜ばれることか。
そこでふと、利休の心に重い影が射した。
『そうだった。俺は今、故知れぬ敵意に囲まれていたのだった』
古渓老師の顔が浮かぶ。老師もまた、秀吉の勘気を被り九州に流されていたのを、周りの取りなしでやっと京に戻ってきたところだった。表立っては動けない身だったのに、利休の窮地をいち早く知らせてくれた。
亡き信長公の葬儀を取り仕切るほどの方でも、秀吉のご機嫌次第で木の葉のように吹き散らされる。悔しいが、私の命運もあやつの
目配せ一つで、断たれてしまうかもしれない。
いつしか陽は落ち、ステンドグラスはその色を失なった。セミナリオの内部にひたひたと闇と冷気が忍び込んできた。
利休は重い溜め息をつき、立ち上がった。そろそろ店から迎えの者がくる時分だ。帰らねばなるまい。
教会の戸を開けて誰かが入ってきた。
「利休殿」
利休門下の高弟、蒲生氏郷だった。
「ああ。氏郷どのか」
利休の声が急に寛いだものになった。氏郷は利休の弟子のうちでも筆頭と言われている。
幼い頃、織田家の人質として安土に送られたが、文武両道に秀で信長公から娘の冬姫の婿にと望まれたほどの、俊英だった。
氏郷は利休が織田家の茶頭に任ぜられてすぐに、弟子入りした。生真面目な性格で、一度教えたことは決して忘れない。点前の手順、道具の扱いは完璧に覚えている。利休門下の弟子を利休七哲と呼ばれるが、まず筆頭に名前をあげられるのは、氏郷だった。
「奥州の一揆の件で、大坂に出向いておりました。なんとか事は、落着いたしまして、お師匠様にお目にかかりたく、堺まで足を伸ばして参ったのです。路上で倒れられたと聞き、用心のためお迎えにあがりましたが、お加減はいかがですか」
「ああ。ちといろいろありましてな」
「いろいろですか……」
氏郷の声が複雑な声音になる。彼にも何やら思い当たることが、あるのかも知れない。
「とにかく店に帰りましょう。少し冷えてきました」
二人は並んで夜道を帰り始めた。もちろん、無言である。無言ではあるが、お互い心の中では会話し合っている。
(お師匠様、お心を強く持ってください。時間がたつにつれて、状況は好転するでしょうから)
(心配をかけてすまない。だが、私はもう七十だ。そろそろこの生臭い世界から引退して、どこかの山奥で庵を開いてひっそりと暮らしたいと思うことがあるのだ)
(何をおっしゃいます。私はまだまだあなた様から学びたいことがたくさんあります。奥伝の台子の手前も、教えてくだされ)
(そうでしたなあ)
氏郷の点前は、武将らしく豪快ではあるがどこかにこの世を諦観して眺めているような無常観が漂う。利休の説く侘びの概念とはまた違って、戦場でおびただしい無惨な死をみてきた者の、透徹した境地とでもいえるだろうか。
氏郷が、利休と秀吉の微妙な関係を心配しているのは、よくわかっている。二人の間にある微妙な心理の綾を、この鋭利な弟子は感じ取っているのだ。天下人秀吉と、日本一の茶頭と言われる利休の、互いに認め合いながらも相手を心の中では見下している、その心の裡を。
「たかが、茶人ではないか」
「たかが成り上がりの田舎者ではないか」
二人の心理戦を、氏郷も察しているのだろう。あえては何も言わないが、利休の心の裡を気遣って、駈けつけてきてくれる。氏郷の心遣いは、今の利休にはことさら暖かく感じられる。利休と氏郷は黙したまま歩き続けた。
途中から背後の空気が変わった。何者かがつけてくる気配がする。それは以前、聚楽第近くの不審庵で、不意に訪れた秀吉に稽古をつけ送り出した後に、不審庵の周囲に満ちていたものに似ていた。その気配は二人が店に入るまで続いた。
店に入ると、心配した店の者が取り囲んだ。
「大事ない、大事ない。さて氏郷様、茶でも一服いかがかな」
利休がわざと明るい声を出す。店の者たちは安心したのか、、散って行った。
「我々の後ろにいたのは」
「多分、あの男の」
二人の脳裏に石田三成ののっぺりとした顔が浮かぶ。薄い一重まぶたの下の鋭い眼は、いつも何かを探るようにこちらを見ている。しかし、彼の視線とこちらの視線が合うことは、決してない。
二畳対面の最も侘びた茶室に二人は膝を突き合わせて座った。傍目から見ると、年の離れた親子のようにも見える。二人とも背が高く、肩幅が広い。後ろ姿から感じられる、どことなくこの世を諦観した雰囲気には、共通のものがある。
「時々、眠れなくなるのです。先のことが案じられて」
「ご心配には及びません。利休殿には徳川様始め、細川、毛利、伊達などあまたの有力な弟子がいるではありませんか。きっと役に立ってくれます」
「ううむ、しかし」
「わたしの領国会津は、ちと遠いのですが、いざとなったら必ず駆けつけます」
利休はまた、無言になる。事態はそこまで切迫しているのだろうか。秀吉が自分を捕らえ処罰するとの噂が。広がっているのだろうか。自分にはそこまでの危機感はないのに。
「ご親族は、私が命に代えても守りますゆえ」
氏郷の眼が光る。この男は実直な男だ。きっと、約束を守ってくれる。しかしながら、事態はそんなに切迫しているのか。利休にはその実感はない。
「実は、私にも思い悩むことがあります」
氏郷が、吐息を吐き出すように話し始めた。
「氏郷さまにですか。はて、なんでしょう」
氏郷は、言いあぐねている。口に出そうか、出すまいか。この屋敷内ならば、聞くものもいないだろうが、しかしわからない。氏郷はそれきり口をつぐんだ。
利休は、ていねいに濃茶を練る。唐渡りの青磁茶碗に、抹茶の緑が映える。
「美しい」
「誠に」
どろりとした濃茶を二人で回し飲む。苦みの中にほのかに甘みが立ち上ってくる。茶を回し飲むことで、亭主と客の一体感が増してくる。
「一期一会」
という禅語が二人の心をかすめた。この二人で茶を飲むという機会は二度と再びはないかもしれない。二人は長い間、茶釜の釜鳴りの音を、放心したように聞き続けていた。
明け方の海鳴りの音を、利休は夢うつつに聞いた。戦場の兵士たちの雄叫びのようでもあり闇をつんざく雷のようでもあり。いつしか群衆のどよめきのように聞こえてきた。
セミナリオの礼拝堂の正面にかかげられた十字架に、白衣の自分が架けられている。手首、足首を釘で打たれ、鮮血が滴り落ちている。
周りにはいつのまにか、妻のりきと子供たち、親類縁者、店の者たち。数十人はいるだろうか、みな十字架に打ち付けられ苦しみの声をあげている。
群衆たちは口々に
「てんかさまをないがしろにした罪で、はり付けにされたそうだ。おそろしや、おそろしや」
「唐入りなど、見果てぬ夢じゃと触れ回ったそうな」
と、どよめいている。役人たちが一斉に槍を持ち身構えた。その後ろにはあの男が、無表情に立っている。
あの男の右腕が上がった。
「突け」
そこで、利休は目が覚めた。
「いかんいかん。このままでは大変なことになる。てんかさまにおめにかかろう。捨て身でお詫びをし、お許しを乞おう」
利休は怯えた兎のように、堺の店を飛び出した。
(6)
秀吉は聚楽第で、遅くに生まれた鶴松を抱いていた。長く子ができなかった秀吉にとって、諦めかけていた頃になってやっと出来た血を分けた我が子なのだ。可愛くてたまらないらしい。
もっとも、まちでは様々な噂が流れている。曰く、
「ほんとうは、誰の子種じゃろうか」
「あまたの側室にも出来なかった子が、なぜ淀の方だけに」
「おととさまに、似てはおられぬとか」
「てんか様は、何もかもご承知のうえらしい」
まちの辻辻で、密かに噂は広まり、波紋のように拡がっていく。
「てんかさまも、おひとのいいこと」
「三成殿かのう、真田殿かのう、氏郷公との噂もあるが」
「幼いながらも眉目秀麗、涼やかなまなこは、氏郷さまに生き写しじゃそうな」
「しかし、それはあるまい。あのお方に限っては」
信長の娘婿であった氏郷は、本能寺の変の後も、明智光秀の誘いになびくことなく、居城の日野城に信長の一族を手厚く保護した。信義に厚い氏郷にかぎって、信長の姪である淀の方に、そのような振る舞いに及ぶ訳はないと、大方の評判だ。
「では、誰が」
「さてさて、それは」
どこかで誰かが聞いていたのか、口さがないおしゃべりをした者は皆、夜の闇に紛れて惨殺された。
聚楽第に戻った利休の耳にも、洛中の噂が聞こえてきている。
「たしかに、似ている」
決して口外はしないが、利休も気づいている。
「あの面立ちはやはり」
利休の背筋に冷たいものが走った。
「利休、帰ってきたか」
久しぶりに聚楽第に出仕した利休は、控えの間にいた。その障子を大きな音をたてて開け、秀吉がどかどかと踏み込んできた。あの男、三成も後ろにいた。
「どうであったかのう。堺は」
「何も変わってはおりませぬ。ますます賑わっておりました」
「倒れられたと聞いたが」
後ろに控える三成の目がそれとなくこちらを窺う。やはり、見張られていたのか。
「はい。もう齢七十にもなりますと」
「そうか、十分に養生せよ」
しばらく、秀吉は利休の顔を眺める。その目にはどこか残忍な色が浮かんでいる。
「七十か。そろそろ利休殿も引退の潮時かもしれぬのう。のう、三成」
三成は何も言わない。しかし、閉じた唇の端が『してやったり』と、言わんばかりだ。
利休の心が激しく揺れ動く。まだまだ、仕事ができますと、秀吉の慈悲にすがるべきか、それともここは潔く引くべきか。このところの秀吉とのいきさつを考えると、このあたりで引く方が、穏やかに事が収まるかもしれない。
「そうかもしれませんな」
利休の口から、溜め息と同時に言葉が漏れた。
『そうだ、この辺で引こう。このまま秀吉の感情が悪化して行くと我が一族がどんな目に会わされるか、分からない』
「そうか、引くか」
秀吉は、思案顔で障子の外の庭を眺める。ようやく着き始めた苔の上に朝の露がきらきらと光っている。利休も庭を眺める。この庭は利休が差配して造り上げた庭だ。利休は数多くの茶庭を設計し造園したが、この聚楽第の庭が一番気に入っている。利休は今の窮地も忘れ、放心したように庭を眺めていた。
「次の茶頭は、誰がよいかのう」
「小堀、織部、我が息子の小庵。幾人もおりまする。織田有楽斎どのも、適任かと」
秀吉の答えはない。突然、秀吉がわめき出した。
「わしの指図も聞かず、何を勝手にやめるだの言い出すのだ。この馬鹿者が」
秀吉の口のはしからよだれが落ちている。もはやそれにも気付かぬほど、怒りは彼を狂人にした。秀吉が言い出したことではないか。利休は愕然とする。このごろの秀吉は昔の怜悧だった彼とは別人のように、感情の起伏が激しい。
「勝手なことを言い出しおって。しばらく屋敷に控えておれ。いいか、わしがいいというまで出てくるな」
足音荒く、秀吉は出て行った。残された利休はじっとそのまま動かない。表情も変えない。瞑目し、ゆっくりと呼吸を繰り返していた。そのうち、何故か笑いがこみ上げてきた。
『ばかばかしい、なんであの男の機嫌を取らねばならぬのだ。あの狂人の。下らぬ。下らぬ。わしはもう嫌だ。これ以上つきあってはいられない。思えば多くの時間をあの男と過ごしてきたが、あの男の茶はほんのうわべだけ。成り上がりの土百姓の本性のままだ。ああ、ばかばかしい。つきあってきた私も馬鹿だ。なんと、虚しい時を過ごしてきたことか』
利休は晴れやかに笑った。腹の底から笑った。笑い過ぎて涙が出てきた。その涙は、憐憫のなみだでもあった。なんとかわいそうな自分であったことかと。
廊下の向こうで、襖の陰で、こちらを見張る者の気配を感じてはいたが、利休は笑いを止めようとはしなかった。
(7)
ひとたび、馬鹿馬鹿しいと思い始めたら身回り全てのことが虚しいと思ってしまう。日々の典礼、作法、朋輩との付き合い、茶の湯の道具立て、秀吉の機嫌をうかがうこと、三成の目を恐れること。
己の目指すところの茶の湯に向けての創意工夫にも、気が入らない。道具、季節感、花、庭、茶料理の献立。そんなものは、どうでもよいではないか。たかが、茶碗一杯の茶を飲むだけのこと。しつらえや、道具組などどうでもよい。その辺の器に抹茶を点てて飲めばよいだけだ。唐物だの、朝鮮青磁だの茶碗の由来にこだわってみても、目をつむって飲んだら味の変わりなど、ない。
気の張る付き合いも、どうでもよくなってきた。どこそこのお茶人が名物のお道具を手に入れたとか、あそこのお茶事ではどんな料理がでたとか。家康殿がどこの茶会にまねかれたとか。
そんな事も、もう考えたくはない。自分は何のために茶道に邁進してきたのか。旧来の貴人たちが行ってきた雅な書院の茶に、利休は草庵の茶を美とするという、茶道の革命を起こした。茶の湯を武士や富裕な商人たちのものから、庶民も楽しめるものにした。道具も渡来品に拘らず、そこいらの市で売っているもので十分と、説いた。
今の利休の考えはもっと進んで、唐渡りでも、市中のものでもどちらでもよく、そのとき手に触れたもので、良いのではないかと思い始めている。
このまま、どこかの山奥に庵を結んで遁世し、釜一つ、茶碗一つで侘び茶をきわめたい。
春には花を、夏には青葉を、秋には紅葉を、冬には枯れ木を相手に、茶を点てる。その庵は方丈で良い。炉と、何冊かの謡本と、わずかな茶道具があれば、それで良い。
かの西行法師や、鴨長明が出家遁世した跡を私も追ってみたいものだ。
ただ、気がかりは家族のことである。りくをはじめ、連れ子の小庵、実施の道安と娘たち。嫁いだ彼女らに累が及ばないかと、そこだけは利休は心配している。ひとたび罪に落とされたら、一家は皆殺しになってしまう例を数多く利休は見聞きしてきた。
自分はもう齢七十になり、十分に生きたと思う。しかし、家族のものを道連れにするのは忍びない。いっそのこと、秀吉からの何らかの沙汰がある前に、自刃してしまおうか。そうすれば、家族に手が及ぶこともないかも知れない。
利休はそう肚を決めた。決めると、妙に清々しい気分になった。豪商や武人たちが前からほしがっていた茶道具を、売り払うことにした。その代金は密かに堺の店に隠し置いた。嫁いだ娘、実の息子、妻りくの連れ子にもそれとなく別れを告げた。
もうじき庭の椿が散りそうな、寒さが少し和らいだ日の朝、秀吉から書状が届いた。内容は、詫びを入れろと。諸侯が揃った場で、自分に低頭しろと。そうであれば、許そうとのことだった。皆が危惧していた切腹の沙汰でではなかった。
利休は書状を読み終えると、誰憚ることなく大笑いをした。
「これがこの世での笑い納めじゃ。ああ、なんと心が晴れることか」
りくが驚いて様子を見に来た。
「どうされました、旦那様」
「やっと、胸のつかえが下りたのじゃ。言ってやろう。秀吉は大うつけじゃと。今に豊臣の世は滅びるじゃろうと。言いたいことを言うとは、なんと心が冴え冴えとすることか。宗二の心持ちがよくわかった」
利休は決然とその書状を破り捨て、使者を追い返した。数日後、切腹を申付けるとの書状が聚楽第より届いた。
利休はりくの心尽くしの朝餉をゆっくりと楽しんだ。
「旨いのう」
「美味しゅうございますか」
「ああ。こんな折でも旨いものは旨いぞ」
「まあ」
りくが、吹き出した。利休もつられて笑った。二人は笑顔ではあったが、頬に一筋涙が流れた。
利休は、庭の紅椿よりもっと赫い血を真っ白な死装束に染めて、この世を去った。