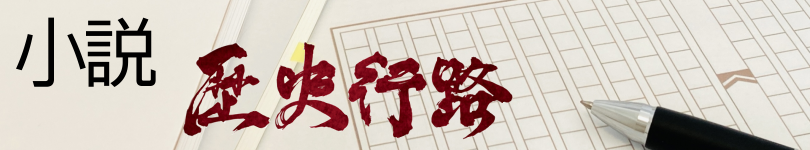山上 安見子
「見て見て、お父さま。山も,湖も、空も、みんな笑っているわよ」
わたしはいつものように父の膝に抱かれ、遠くに霞む琵琶の湖を眺めていた。まだ春浅く、城の周りの山々は淡い緑にかすかに煙っている。よく晴れた水色の空と湖面がたがいに笑いかけている。
甲冑姿の父は、ため息交じりに言った。
「ああ。ずっとこのままお前と一緒に、この景色を見ていたいよ」
わたしは頬を膨らませる。
「いくさなんか、なければいいのに」
もう、ずっと城の外に出ていないのだ。本当は外で活発に遊びまわるのが大好きなのに。
私の名はちゃちゃ、五歳になったばかり。父の浅井長政と、母であるお市御寮人の兄、織田信長との間にいくさが起こっている。当初は浅井勢が優位であったのだが、三年にわたる戦闘の果てに、いつしか浅井勢は劣勢を余儀なくされ、織田の軍勢はこの城のすぐ近くにまで攻め寄せてきていた。
「この城もよく保って、あと半月だな」
父の独り言に、ちゃちゃは耳をふさぐ。
「そうなったら、私たちは、どうなるの」
「そうだなあ」
父の答えは、ない。
父長政と母お市は、二人並んで座ると、一対の雛人形と見まごうほどに美しい夫婦だ。武将には珍しくうりざね顔で切れ長の目をした父と、すっきりと通った鼻筋に意志の強そうな瞳の母は、美男美女のお似合いの夫婦だと、よく侍女たちが噂していた。
母の髪は、一本一本が命を持っているのではないかと思えるほど、つやつやと黒かった。その髪にはいつも織田家の家紋の揚羽蝶が刻まれた鼈甲の櫛が、挿されている。
「この櫛は、祝言のため尾張を出発するときに、兄信長が贈ってくれたもの。この櫛を挿していると、不思議と災厄を免れるという言い伝えが織田家にはあるのだと言ってね。魔王と恐れられている兄にも、存外優しいところがあるのよ」
私はその櫛が欲しかった。自分の髪に挿してみたかった。でも母は
「まだ、ちゃちゃには早いわ」
と、取り合ってはくれなかったけれど。
もう一つ、いやもう一人と言えば良いのか、信長叔父は母に忍びの者をつけてくれていた。
ましらの権。背は五尺に足りない。異様に長い腕は地面に届きそうだ。ひたいはせり出し、その奥のくぼんだ目の表情は、ほとんど読み取れない。
やや膝をかがめて音もなく歩き、走り、跳ぶ。足軽の身なりになったり、修験者姿や、百姓、僧侶、猿楽師、薬売り、見るたびにいでたちが違う。どれが本当の姿かわからない。
だけど少し猫背気味で、俯きかげんに歩くその姿は、どんな服装でもすぐに彼だと見分けられる。
権は、いつもは姿を見せない。だけど、なんとなくその気配は感じられる。私と妹たちが春の野で若草を摘むとき、琵琶湖のほとりで夏に遊ぶとき、秋の紅葉狩り、冬の雪遊び、権は目立たないよう、木立や物陰に隠れて見守ってくれている。私たち姉妹は、安心して遊ぶことができた。
どこで生まれたのか、親兄弟はいるのか、何歳なのか、全てわからないけれど、彼はいつも私たちのそばにいた。
それから、安土から嫁入り道具としてたずさえてきた雛人形もあった。母はいくさのただ中であっても、草木が芽吹く弥生になると、かかさず侍女たちに命じて、雛人形を飾らせた。せめてひとときでも、娘たちに心穏やかに過ごさせたいとの、母としての願いだろうか。
「本当に、お父さまとお母さまによく似ているわ」
晴れ着を着せてもらい、薄化粧を施されたちゃちゃは、薄暗いろうそくの灯に照らされたお内裏様とお雛様を見てつぶやく。
「ちゃちゃさまも、きっとお母さまのようにお綺麗にお育ちになられますよ」
侍女たちのことばに、ちゃちゃは一瞬の夢を見る。お内裏様のように美しい花婿の隣に座る自分を。そして、夢はすぐにやぶれる。
そう、ここはいくさ場。誰もが明日の命なんてわからない。
父浅井長政は、武芸の腕はもちろん、立華・連歌・香道・能など、名門の武将としての当然の教養として嗜んでいる。古典や漢籍にも詳しい。
歌人、藤原定家の書風を手本とする定家流の書の達人でもある。平時には、いつも書見台に本を載せ、時の経つのも忘れて読みふけっていた。
父の手近かには、常に「古事記」や「日本書紀」が置いてあり、時間が許せば、いにしえの物語、ちゃちゃにもわかるように語り聞かせてくださる。
ついこの前までは、都から冷泉流の和歌の師や、観世流の能の太夫もこの小谷城に滞在していた。もっとも、信長軍が押し寄せてくるとの噂が立つと、すぐに城下からその姿は消えてしまったが。
城内には能舞台があり、母と共に、ちゃちゃも幼い妹の初や江も、見所から父が舞う能を見物した。
長政は、平家の公達がシテとなる修羅能を、好まなかった。源氏との戦に敗れて命を落とし、修羅道に落ちた苦しみを語る武将たちに、明日をもしれぬ我が身を重ねたのだろうか。
得意としたのは、「竹生島」。琵琶湖に浮かぶ、竹生島神社の守り神「弁財天」と、島の周りを、とぐろを巻いて守っているという龍神が、仏の徳を称えて舞い遊ぶ、めでたい能である。
しかしながら、松明に照らされて舞う直面の父は、どことなく死を覚悟していると、幼いながらもちゃちゃは感じていた。
「薄鈍色に光を映す今日の琵琶の湖は、また一段と美しいな。そうだ、ちゃちゃ。古くからこの地に伝わる恋物語を語ってやろうか」
恋物語。その言葉はちゃちゃの胸をときめかせる。
「うん。うん。聞かせて、お父さま」
「古事記という、古い書物に書かれている物語だ。この湖にまつわる、悲しい恋の物語だよ」
父は、銀色にたゆとう湖にちらりと目をやると、ゆっくりと話し始めた。
「はるか千年も昔に、この湖国の岸辺には女鳥(めどり)姫という、若く美しい姫が住んでいた」
穏やかに、父の話は続く。
「大和の国を治めていた大王の大鷦鷯(おおささぎ)はその評判を聞き、女鳥を妻の一人に娶ろうと、異母弟の隼別(はやぶさわけ)皇子を使者として遣わすことにした」
ちゃちゃの目に、ゆったりとした裳を翻し、肩から五色の長い領巾(ひれ)をたなびかせた、黒目勝ちの美少女が浮かんだ。少女は高い楼閣から、さざ波を受けて光る湖を明け暮れ眺めていた。誰かの訪れを待っているかのように。その面差しは、どこか母のお市御寮人に、似ていた。
「草木が萌え始める早春の朝、白馬にまたがり足結いの鈴を響かせながら、都から凛々しい若者がやってきた。隼別王子だった。王子と楼閣の頂上にいる女鳥との、目が合った」
ちゃちゃは目を閉じて、その光景を思い浮かべる。互いに見つめ合う古代の皇子と姫は、どんなに美しかっただろうか。
「あなたが女鳥姫か」
「ええ、あなたの名は」
「我が名は隼別。兄の使いでやってきた」
呼びかわす二人の声は、湖面を涼やかに渡る春の微風のようだったろう。
「そのお姫さまは、いくつぐらいだったの」
「そうだな。十二、三歳というところかな」
ちゃちゃよりは、ずいぶんと年かさだ。でもちゃちゃは、すっかりと女鳥姫になった気分だった。
「それから、どうなったの」
「隼別の皇子は、女鳥姫を一目見るなり、恋に落ちたんだ」
「あら。お兄さまの大王の、思われ人だったのに」
「ああ、そうだ。困ったことに、女鳥姫も隼別の皇子が好きになってしまい、大鷦鷯大王のもとには行かないと言い出した。何しろ大王は髪も眉もヒゲも真っ白な、かなりのおじいさんだったからね」
「まあ大変。二人はそれからどうしたの」
「隼別の皇子は、姫をさらって湖国から逃げ出し、吉野の山深くに隠れたんだ」
「大鷦鷯の大王は、怒ったでしょうね」
「ああ。すぐに大勢の兵士を差し向けた。しかし投降するならば、二人を助けようとも伝えた」
「まあ、二人はどうしたの」
「皇子は、女鳥姫だけでも助けようとした。自分はいずれは大王に反乱した罪で、屠られることは分かっていたからね。大王の残忍さは、国中に知れ渡っていた」
ちゃちゃは、叔父信長の評判を思い出した。比叡山の僧侶を何千人も、焼き殺したとか、一向宗の門徒を撫で斬りにして皆殺しにしたとか。陰では日本一の大魔王と、呼ばれているらしい。
ちゃちゃは、身震いした。もしもいくさに敗れたら、私たちも、どうなるかわからない。たとえ、血が繋がっていても、叔父上さまの気分次第で磔になったり、首をはねられたり。
父も、話をやめてじっと何かを考え込んでいる。
ちゃちゃはわざと明るい声で、たずねた。
「それで女鳥は、どうしたの」
「どうしたと思うかい」
ちゃちゃは、遠くに鈍く光る湖を眺める。春霞が一面にかかり、さざなみが陽の光を反射して、少し眩しい。ちゃちゃは目を細めながら、父に答えた。
「そうね、私だったら、好きな人と一緒に死にたいと思うわ。生き延びて嫌なおじいさんの妻にさせられるなんて、まっぴらよ」
「そのとおり。二人は死を選んだ。桜の花が満開の季節だというのに、季節外れの雪が舞う寒い夜のことだ。
吉野の山の周りを大王の兵士が何重にも取り囲み、激しい戦闘のすえ、家来はほとんど討ち果たされてしまった。
敵の兵士たちが、じわじわと包囲の話を縮める。二人は巨大な桜の老樹の下に追い詰められた。もうどこにも逃げられない。その二人の上に、強い風にあおられた雪と桜の花びらが容赦なく降り積もる。
敵の兵士たちの持つ松明が二人を照らしだす。もう逃げられないと観念した二人は、固く抱き合った。
『姫、もはやこれまでだ。あの世で会おう』
『ええ、西方にあるという常世の国で、いつまでも一緒に暮らしましょうね』
次の瞬間、女鳥が短い悲鳴をあげて地面に倒れた。隼別が女鳥の胸に深々と刀を突き刺したのだ。女鳥は愛する隼別の腕の中で息絶えた」
「まあ……」
「皇子も、すぐに喉を掻き切り、女鳥を抱きしめたまま絶命した」
ちゃちゃは、なおも湖を見つめ続けた。湖面の白く光るきらめきの中に、若く美しい二人が固く抱き合ったまま息絶えた光景が浮かぶ。
二人のなきがらの上には粉雪と桜の花びらが降り積もり、二人の流す血で紅に染まったことだろう。それは残酷ではあるが、美しくもある光景だった。
「翌朝、この湖の上を二羽の白鳥が、海に向かって飛んで行ったそうだ。隼別と女鳥の魂の化身だろうと。二羽は海のはるかかなたの、常世の国に向けて飛び立ったのだと、この地では長く言い伝えられている。二人は、きっとあの世で幸せに暮らしているのだろうね」
ちゃちゃには、降りしきる桜吹雪の下で血みどろになって息絶えた二人が、父と母の姿に思えて仕方なかった。そんな不吉な。でも、考えられなくはない。ちゃちゃは、思い切ってたずねてみた。
「もしものことがあれば、お父さまもお母さまと一緒に、死にたいと思っていらっしゃるの」
「ちゃちゃは、難しいことを聞くね」
父長政も、春霞の湖を見つめる。湖を囲む山々は、芽吹き始めた若葉で薄緑に萌えている。早咲きの山桜だろうか、ところどころが薄紅色に浮かんで見える。いくさの最中であっても、今年も春が訪れていた。
しかしよく目をこらすと、湖の岸辺には織田方の旗指物がなん十本もたなびき、湖面には、軍船がひしめくほどに浮かんでいる。小谷城は、すでに信長の軍勢に厳重に囲まれているのだ。
「できることならば、お市とともにあの世へ行きたい。しかし、幼いお前たちを道連れにするのは忍びないしなあ」
父の顔は、泣き笑いの表情になった。
「殿、予想より早く敵の軍勢が、大手門より攻め寄せてまいりました。すぐに御下知を」
階下から、殺気立った声が聞こえてきた。瞬時に表情を引き締め、ちゃちゃの頭を愛おしげにゆっくりと撫でた。妹たちを頼むよと、言いながら。甲冑姿の父は階下へ駆けおりて行った。ちゃちゃが、父とゆっくりと語り合ったのは、その時が最後だった。
そこからちゃちゃの記憶は途切れ途切れになる。破城槌の猛攻でついに破られた大門から、信長方の兵士が、荒れ狂う波しぶきのように押し寄せてくる。城の方々で火の手が上がった。
元結いが切れて総髪になった父に、母が取りすがっている。一緒に連れて行って、私も死にますと絶叫する母。子どもたちが、いるじゃないか。生きてくれと言い残して、斬り合いの中に飛び込んで行った父。
炎がゆらりと近づいてくる。焦げ臭い煙にむせる。うめき声や悲鳴、鉄砲の音に耳を塞ぎ、恐怖のあまりしゃがみこみ泣き叫ぶ妹たちをちゃちゃは、両手にかばう。本当は怖くてたまらないのだけれど、父の頼みを果たさなければ。
織田方の軍勢が、ちゃちゃたちの潜む部屋に、なだれ込んできた。ましらの権が必死に私たちをかばう。でも多勢に無勢。権は斬り伏せられ炎の中にくずれ落ちた。炎が迫る。もう私たちを守ってくれる兵もいない。ここまでだわ。死を覚悟して懐剣を首に当てた私の耳に、低く響く声が聞こえた。
「姫さま、死んではなりません。生きて、生きて、生き抜くのです」
背後から炎に照らされたその男の顔は、影になってよく見えなかったが、かろうじて見えた目元は深い憐れみに満ちていた。
懐剣は払い落され、そのまま気を失った私は、気づくと誰かの背におぶわれ揺られていた。
「気がつかれましたか」
爽やかな声だった。
「お母さまや、妹たちは」
「ご無事です。後からついてこられていますよ」
振り返った私の目に、巨大な炎が揺らいでいた。小谷城が燃えていた。泣き出した私を、その方の腕は優しく支えてくれていた。
私は、泣き続けた。涙を止めようとしても次から次へと溢れ出る。お父さまや家臣たち、そして城が燃えてしまう。大切な思い出も、跡形もなく消えてしまう。
それは、初めての喪失感だった。この世にあるものは、いつか滅びてしまうのだ。幼いながらも、私の胸にはなんとも言えない空洞がその時以来、宿ってしまった。その空虚さはわたしの生涯を通じて、決して消えることはなかった。
「姫さま。お悲しみはよく分かります。でも、泣いてばかりいると、お体に触りますよ。わたしが一つおとぎ話をして差し上げましょう。
姫さまもご存じの琵琶湖にかかる瀬田の唐橋のお話です」
わたしは無言でうなずいた。その方の広い背中の温もりが心地よく、涙は次第に止まった。
「私の遠い先祖は、藤原秀郷、別名俵藤太と言って、武芸に優れた武者でした。今から六百年も昔のことです。坂東で起こった平将門の反乱を鎮め、都に戻っていた藤太はある日琵琶湖にかかる瀬田の唐橋を通りかかりました」
私の目に、古えの凛々しい武者の姿が思い浮かんだ。鎧甲冑に身を包み、腰には大刀を佩く美丈夫だ。肩をいからせ、のっしのっしと大股で橋を渡っている。
「すると、橋の真ん中に大蛇が横たわっている。通行人は気味わるがって引き返していた。しかし、藤太は平然と進み、大蛇に近づいた……」
私はおぶわれたまま寝入ってしまったようだった。私を支えるがっしりとした腕、温かな背中。遥かなむかし、私はこの背中と腕を知っていた気がする。そんなことをうっすら思いながら。
気付いた時には、織田方の本陣に着いていた。
「姫様、またいずれ」
登り始めた朝日を背にしたその方の顔はよく見えなかったが、私をしばし見つめ、名残惜しげに去って行かれた。
「藤太のお話の続きを聞かせてくださいね」
私はその方の後ろ姿に、精一杯の声で叫んだ。
そして信長公の前に、引き出された私たち母子。妹たちは、私の後ろに隠れるようにして、おそるおそる信長叔父を見ていた。
「お市、役目ご苦労。しばらく休め」
役目ってなんのことだろう。母は強い眼で見返した。
「役目だなんて、そんなつもりはありません」
「そうかな」
信長叔父は傲然と母を見返す。先に諦めたように目を伏せたのは、母だった。
「これからお世話になります。娘たち共々、よろしくお願いします」
母のため息交じりの声に、叔父の表情が少し緩む。しかし、母と私たちを見るその目は、何か高価な衣装を値踏みしているような、そんな目だった。どこへ売りつければ一番高値で売れるか。そんな計算を巡らせているような。
私は母の手をしっかりと握り、叔父上を睨み返した。叔父上の周りには、何かこの世ならぬ禍々しいものが漂っている。
少しつり目の眼差しは、青みがかっていて澄み切った清水のようではあったけれど、その底には何か得体の知れない魔物が潜んでいそうだ。
「ああ、怖い。お父さまの元へ帰りたい」
お父さまの優しい眼差しを思い出し、私はべそを書いた。
不意に親しげな声が聞こえてきた。
「姫さまがた、お待ちしておりましたよ。あのままどこかへ行ってしまわれるのではないか、心配しておりました」
派手な陣羽織を着た武将が、嬉しそうに歯を見せて笑っている。
「お市さま、今も相変わらずお美しい」
「お前が浅井に嫁いでのち、この羽柴秀吉は随分と出世した。もはや昔の猿ではない。立派な城を持つひとかどの武将だ」
信長叔父の言葉に、相好をくずし笑いをうかべる男。でも、私は築いた。目だけは笑っていない。彼もまた、目の底に不気味な魔物が潜んでいると。母はさも嫌そうに、男から顔をそむけた。
その男秀吉に、私はなぜだか哀れみを感じた。もしかしたら、そう遠くない将来に、私はこの男を食い尽くしてしまうのではなかろうか。
私はその当時、わずか五歳の幼女だったけれど、何か得体の知れない暗い渦を、秀吉との間に感じたのだ。この男と関わってはいけない。互いが不幸になってしまう。そんな予感めいたものが、しきりに胸をよぎった。
でもその頃の私にできることは、その男に向かって思いっきりしかめっ面をするのが、精一杯だった。私の顔がよほど面白かったのか、秀吉は大声で笑った。
「なんと面白い姫でしょうか。将来の婿殿も、きっと楽しく思われるでしょうな。ああ、愉快、愉快」
不幸にも私の予感は、数十年後に現実のものとなってしまう。私はこの男が一生をかけて築いたものを、全て破壊してしまうことになるのだ。
小谷の城が落ち、私たちが信長の元に身を寄せてからも、日本の至る所で戦さは続いていた。果てしなく続く戦闘と、殺戮と、破壊と、混乱が続いていた。
叔父信長についての、耳を覆いたくなるような血なまぐさい噂が絶えず聞こえてくる。歯向かう農民を虐殺した、罪のない女子どもまで無慈悲に撫で斬りにした。敵軍を一人残らず殲滅した。
その頃、私は不思議に思っていたことがある。私たち母娘を保護してくれる母の異母兄弟たちは、皆優しく穏やかな方ばかりなのに、なぜ長兄の信長殿だけ、あのように残忍で無慈悲なのだろうか。
「今に天罰が当たるに違いない」
そんなひそひそ声が、どこからか聞こえてくる。家屋敷、田畑、家族、全てを失い彷徨う飢えた浮浪者が、その頃の日本にはそこかしこに溢れていた。
ありがたいことに私たちは安全な住まいが与えられていた。飢えに苦しむこともなく、命の危険もない場所に。
母お市の同腹の兄、織田有楽斎に保護され屋敷に迎えられて、いつしか五年になる。母と有楽斎叔父は仲が良く、この叔父は私たちを不憫に思ってか、何くれとなく細やかな心遣いをしてくれる。
有楽斎は、風雅を好む風流人でもあった。源氏物語や古今集を常に携え、衣服にゆかしい香を薫きしめる。そんな人だった。戦場に赴く時には、兜にも香を染み込ませ出陣するとも、言われていた。
尾張知多の叔父の居城には、この時代にしては珍しく、入母屋造りの寝殿作りの屋敷を設えていた。戦のないときは、香道の宗匠を招いて香合わせの会を催し、私と母を招いてくれた。
信長が簒奪したという、奈良東大寺正倉院に伝わる香木の蘭奢待の一片を、兄信長から分けてもらっている。会では時折、その伽羅が試み香として出香されることがあった。四畳半の室内に伽羅の香りがみちる。
天上に気高く咲く花の香りとでも言えば良いのだろうか、甘く上品な香りはいくさに疲れ、ささくれた私たちの心を癒してくれた。
松虫の鳴く頃、一人の武将が聞香の会の客としてこの城にやってきた。戦場から駆けつけたと言うのに、月代もヒゲも綺麗に剃ってある。涼やかな目の美しい男、その名は蒲生氏郷。
客待合で挨拶を交わす。美しい目の男は、私の顔を気遣わしげに見る。
「お元気そうで、何よりです。小谷の落城の折はまだお小さくて、なんとおいたわしいことかと心を痛めておりました」
「あなたがあの時、私を背中におぶってくださった方なのですか」
「甲冑を通しても、あなたの悲しみが伝わってきましたよ。よくご無事に成長されました」
亡き父浅井長政にどこか似ている。細面の顔、通った鼻筋、どこか悲しげな目元。私の胸は少し高鳴る。
四畳半の茶室を使って、組香のお点前が始まった。今日は源氏香。源氏物語の五十四巻の名を使い、五種の香を当てる。氏郷さまが正客に座られた。試み香に蘭奢待の伽羅、二香に白檀、三香に沈香を使う。
氏郷さまはみな当てられ、今日の出席者の成績を記した会記は、氏郷さまのものとなった。
部屋を変え、皆で菓子と薄茶をいただく。
「見事でしたな。氏郷さま」
香元を勤めた叔父有楽が、感心したように話しかける。
「血なまぐさい戦場を駆け巡るうちに、雅な香りなど嗅ぎ分けられなくなっていると、思ったのですが。まぐれでも嬉しいですな」
氏郷さまの口元には苦いものが浮かんでいる。
「戦場から戦場へ。気の休まる時がありません。今日はつかの間、心を遊ばせていただきました」
「よく、おいでくださいました。しかし次にお会いするのは、どちらの戦場でしょうかな」
二人は寂しく笑い合う。私たちもうつむくしかない。武将とはいえ、その命は明日をも知れないのだ。
「私の茶の湯の師匠、千利休宗匠が言われるように、まさに一期に一会ですなあ」
供を連れ、馬で去って行く氏郷さまを、私はいつまでも見送った。
その夜、いつものように母と私たちは一緒に休もうとしていた。ふと思いついて、私は母に尋ねてみた。
「まだお父さまが生きてらした時、隼別皇子と女鳥姫のお話を聞いたの。お母さまは、ご存知ですか」
「ええ。千年も昔から湖国に伝わる若い二人の悲恋物語のことね。嫁いで間もない頃、お父さまが話してくださったわ」
「お父さまは、あの二人のように、お母さまと二人であの世に旅立ちたいと、お思いのようでした」
母が、深くため息をつく。
「私もどんなにか、それを願ったか。あの人のいないこの世に、生き残っても仕方ない。女鳥姫のよう潔く命を絶ってしまいたかった。
でも隼別と女鳥には子どもがいなかったけれど、私にはあなたたちがいた。あなたたちを残して死んではいけないと、お父さまに強く戒められたのよ」
そのことは、ちゃちゃも覚えている。あちこちに炎が上がり、銃弾が飛び交い、怒号と断末魔の叫びが聞こえる。私たちは、城の奥まった部屋に隠れていた。抜き身の刀を持った父が、飛び込んでくる。
「城はもうじき落ちる。子供達を連れて、信長を頼れ。悪いようにはしないはずだ。これでお別れだ。市、私はあなたと過ごせて幸せだった」
顔を背け、足早に去ろうとする父に母が必死に取りすがる。
「待ってください。私も連れていって」
絶叫し、泣きふす母。きな臭い煙、部屋に乱入してきた敵方の兵。そのうちの誰かが私に叫ぶ。
「生きなさい姫よ。死んではなりませぬ」
私たちは担ぎ上げられ、城外に連れ出された。燃え上がり、天に向かって火柱を吹いて、焼け落ちていく小谷城。火柱はやがて龍の姿を取り、やみ夜を自在に跳ね回る。
幾度この場面を夢に見たことだろう。泣きながら目を覚ましたことだろう。
「今でも死にたいと思っているの」
私はおそるおそる尋ねてみた。
「いいえ。今は生きなきゃいけないと思っている。あなたたちを守らなきゃね」
母はきっぱりと答えたけれど、こうも続けた。
「でもいつかはお父さまの元へ行きたいわ」
私はまだ幼く、男女の心の機微はわからないけれども、父と母が遥か昔の隼別皇子と女鳥姫に負けないくらい、深く愛し合っていたのは、わかっていた。
侍女たちの噂話では、兄信長の命でいやいや浅井家に嫁いできた母お市の方であったけれど、共に時を過ごす間に深く愛し合う仲になったと。
嫁ぐ前には、兄の信長から浅井家の内実を密かに知らせるよう、命令を受けていたにも関わらず、不確かな情報しか伝えていなかったとも。
それは、肉親であってもいくさの駒としか扱わない、兄信長への母の精一杯の抵抗であったかもしれない。
私はその深い愛情に憧れた。命をかけて愛し合う、そんな相手が現れないかしら。
その時、二人の武将の顔が浮かんだ。猿に似たあの男、秀吉。あの男の顔を思い浮かべると、なぜか腹立たしさを覚える。
近づかなければいいのだわ。ずっと叔父織田有楽斎の城に住まわせてもらおう。
そして、もう一人。蒲生氏郷さまの顔も浮かんだ。懐かしく慕わしい。ずっと以前どこかで出会ったような、そんな気さえしてしまう。
もしかして、氏郷さまが私の隼別皇子かも。十歳になった私の胸はときめく。膨らみかけた胸の先が少し痛い。十六夜の月が中天にかかり、少し欠け始めた春の月の柔らかな光が、眠れない私にささやく。
「きっとそうよ。そうだと思うわ。あの人があなたの隼別皇子。そしてあなたは女鳥姫の生まれ変わり。あなたの思いが本物なら、今にきっと会えるわよ」
弥生の空の朧な月の光に包まれて、幸せな気持ちで私は眠りについた。なのに、またしてもあの夢を見てしまった。小谷城が炎に包まれ、その炎が龍の形になって天へ昇っていく夢を。
しかし、その夢の続きがあった。天に昇って行った龍は、反転して地表目指して舞い下りてきた。そして、氏郷さまにおぶわれたまま、うとうとしていた私めがけて急降下し、そのまま私と一体になってしまったのだ。私は驚いて目覚めた。
月はとうに落ち、闇は深かった。その闇の底にちろちろと燃える炎が浮かび、すぐに消えた。
遠くで野鳥が鳴いた。その声は何かの警告のように、長く尾を引いて響いた。
時間は無慈悲に流れゆく。叔父信長は本能寺で横死。母は私たちを連れて柴田勝家さまと再婚し、北国の北ノ庄城へ移った。
母はこんなに楽しそうに笑う人だったのか。ちゃちゃは意外だった。実の父浅井長政と一緒に過ごす時はもちろん,和やかな顔で微笑んではいたが、笑い声を立ててはいなかった。
義父柴田勝家も、よく笑っていた。いや、笑うというよりももっと豪放で、笑っていることによって不吉な何かから逃れようとする感じ。それは多分、身近に迫ってくる滅びの予感ではなかったか。あの豪傑笑いの陰には、迫り来る死への恐怖がにじんでいたと、私は思った。
一番下の妹、ごうのあどけない仕草に笑い、まだ幼い小姓の微笑ましい失敗に笑い、私と中の妹、はつとのたわいないケンカに笑い。
残り少ない人生の貴重な日々を、家族みんなで笑って過ごそうとの、勝家さまの暖かい配慮が感じられた。強面の老武者勝家さまは、見た目とは違い、人情に厚く思いやり深い方だった。母と私たちは、一日一日を精一杯楽しもうとしていた。こんな日がずっと続けばいい。永遠にこうして過ごしたい。幼い日、長浜城の落城を経験していた私には、この穏やかな日々の向こうに、破滅が見えていたけれども。
清洲城での秀吉と勝家さまの約定はあっさりと覆され、北ノ庄城めがけて秀吉軍が押し寄せてきた。両軍は賎ヶ岳で激突した。
しかし、頼みの前田利家が突如豊臣側に寝返る。味方は総崩れとなり、敗走の途中に逃げ出す者も多くいた。
勝家さまは、わずかになった敗残の兵と共に北ノ庄城へ引き返してきた。
「秀吉と利家にしてやられた。二人とも、若い頃からわしが目をかけて育ててやったのに。なんと恩知らずの者たちだ」
母の待つ居室に、武具を身につけたまま現れた勝家さまは、母の顔を見るなり悔しげに吐き捨てた。
母は黙って聞いている。その顔には微塵も動揺がない。それどころか口元にはかすかに笑みさえ浮かべている。
「秀吉が攻めてくるまで、あとどれくらいの猶予がありましょうか」
「二、三日と言うところだろうか」
「まだ時間がありますね。この世の名残りに、皆で別れの宴をいたしましょう。皆に城中の食料と酒を振舞って、これまでの苦労を労いましょう。宴では勝家さまもひとさし舞ってくださいませ」
不思議なことに、母の表情は晴れやかだった。迫り来る破滅を、まるで待ち望んでいるかのように。
その時の母を、私は今でも思い出す。菩薩にも似た安らかな微笑みと、上機嫌さ。周囲の家臣たちや女中たちのうろたえた様子と、真反対なのだ。
「お母さまは何がそんなに嬉しいのでしょうか」
私は不思議なものでも見るように、母を眺めていた。
食料庫が開けられ、酒蔵から全ての酒が運び出された。負傷した兵士たちは、その傷跡をボロ布で縛っただけという応急手当てで、宴会の場に座っていた。
塩漬けの魚、漬物、味噌煮にした野菜、握り飯。そんな食事だったが、皆よく食べた。酒も大いに飲んだ。
「この世の名残りじゃ。遠慮せずにいただこう」
「ああ、すべて空になるまで飲んでよいぞ」
勝家さまの言葉に、侍も足軽も侍女たちも、入り混じり盃を交わす。中にはそっと目配せをして侍女の手を引き、消えていくものもあった。
勝家さまは、酔いに酔っていた。足元がふらつき、ろれつが回らない。それでも、謡いながら舞い続けている。
一番手柄は 誰ぞ
褒美を つかわすぞ
金銀砂子に 見目佳きおなご
持ってゆけ 持ってゆけ
そのうちに、勝家さまはよろけながら母の前に座り両手をついた。
「市さま、申し訳ない。あなたを幸せにすることができなかった。天下人の妻にして差し上げようと思ったのに。こんなことになってしまった」
いつのまにか勝家さまの目から、涙が溢れている。鬼柴田は、悔し泣きをしていた。
「秀吉め。決して許さぬ。あの世に行っても、祟り続けてやる。おぼえておれ」
そう言い終わると、その場に崩れるように横たわり、そのまま眠り込んでしまわれた勝家さまに、母はそっと上掛けをかけた。
「良いのです、良いのですよ。誰のせいでもありません。これがわたしの定めだったのです」
そして、広間にいる皆に聞こえるよう大きな声で言い渡した。
「これで宴は終わりじゃ。明日の戦に備えてもう休みなさい」
凛とした声だった。乱れた座に一瞬で緊張が走る。そうだった、今は戦のただ中。明日にでも、秀吉軍が攻めてくる。皆は夢から覚めた人のように、うなだれてぞろぞろと持ち場に去った。
広間には母と眠っている勝家さま、私、妹二人、何人かの近習が残った。私たちは、母の周りに集まる。
「母上さま、私たちも明日には殺されるのでしょうか」
中の妹、はつが不安げな声で尋ねる。
「そうかもしれません。いえ、そうなるでしょう。武家の娘らしく覚悟を決めなさい」
「嫌です。死ぬのは、痛いのは嫌です」
下の妹ごうが、なきベソをかく。
その時の私の気持ちはどうだったのだろう。生きていたかったのか、いたくはなかったのか。母のいうように、これも自分の定めと諦めていたのか。
「いいえ。ここで皆で死にましょう。そして」
母の言葉は途切れた。私は、母の心の中を思った。きっと、父長政の元へ行きたいんだわ。
あの時小谷城で父と共に死ねなかったから、今度こそ死んでしまいたいのだ。
私は、母という女性の怖さを感じた。勝家さまと夫婦になったのも、いずれこうなる予感がしたから。お母さまは死に場所としてここ北ノ庄城を選んだのだ。
「お父さまの元へ。みんなで」
私の言葉に、母が頷く。
その時勝家さまの声がした。
「お市さま、それはいけません」
勝家さまは身を起こすと、静かに言葉をつないだ。
「姫たちには、未来があります。道連れにしてはいけません」
「でも、残していくのは不憫です」
「いや、ちゃちゃさまはもうじき十四。お嫁いりをしてもよいお年頃。姫さまたちの、将来を摘んではいけません」
お嫁入り。私の頭に氏郷さまの顔が浮かんだ。嫌だ。死にたくない。一目でもいいから、氏郷さまにお目にかかりたい。会って、そして……。
「ちゃちゃは、どうなのです」
母の、美しい切れ長の目が私をじっと見つめる。私は自分でも思いがけないほど、きっぱりと答えた。
「私は、生きたい。生きて、生きて、生き抜きたい」
「そうですか。」
母は、どこか安心したように深く頷く。
「では、妹たちを頼みますよ」
「はい。きっと」
私は母の手を握り、深く頷いた。生きたい。生き抜きたい。生きてあの方にお目にかかりたい。私の心に深く沈んでいた願いが、私を突き動かしていた。
その夜は、勝家さま、お母さま、私たち皆で一緒に休んだ。目前に敵が迫っているというのに、母と勝家さまはぐっすりと眠っていた。もう、覚悟が定まっているからだろう。
私はなかなか眠れなかった。お母さまがこの世からいなくなっても、生きて、生きて、生き抜くのだ。そうして、もう一度氏郷さまにお会いし、この胸の内を聞いてもらうのだ。
そう決心したら、合戦の怖さや母と別れる悲しさは薄らぎ、何か楽しい冒険の旅へ出発するような気分になっていた。
夜明けとともに城門近くで鬨の声が上がった。敵はもう目の前まで迫っている。味方の兵たちはすぐさま跳ね起きて防戦したが、あっという間に城門が破られ、敵兵が城内へ押し寄せてきた。
罵声、鉄砲の音、刃のひらめき、断末魔の呻き声。小谷城落城の時と同じ光景が繰り返される。覚悟はできていたとはいえ、私は恐怖に震えた。妹たちも、目をつむったまましがみついてくる。
「お母さま」
私は、思わず母を呼んだ。
「しっかりなさい、ちゃちゃ」
白装束に着替えた母は、静かに微笑んでいた。
「これからはあなたが母代わり。妹たちを頼みます。もうじき、秀吉の使いがあなたたちを迎えにきます。見苦しくないようにふるまうのですよ」
母はいつも髪にさしていた鼈甲の櫛を、私の髪にさしてくれた。
「この櫛は織田家に代々伝わるもの。きっとあなたを守ってくれます」
そして私たち一人ひとりを抱きしめた後、母は静かに勝家さまが待つ天守閣に登って行った。
煙と炎が迫ってくる。もう戦っている兵はいない。周囲が奇妙に静かになった。聞こえるのは、炎が爆ぜる音だけ。その音は次第に近づき、熱い空気が周りを取り巻く。
誰も私たちを迎えに来ない。このままここで、炎に巻かれ死んでしまうのではないか。私は心底恐怖にかられた。
妹たちを脇に抱えたまま、熱風と恐ろしさで気が遠くなりかけた時、遠くから私を呼ぶ声がした。
「ちゃちゃさま、どちらですか。迎えにきました」
私は正気に返った。聞き覚えのあるあの声。まさか、空耳ではないでしょうか。
「ちゃちゃさま、返事をしてください。私です。氏郷です。お迎えに参りました」
私は跳ね起き、声の限り叫んだ。
「氏郷さま。ここです。ちゃちゃはここです」
煙と炎をかいくぐって、一人の武将が現れた。焦げた甲冑、頬には切り傷の痕、肩当てには折れた矢が突き刺さったまま。でも、その顔は紛れもなく氏郷さまだった。
私はその胸にしがみつく。
「怖かった。とても怖かった。このまま死んでしまうのではないかと」
氏郷さまの家臣が妹たちを背負い、城からのがれ出る。私は氏郷さまに手を引かれ、その後に続いた。
城門を出て間もなく、天守閣から火の手が上がり轟音とともに崩れ落ちた。夕暮れの薄暗闇の中、炎は天を焦がし、やがて消えた。
お母さまが逝ってしまわれたのだ。お父さまの元へ。私はただ、立ち尽くしていた。
「同じだわ。あの時と。長浜城でお父さまが亡くなられた時と」
氏郷さまは、片手拝みで「南無法蓮華経」と繰り返し唱えている。
「さ、ちゃちゃさまも」
私も震える声で、唱和する。
「お母さまが、父上に会えますように。永遠に二人で幸せに暮らせますように」
焼け落ちた天守閣から立ち上る白い煙が、いつしか大きな白鳥の姿に形を変えた。
天空のどこからか、美しい白鳥が舞い降り、誰かを呼ぶように鳴く。その鳴き声に応えるように、もう一羽の白鳥が寄り添う。
二羽の白鳥は、私たちのいる上空を一周すると、やがて湖の方角へと飛び去った。
やはり。と、私は思った。お父さまが迎えに来られたんだわ。
「お母さまどうかお幸せに。でも、私は生きたい。生きて愛する人のそばで過ごしたい。どうか、見守ってください」
急に冷たいつむじ風が舞い、空は黒雲に覆われた。大粒の
雨が降り始め、豪雨は一晩じゅうやむことはなかった。
「鬼柴田の怨念じゃ。こわやこわや」
私たちの仮の宿舎となった古刹の小僧さんたちが、声を潜めて噂していた。
天下人となった秀吉は、私たち三姉妹を手厚く保護してくれた。贅沢な暮らしをさせてもらっても、私はちっとも嬉しくない。豪奢な衣装も、調度品も、贅をこらした毎日の食事も。
私の心はもう何も、感じなくなっていた。全てがどうでもよく思えてきた。笑うこともなく、泣くこともなく。ただ、湖に浮かぶ笹舟のように、あてどもなく、さまよっているだけ。
私の隼別皇子は、いつ現れてくれるのかしら。私も好きな人の腕に抱かれて、女鳥姫のように死んでいきたい。そしてお父さま、お母さまたちといつまでも幸せに暮らしたい。戦乱の絶えないこのうつせみの世は、私には辛すぎる。
そして今日は、秀吉と一緒の輿に揺られている。さっきから、私の顔をまぶしげに盗み見る秀吉の目が、鬱陶しくてしかたない。