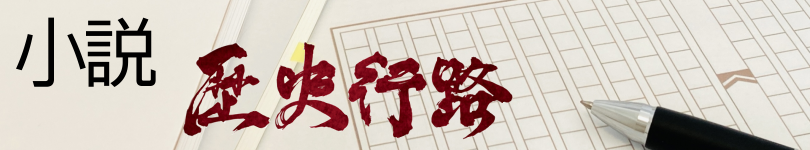西山ガラシャ
1
名古屋城下、長島町の角地に貸本屋「大惣(だいそう)」がある。「胡月堂(こげつどう)」という屋号があるのだが、主の大野屋惣八(おおのやそうはち)の名を略して、大惣の名で呼ばれることが多い。
文政三年(一八二〇)の初夏、 十一歳の小田切伝之丞(おだぎりでんのじょう)は、借りた本を風呂敷に包んで、大惣へ返しに行った。借りる本はいつも、高力猿猴庵(こうりきえんこうあん)の絵入り本と決まっている。名古屋の祭や見世物、東海道の宿場町を描いたものなど、どれもこれも伝之丞のお気に入りである。
伝之丞は、絵師になりたいと常々思っていて、猿猴庵の絵をひたすら模写し、描き方を学んでいる。昨日は東海道吉田宿の宿場町の絵を模写した。手前の道幅は広く、奥へいくほど狭く描く。道の両側に立ち並ぶ本陣、問屋場、旅籠屋などの建物も手前は大きく奥は小さく描く。すると、一筋の道がはるか遠くへ続いていように見えることを覚えた。次も、別の宿場町の絵入り本を借りるつもりだ。
伝之丞は、大惣の暖簾をくぐり、土間で履物を脱ぎ畳に上がった。
店は壁に沿って背の高さほどの書棚が並べられ、書物が平積みになっている。店の裏には二棟の書物蔵があり蔵書数は一万冊を下らない。
伝之丞は書物の匂いが充満した大惣が好きである。妙に落ち着く。大惣で一日じゅう本を読んでいる人の気持ちがわかるような気がしている。
帳場に座っている主の惣八の顔を見ると、少し緊張する。
「いらっしゃい」
声を掛けられた。伝之丞は惣八のところへ寄り、藍の風呂敷を解いて借りた本を返却する。
「次は、馬琴の八犬伝など読んでみたらどうだい」
先日断ったのに、また曲亭馬琴を勧められた。主の惣八は、馬琴に心酔しているのだ。
「また猿猴庵さんの東海道の本を借りたいです。模写をしているので」
借りる予定の猿猴庵本は、駿河や相模あたりの宿場も網羅されているはずだ。早く品川や日本橋まで載っている巻も見たい。江戸を知りたい気持ちもある。
「ほう。また猿猴庵さんの本か」
伝之丞は模写した絵を持参してきたので、惣八に見せた。
帳場にいた常連客の虎二郎も絵を覗き込んだ。以前にも惣八と虎二郎に絵を見せた記憶がある。
「ますます腕を上げたじゃあ、ないか」
「絵師になりたいんです」
「絵師ったって、伝之丞さんは小田切家のご嫡男だから、元服して、いずれは立派なお侍になるだろうよ」
丸顔の惣八は、目も鼻も丸っこいが、額にも目尻にも深い皺がある。
「猿猴庵さんだって、お侍だと聞きました」
実際、高力猿猴庵は三百石取りの侍だ。
惣八の隣で、虎二郎が少し頭を傾けた。虎二郎は近所のご隠居で、大惣の筆耕の仕事も請け負っているらしい。
「猿猴庵さんの生き方を真似すると、お父上が嘆くぞ。わしは猿猴庵さんほど、堂々と芝居や見世物を見に行く侍を、ほかに知らん。祭の日には、町人をかき分けて沿道の最前列を陣取って、見てござっせる」
「もっとも、祭の絵を描いてくれと頼んだのは、わしだけどさ」
惣八が苦々しく笑った。
「武家の矜持なるものを、猿猴庵さんは持ち合わせておるだろうか?」
虎二郎がちらりと惣八を見た。
「たまに思い出す程度でない? 日頃は侍だってことを忘れておると思う」
「まあ、泰平な世だで、それでもええわなぁ」
「武より文の人だし」
尾張名古屋の風土は、なんでも許されてしまう微温湯(ぬるまゆ)のような馴れ合いの部分がある。なあなあの和みは、大惣にも少なからず漂っている。
江戸の貸本は見料を取ると聞いた。貸本屋が本を背負って得意客を回るらしい。大惣は酒や化粧品や硯などを売っているが、貸本の見料は不要だ。貸本は、主の道楽でもあるのだ。
虎二郎が体の向きを変えて、伝之丞の顔をまっすぐに見た。
「猿猴庵さんってやね、すこぶる目がよくてな。一町ほど離れたところにある高札の文字を、すらすらと読むのよ。わしは一緒に歩いておって仰天したね」
「へぇ。だからこんなに細密に描けるのかな。虎二郎さんは、猿猴庵さんとお知り合いですか。猿猴庵さんに会ってみたい」
貸本屋では本を介して老若男女、侍も町人もご隠居も子ども一緒になって交流するものだから、出会いも多い。
「近々、猿猴庵さんが来る予定だから、伝えといてやるよ。弟子にしてもらえばいい」
伝之丞は惣八の言葉が嬉しく、猿猴庵に会えるかもしれぬと思うと胸が高鳴った。
「猿猴庵さんは、いつ来られるんですか」
「もうすぐ原稿ができるっちゅうとったから、二、三日のうちにはきっと来るだろう。来訪は晩が多い。店頭の置き行灯を点ける頃に飛び込んでくる」
大惣は、単に本を貸すだけでなく、文人や絵師を抱えて本作りもしている。
「猿猴庵さんに会えるまで、明日から毎日、夕方に来ます」
伝之丞は明言し、そのあとで尋ねた。
「ところで猿猴庵さんの、猿猴(えんこう)ってどういう意味ですか」
「猿のように毛むくじゃらの河童のことだ」
架空の生き物であるらしい。
「猿猴は、この世に存在していますか」
「おるよ。猿猴はときどき女に化ける。近年、堀川の桜が咲く頃、妙に女性の花見客が多いのは、猿猴が化けた女が何人か混じっておるからだ」
さきほどまで、てきぱきと奥のほうで本の整理をしていた惣八の息子が急に近寄ってきて、伝之丞の耳元でささやいた。
「親父の話は、半分は嘘だと思って聞いて」
息子の囁きが聞こえたのか、惣八は、かかかっと高らかに笑った。
2
翌日。日没よりもだいぶ早い時間から、伝之丞は「大惣」の周りをうろついていた。
猿猴庵らしき人物が大惣の店内に入っていったが、伝之丞は緊張して、店に入ることができずにいる。店の裏へ行き、書物蔵と店とを結ぶ勝手口からこっそりと店内の様子を眺めていた。風を通すために、いつも夏場は勝手口が開いている。
惣八が猿猴庵と話しているのが見えた。声も聞こえる。
「猿猴庵さんの弟子になりたい子がおりましてね。小田切松三郎さんのご嫡男で、伝之丞という十一歳の子です。知っていますか」
自分の話をしていると気づいて、伝之丞は息をひそめた。
「知らぬ。小田切とは誰や」
猿猴庵は尋ねながら、風呂敷を解いて紙の束を取り出した。大惣から頼まれていた原稿だ。
「尾張徳川様のご家臣で、馬廻組のお侍です」
「馬廻組なぁ。知っとるような、知らぬような」
「あれ、猿猴庵さんも馬廻組でしょう?」
惣八が問う。
「わし、人の顔はよう覚えとるけど、名前なんか、覚えぬもん」
原稿は惣八の前に差し出された。
「ああ、原稿をありがとうございます!」
「で、馬廻組の小田切某の倅が、何だ?」
伝之丞は隠れて耳をそばだてている。
「猿猴庵さんの弟子にしてやってください。絵師になりたいそうなので」
惣八は、伝之丞の口からは直接言えぬ願いを、ありがたくもすべて代弁してくれた。
「弟子ったって、十一かそこらの餓鬼なんだろう」
「年の割には、落ち着いた子です。よく店に来ます」
伝之丞は息を潜めて話に聞き入る。
「孫より若い、ひ孫みたいな餓鬼と、果たして何をしゃべってよいかの。わしは、無口な質だから戸惑う」
六十五歳の猿猴庵が、冗談なのか真面目なのか分からぬ声色で話している。
「わしと散々喋り散らかしといて、無口などと、よう仰いますね」
惣八が少々あきれている。
「知らんと思うが、わし、家の中では何も喋らんのよ。倅と孫も、わしに似て無愛想な男での。ときどき倅の嫁が、何か一人で喋っておるだけで、家はしん、としている」
猿猴庵は三十歳で妻を亡くしてから、家族の中で女は、倅の嫁だけだ。
「無口だかどうだか知りませんが、わしと喋るように、小田切さんの子にも話してもらえばいいんです。一度、会ってやってください。何度も申しますが、ただの餓鬼じゃありません。絵の筋がいい。猿猴庵さんのご指南によっては、大成するかもしれません。そしていずれは、大惣でお抱え絵師として仕事をしてもらうという流れになれば、なお幸いと思うております」
伝之丞は、惣八の言葉に飛び上がりたいほど感激した。
「どんな絵を描くんだ」
「猿猴庵さんの作品の模写です。色味も綺麗です」
「模写なんかやめて、自分で勝手次第に描けと言ってやる」
「ええ、何でも言ってやってください。おそらく猿猴庵さんの言葉が力になります。もう少しここにおってもらえば、きっと現れますから」
伝之丞は裏の勝手口の近くから、大惣の正面に歩いた。心ノ臓が高鳴りすぎて、胸がはちきれそうだった。
暖簾を分け入った。
「あ、来た、来た」
惣八が激しく手招いた。
伝之丞は心が逸り、慌てて脱ごうとした草履が足指にひっかかり、草履が飛んでいってしまった。草履は土間に立て掛けてあった「貸本あります」の小さな立て看板にあたって、看板が倒れた。草履を拾いに行って、看板も元に戻してから畳に上がる。
(「年の割には落ち着いた子」と言われたばかりなのに)
伝之丞は胸中で叫びながら、ますます焦った。
「慌てんでも、ええよ」
惣八が笑っている。
伝之丞は胸の内で、(落ち着け、落ち着け)と何度も言い聞かせた。
「小田切伝之丞と申します」
一言、発してみれば、あとはその場の流れに任せるだけだ。
猿猴庵の目が、まっすぐに伝之丞の顔を見ていた。なんとなく目を伏せたくなる。
「わしは今日、今から広小路の見世物に行く。一緒に来るか」
伝之丞は、いきなり猿猴庵に誘われた。
慌てたのは惣八だ。
「ちょ、ちょっと猿猴庵さん。待ってください。いきなり夜の盛り場に連れ出さないでください。まだ十一歳ですから」
「絵を描くとは、描く対象を、よく見るところからはじまる」
「何も見世物の絵でなくても。せめて、昼間の見世物にしてください」
惣八が、なぜか困っていた。伝之丞はなんの迷いもなかった。
「行きます! 今日これから見世物があるのですね。夜の見世物ですか」
「うむ。江戸の産で、狸友(りゆう)という芸人が、百人芸をやる」
「『りゆう』って、どんな漢字を書くんですか」
「狸(たぬき)の友だ」
猿猴庵の低い声が耳に心地よい。
「狸の友がやる百人芸が楽しみになってきました。見世物には行ったことがなく、行きたいです」
話がとんとん拍子に進んだ。
「そなたの父上は、見世物には行かぬのか」
「行きません。武士は、見世物や芝居は見ぬものと言っていました」
「そうかい。わしも武士だがのう」
惣八が、ますます狼狽えはじめた。
「猿猴庵さん。やはり、いきなり見世物に連れていくのは、いかがなものかと、わしは思います」
猿猴庵が眉を寄せ、惣八を見た。
「何がいかんのだ。わしが弟子に見世物の見方、ひいては絵の描き方を教えてやるというのに」
すでに弟子にしてもらえたのかと、伝之丞は猿猴庵の顔を見上げた。頬が大きい。体も大きい。首も太い。堂々としている。
反して、惣八は戸惑いを隠せぬ顔をしている。
「どうしてもとおっしゃるなら、わっし、今から小田切松三郎様のところへ行って、話をしてきますから。絵の勉強のために、猿猴庵さんが伝之丞さんをご自宅に連れて行きました、と。大惣からの帰りに、子が拐(かどわ)かされたかと、ご案じになるといけないので」
「連れていくのはわしの家じゃあないよ。見世物小屋に行くんだ」
「ええ、そのあたりはぼかして小田切様に適当に話しておきますから」
五十六歳年上の師匠と出会った初日に、伝之丞は、人生ではじめての見世物を見た。
3
夜の広小路は、人で溢れていた。店が両側に建ち並び、行灯が通行する人々の顔を明るく照らしている。
見世物小屋は、広小路の東の大須に近いところにあった。
木戸銭を払い、小屋の中へ入る。木の板に緋毛氈が敷かれており、腰をかけた。舞台の両端には燭台が置かれ、火が揺らいでいた。
幕が開く。
畳二畳を横に並べたくらいの奥行きのない舞台で、客席と舞台とが実に近い。
屏風があり、冒頭に講談師が出てきた。
「尾州名古屋の広小路は、今日もたいそう賑わって、千客万来、感謝申し上げまする。本日、百人芸をお目にかけますのは、江戸っ子の狸友でございます。江戸にも両国広小路なる夕涼みの名所がございまして、夏になりますれば、道の両側にはびっしりと店が立ち並び、川遊びの船が漕ぎ出でて、陸も川も賑わうのでございます。見るべきものは、なにはさておき大花火。花火を見ようと両国橋には爪も立たぬほど、人が群衆するのでございます。今日は、そんな江戸の風物詩を尾州名古屋の皆様にご堪能いただきたく、狸友が両国の夏を再現いたします。どうぞお楽しみください」
講談師の声がいい。張りがある。屏風の奥から三味線の音が聞こえてくる。腹の大きな狸友が登場し、舞台の中央に座った。
見世物は、芝居仕立てだ。
女の声がする。狸友が口だけで女の声を真似ているのか、あるいは屏風の後に女がいて声を出しているのか判別できない。
「お客さん、いったいどこからいらしたの」
「尾張名古屋だ」
「ならば、とくと江戸見物などなさるといいわ」
「どこか、名所はあるかいな」
女の声も、男の声も、狸友の声に違いなかった。唇が動いている。一人で何役もこなすらしい。
「江戸の名所は数知れず、中でも大川(隅田川)の花火を見ずして、あの世には行かれぬと、もっぱらの評判ですよ」
「ああ、ならば明日、両国橋に行って花火を見てこよう」
「お客さん、花火は船に乗って見るのがいちばんよ。でも船は人気で、一年くらい前から話を付けておかなければ、とうてい船に乗るのは無理ですよ。でもね、お客さんがどうしても見たいって言うなら、わたしが船宿に話をつけてあげます」
「どうしても見たい。ぜひ頼むよ」
「高いけど」
「いかほど?」
「五百文」
「ずいぶん高いねぇ。ふっかけておるだろう」
「大川の花火は、千両の価値ありと言われているのよ。五百文など安いもの」
「そうかい?」
しぶしぶ銭を払うしぐさをする狸友である。
「ただね。雨なら花火は中止になる。中止になっても払い戻しは、ございません」
「明日は、雨など降らぬだろう」
「てなわけで、男は五百文で納涼船に乗られるよう、女に頼んだ」
狸友が語り役も兼ねている。再び三味線の音色が響いた。
音が次第に小さくなる。虫の音がする。行灯も暗くなったと思ったら、また明るくなった。
鶏の鳴き声がした。狸友が口元だけでまねている。朝だ。
「ほうれ、みろ。俺の日頃の心がけがよいせいで、今日も晴天。雨など天地がひっくり返っても降らぬわさ」
駕籠舁きの声が遠くから近づいてくるように聞こえる。狸友が口の中で音を出している。大八車が通る音、鳥の鳴き声も狸友が一人で口元に手を当てたり離したり、頬をへこませたりして、音を作り出している。
(これが百人芸か!)
一人で何役もこなす。伝之丞はすっかり江戸の雑踏の中にいるような気分になった。
時の鐘が響く。不思議なくらい本物に近いが、狸友が作り出した音だ。
「さて、両国橋に向かうか」
両国広小路の雑踏の音がする。
「お客さん、蒲焼きを食っていかないか」
ぱたぱたと煙を団扇であおぐ。
「ああ、腹がすいたなぁ」
伝之丞は聞いているだけで腹が鳴った。蒲焼きの匂いすら漂ってきそうである。
「お客さん、今日は、ちと雲行きが怪しいねぇ。花火はどうかねぇ」
「何を言うか。こんなにいい天気じゃぁないか」
「西の空がどんより暗くなってきたよ」
狸友が蒲焼き屋と、旅人との声を使い分けている。
伝之丞は、完全に旅人の男に気持ちが同化して、天気が心配になった。
男は、船着き場に急いでいるのか、足音が忙しない。
「雨よ、降るな」
だが、天を見上げ、雨がぱらりときた仕草をする。
顔に悲壮感が漂う。
「せめて花火が見えずとも、川遊びだけはしたい。納涼船に乗るために、五百文も払ったのだ」
雨は無情にも降り出した。遠くから近くへ雨脚が急に強まる。一瞬、弱まったかと思えば、再び強まり、ざあざあ降りとなった。
狸友は、急に着物を脱ぎはじめ、大きな腹を出す。腹を叩くと大鼓の音がする。頬を凹ませ口を叩くと小鼓の音がする。
やがて雷鳴の大きな音が鳴り響き、人々の悲鳴すら聞こえる。
両国橋で花火を待っていた人たちが、一斉に店に雨宿りのため店に駆け込む様子が目に浮かんだ。
三味線の音色もまた、派手に鳴り響き、見世物小屋に緊張と感動が走る。
「あーあ、本当に雨が降りやがった。ついてねぇな。花火は中止か」
「江戸へ来た記念に、両国橋を渡ってやるぜ」
大雨の中、人々の流れとは反対側に向けて、男は歩き出した。
すると、雨が急に小雨になった。
「ここが橋の中央か。すっかり雨は止みそうだ。いや、雨は止んだぞ」
「しばらく川面を眺めていると、一発の花火が高く上がった」
花火の音が、本物の花火の音と、まるで同じだ。連続で花火が上がる音がする。大きな花火の音が聞こえる度に「たまや〜」、「かぎや〜」の掛け声が飛ぶ。
伝之丞は、昨年の夏に見た清須の花火を思い出していた。遠くから見たので小さくしか見えなかった。だが今日は、江戸の両国橋で大きな花火を間近で見ている心地がした。
狸友の百人芸の幕が閉じた。
周りの観客を見渡せば、顔の明るいことといったら、まぶしい程であった。あっちの顔もこっちの顔も、笑い、悦び、楽しんでいる。伝之丞は胸が熱くなった。
気づけば隣に座る猿猴庵が、一心不乱に紙に矢立を走らせている。
何かが憑依しているようで、猿猴庵から熱が発せられているように感じた。
話し掛けられる雰囲気ではない。ただ黙って、小さな紙に描かれる絵を見ていた。
「さて、弟子よ。帰ろうか」
広小路からの帰り道、大きな月が出ていた。
伝之丞は、百人芸を見た興奮が抑えきれずにいた。月を見上げながら、隣の図体の大きな猿猴庵に話し掛けた。
「猿猴庵先生、月が歌い出しそうに見えますね」
月を指した。
「月が歌うだと? 月は歌わん。おまえが歌い出しそうだ」
「歌っていいですか」
伝之丞は猿猴庵を見上げた。
「ええよ。歌いたければ歌え。思う存分歌え」
猿猴庵に促され、伝之丞は妙な節回しの歌を道すがら叫ぶように口にした。何の歌でもない。即興だ。伝之丞が一人で歌って歩いた。
すれ違う人が振り返った。伝之丞は気にしなかったし、猿猴庵も笑って聞いていた。
「猿猴庵先生、わたしは百人芸と同じくらい見物人が喜んで笑い合う顔が印象に残っています」
「見物人の中では、おまえがいちばん喜んで笑っているように見えた」
伝之丞は、ふたたび月を仰いだ。
「おまえ、雅号はすでにあるのか」
猿猴庵が尋ねた。
「『春江(しゅんこう)』です。春夏秋冬の春に、江戸の江です」
「号はいくつあってもよい。春江もよいが、歌月庵喜笑というのはどうだ。歌う月と書いて、歌月庵(かげつあん)。喜び笑うと書いて、喜笑(きしょう)」
「歌う月! ああ先生、月が歌ってます。月が笑ってます」
「おまえがいちばん笑っている」
伝之丞は、歌月庵喜笑の号を使いはじめた。
4
猿猴庵と一緒に百人芸を見てからというもの、伝之丞は急に世の中が明るく見えてきた。大惣の古い畳も、昨日より明るく綺麗に見える。店主の惣八の顔もまた、にこやかに見える。
風呂敷の結びをはずし、借りた本を惣八に返した。
「五冊とも、面白く読みました」
伝之丞は、猿猴庵の著作物はすべて熟読する勢いだ。
「それは何より。伝之丞さん、なんだか愉しそうに見える」
「惣八さん、今日はわたしの芸を見て欲しいです」
伝之丞は、持ってきた荷物をまさぐり、ささっと準備をして風呂敷を自らの掌の上にかけた。百人芸を見てからというもの、芸に興味をもちはじめたのだ。
「何の芸だ」
「今から、風呂敷の中に、生き物を生み出します」
「手妻か?」
すると、風呂敷の中から聞こえた。
***
ギゴギゴギゴ、ギゴギゴギゴ
***
店にいた五人ほどの客が一斉に振り返った。
「蛙?」
「蛙が店にいる!」
惣八が驚いて、伝之丞の風呂敷を取った。
「あっ、取っちゃだめ」
風呂敷の下で、伝之丞は両手に一つずつ湯飲みを握っており、湯飲みの底を擦り合わせて音を出していた。
「くだらんけど、本当に蛙の声に聞こえたわ」
惣八が笑った横で、どこかの豪商の娘と思われる少女が近寄ってきた。
「もう一回やって」
「いいよ」
綺麗な着物をまとった少女が、ご丁寧にも風呂敷を伝之丞の両手の上に被せた。
伝之丞は、懲りずに、ギゴギゴと音を立てる。少女は、「きゃはははは」と笑い声をたてて満面の笑みを浮かべたから、伝之丞も嬉しくなる。
「本当に蛙みたい」
常連のご隠居も、学生も、皆が寄ってきて芸を見てくれる。
「蛙そのものだ」
芸が注目されて伝之丞は有頂天になった。芸人の気持ちだった。
後日、紙で作った亀や人形を、糸を使って歩かせる芸も披露しはじめた。
5
「大惣で、やりたい放題にふざけていた」
そう気づいたのは、二十歳を過ぎてからだ。
五十六歳年上であった猿猴庵は、天保二年(一八三一年)に七十六歳で亡くなった。伝之丞が二十二歳のときであった。
月の下で歌った思い出が甦る。自らの幼さに赤面したくなる。だがあの日、世の中がどんな星よりも、きらきらと輝いて見えたのだ。
大惣に集う人たちは、しばらくは亡き猿猴庵の話ばかりしていた。
「猿猴庵さんは勝手気ままに生きているように見えて、苦悩も抱えておられた」
「息子さんに先立たれて逆を見てしまったのは、お気の毒なこと」
猿猴庵は亡くなる半年前に嫡男に先立たれて意気消沈し、そのあと一気に衰弱してしまったと聞く。
「三十歳のときに亡くされた奥さんを、ずっと愛しておられた。後添えもとらずにね」
少し暗い話になってきたときに、常連客の、虎二郎が口をはさんだ。
「わしは、猿猴庵さんほど幸せな人も、そうはおらんと思うよ。著作は人気で、みんなが猿猴庵さんの絵入り本を求めて大惣にやってくる。そんな幸せな人生、あるかいな?」
「あたしも、猿猴庵さんは幸せだったと思うわ」
近くにいた女の客も、虎二郎の意見に同意した。さらに女の客が惣八に聞いた。
「ねえ、猿猴庵さんが描いていた『名陽見聞図会』はどうなるの?」
流行りの名所案内の本である。
「伝之丞さんに引き継いでもらおうかな」
伝之丞としては、師匠の仕事を引き継ぐことができ、嬉しい限りだった。その日から、名所案内『名陽見聞図会』の仕事に取り組みはじめた。各地を歩き回り、景色を描いて名所案内をつくった。たいそう愉快な仕事であった。
猿猴庵が亡くなった翌年(天保三年)のことである。
江戸から狸友の倅だという、「小狸(こだぬき)」という名の芸人がやってきて、名古屋大須で芸をはじめた。前評判は極めて高く、伝之丞も見に行こうと決めていた。
その矢先、いつものように大惣にて借りるべき書物を物色していると、客が惣八に話しかけているのが聞こえた。
「大野屋惣八さんにお話があるのですが」
「へい。わっしが大野屋惣八ですがな」
帳場にいた惣八が答えた。
「江戸から来ました芸人の小狸という者です。先日から大須で芝居をやっておりますうちに、ちょいと小耳にはさんだことありまして」
客が皆、振り返った。伝之丞もちらりと振り返った。
(人気の芸人の小狸が来た? 狸友の倅か!)
「おやまぁ。小狸さんの評判は、毎日のように耳に入っておりますよ。ご来店いただけるとは、光栄の至り。小耳にはさんだ話とは、狸友さんが描かれている絵入り本でしょうか」
惣八が対応している。
「まさに狸友の百人芸が写生されたという絵入り本です。猿猴庵さんという人が描いたと聞きました」
「たいそう人気なので飾ってあります」
猿猴庵の絵入り本は、店内の文机に置かれていた。
小狸が、背を丸めて文机に進んだ。絵を眺めて、しばし黙り込んでしまった。
惣八が、戸惑いを隠せぬ様子で小狸に寄った。
「お気に召しませんか?」
「右側で三味線を弾く女は・・・・・・」v
「猿猴庵さんからは、元は吉原の芸妓さんだった人と聞きましたよ。狸友さんと一緒に芸をなさっていたのでは」
伝之丞には、三味線の音色の記憶はあるが、吉原の芸妓だった女が弾いていたなどという話は、はじめて聞いた。猿猴庵が作品として余白が多くならぬよう、想像で描いた女だと思っていた。
「狸友は口上の講談師と二人で名古屋に行ったはずです。百人芸は、一人で百人分の役をやるから百人芸なんです。芸妓を連れていったなど、あり得ません」
小狸は主張している。
「ううむ。倅さんの前で申し上げるのも何ですが、大人の男女の事情は子が伺いしれぬ部分もあって、講談師と二人で名古屋へと言いながらも、実は女も旅に同道していたのかもしれませんねぇ」
惣八の話が当を得ているかは、伝之丞には判断つきかねた。
「親父の狸友に、好いたどこぞの女がいても気にはいたしません。だが、ここに描かれた女は、死んだわたしの母に似ている。たしかに母は元吉原の芸妓でしたよ。親父は母を愛していた。だが、母は、父が名古屋へ向かう半年前に死んだんです」
「なんと」
惣八が、あらためて絵を見た。
小狸も、さらに絵を食い入るように眺めた。
「ああ、見れば見るほど、母に似ている」
しまいには、小狸は母の面影を思いだしたのか、目に涙をためた。
伝之丞は立ち上がり、小狸に近づいた。
「実はわたしも十二年前に狸友さんの百人芸を見ました。十一歳のときのことで、うろ覚えですが」
伝之丞の言葉を聞いているのかいないのか、小狸の涙が止まらない。伝之丞が続けた。
「狸友さんは、舞台にお一人でしたよ。前口上の講談師はおられましたが、口上だけで、すぐにひっこみました。ただ、三味線の音は屏風の奥から聞こえていました。三味線の伴奏者が誰だったかは分かりませんが、師匠は図柄として左右に空白が空くのを嫌がり、左に講談師、右に三味線を弾く芸者を配置することで、絵を面白くしたものだと解釈しております。つまり、絵師の、空想上の女が描かれているんです」
小狸は、顔を上げた。
「空想上の女が、なぜ母に似ているのでしょう。絵の作者は母の顔を見ずして、母が描けますか」
伝之丞も惣八もしばし押し黙った。
惣八が先に口を開いた。
「母が恋しいと思えば、別の誰かが母に見える。そういった経験はわたしにもある」
絵を見る側の問題だと言いたげである。
伝之丞は、描く立場からの意見を述べた。
「猿猴庵は見たままを描くのではなく、感じたことを描く人です。狸友さんは、元吉原の芸者の奥さんを愛していた。それが狸友さんの芸に溢れ出ていた。猿猴庵が感じ取って絵に表したということでしょう」
伝之丞の説明に惣八も頷いている。
「猿猴庵は人間をたくさん描くけれども、全員を写生するわけではない。ほとんど猿猴庵が想像した人物ばかりでね」
「猿猴庵さんに会えますか」
小狸が尋ねた。
「昨年亡くなりました。もうすぐ一周忌です」
「そ、そうですか」
肩を落としたように見えた小狸は、踏ん切りが付いたかのように顔を上げた。
「絵の中で母と会えて良かった。大惣に来た甲斐がありました」
小狸は、礼を述べて店を立ち去った。
翌日、伝之丞は大須へ出向いた。小狸の芸を見に行った。
舞台上で、小狸が最初に挨拶をした。
「尾張名古屋の皆様とは、狸友とわたくし小狸が、二代にわたってご縁をいただき誠にありがとうございます。昨日は、名古屋の大惣という貸本屋に行きまして。名古屋の絵師、高力猿猴庵が描いた絵入り本に、わたしの死んだ母にそっくりな女が、狸友の隣に描かれているのを見ました。貧しく苦労ばかりだった母が、体は死んでも魂だけはこの世に残って、きっと父と一緒に名古屋に来たんだなぁと思いました。それを感じ取ってくれた絵師がいたことに、たいそう救われた思いがいたしました」
そのあと小狸は、新内節を歌い上げ、江戸の遊里の男女について語った。
満員の芝居小屋で、隣の男が急に席を立った。腰を低くして、他の観客の膝の前を歩いて出て行った。空いた隣席に、別の男が歩いてきて座った。
さきほど隣席にいた痩せた男とは別人の、大きな男に思えた。
小狸が滑稽な話をするたびに、男が笑う。笑い声に背筋が、ぞくっとする。猿猴庵の笑い方にそっくりだ。
(ああ、一周忌を前に猿猴庵先生が芝居小屋に戻ってきた)
伝之丞は横顔をちらりと見た。暗くてよく見えぬが、師匠の猿猴庵の顔に思えた。
(見える。見えぬはずの人物が、見える。猿猴庵先生の顔だ)
正面を見れば、小狸の隣に狸友がいる。講談師もいる。伝之丞は瞼をぎゅっと閉じてから、再び目を開けた。
隣席には誰もいない。舞台では小狸がなにやら話していたが、亡き師匠の思い出に胸がふさがり、何も聞こえなくなった。
(完)
2023年4月17日改訂版