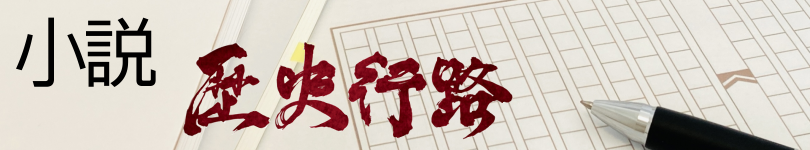飯島一次
ある年の冬、久し振りに蛤町を訪ねると、弥八老人は昼間からひとり盃を傾けていた。
「これはちょうどよいところへいらっしゃいました」
何でも老人の知り合いでしばらく上方へ上っていた人が、帰参の挨拶かたがた一升置いていったのだという。
「おおい、婆さん、熱いとこをもう一本つけとくれ。酒というものはひとりでもよし、また思いがけず訪ねてくれた人に一献差し上げるのも格別心楽しいものでございます」
さっそくに老人の言葉に甘え、差し向かいで盃を重ねることとなった。
「ほう、やはり上方の酒は口当りが違いますね」
老婢は愛想のない無口な人だが、つけてくれる燗はほどよい熱さで、酒は灘か伏見か、あるいは伊丹か、こくのある辛口、喉の奥まで染み渡る。
「わかりますか。昨今は天子様までがこちらにお移りなされ、何かにつけて東都が一番だと言われておりますが、どうして、酒の味ばかりは水が違うものか、まだまだ上方にはかないませんな」
江戸生まれの老人が言うのだから本当だろう。
「とはいえ、わたくし、この歳になって、ようやく酒のまろやかな味わいを楽しめるようになりました。若い時分はもう喉を通りさえすればいいという無茶な飲み方で、味噌か醤油でもあれば肴もいらず、冬でも冷でがぶがぶとやっておりました」
「相当お好きだったのですね」
「好きならば、随分酒を飲むがよし、のまで死んだる義朝もあり。昔の人はうまいこと言いましたな。源義朝という人は下戸だったそうで、それが尾張の野間で討ち死にしたのを引っ掛けた歌です」
「なるほど。野間で死んだと飲まで死んだか」
「男の道楽を飲む、打つ、買うとか申しますが、わたくし手なぐさみも色事もとんと不調法で、ひたすら飲む一方でした」
酸いも甘いも噛み分けた老人のことだから、打ったり買ったりが不調法だったとも思えないが。
「いえ、本当でございますとも。博奕で蔵を建てた道楽者はおりません。わたくしも商売柄、賭場のからくりぐらいは心得ておりますので、馬鹿馬鹿しくて、あんなものに銭は捨てられませんよ。買う方はどうかというと、あれもいろいろと面倒臭いものでして、銭があるからちやほやされるわけでもない。銭を払ってまで気骨を折るのはごめんで、かわで死んだる弁慶の口です」
衣川で死んだ武蔵坊弁慶は生涯買わなかったとか。
「そこへいくと、酒ばかりは何の工夫も才覚もいりません。ただ、目の前のやつをこう飲むだけのことで。うーん、うまい」
「なるほど、その通りかも知れません。さぞお強かったのでしょう」
「さあ、どんなものでしょうか。強い強いとおだてられる者に猛者はなし。自分ではさほど強いとは思いませんね。好きこそものの上手なれとは申しますが、酒好きなのと酒に強いのとはまた別で、わたくしなんぞ、一升も飲めば目の縁が赤くなりました。あなたはお若いから、いくらでも召し上がりましょう」
「いえ、私はどちらかといえば、酒そのものよりも、人と汲み交わし語り合うのが好きなだけでして、ひとりでは滅多に飲みません」
「ああ、それがよろしゅうございますよ。こんなもの、たくさん飲めたからといって何の自慢にもなりゃしない。飲み過ぎれば頭が働かなくなる。愚痴っぽくなって、臭い息を吐いては他人に絡んで嫌われる。物忘れがひどくなる。食べたものをあたりかまわず吐き散らす。足元がふらついて怪我をする。深酒が毎日続くと、顔色がどす黒くなり、手足が痺れ、必ず体をこわします。第一、銭が続かない。百薬の長などと申しますが、どうして、百害あって一利なし、さしずめ、命を削る鉋ですかな。さ、おひとつどうぞ」
「はあ」
「わたくし、昔から深酒はいたしませんで、一度に飲む量を一升と限っております。一升ならば目の縁がほんのりと赤くなって、ああ、いい心持ちで酔った。うまい酒だったと満足して寝ておしまいです。ところがそれを過ぎると、誰かがやめろと止めない限り止まらない。二升も飲むと、変に陽気になって口数が多くなる。三升飲むと、懐具合も忘れてやたら他人に奢ってしまう。五升以上だと、もういけません。あとは一斗飲もうが二斗飲もうが、何も覚えちゃいないんですから、こんな勿体ない話はありませんよ。そこへいくと、酒の粕の匂いだけで酩酊できる下戸が羨ましくなります」
「一斗、二斗といえば、樽でですか」
「いちいち買うのが面倒なので、一度四斗樽を買ったんですが、目の前にあると、いけませんね。あるだけ全部飲んでしまいたくなる。そこを飲まぬが男なりというわけで、歯を食いしばって一升でとどめましたが、それ以後、樽はやめにしました。酒は一升に限ります」
「一升にしても大変なものですよ。毎日一升ですか」
「いやあ、とんでもない。一升酒が毎日続くものですか。いくら好きでも身が持ちません」
「それはそうでしょうね」
「一升飲むのは、まあ、盆正月に紋日ぐらいでございますかな。祭の日、祝いの日、御講に御会式、二十四節気は春ならば立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、夏ならば立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑、秋ならば立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降、冬ならば立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒とございます。あとは花見に月見に雪見に梅見、川開きに虫聞き、紅葉狩り、遊山の日、井戸替えに煤掃き、暑気払いに風邪封じ、初物が入った時、喧嘩の仲裁、町内の葬い。そうそう、毎月欠かせないのが二親の命日、父方母方の祖父母の命日、伯父叔母の命日、死んだ連れ合いの命日、舅姑の命日、世話になった親分の命日にも故人を偲んで毎月一升飲みました。それと雨の日は気分がむしゃくしゃするので一升。あとは、ええっと、何かあったかな」
「今でもそういう日には一升お飲みになるんですか」
「この頃はもう舐める程度で、一升片づけようとすると、暇がかかってしょうがありません」
盃を舐めるようにちびちびと飲んでいる様子からは、かつての酒豪ぶりはうかがえないが、今でもゆっくり時間をかけて一升は飲むというのだから、たいしたものだ。
「人それぞれ分に合った量というのがございまして、それさえ弁えていれば、酒は長寿の薬です。こんないいものはありません。が、今も申しましたように、わたくしの場合、一升を越えると我を忘れ際限がなくなりますので、予め量を決めております。これにはわけがございまして。実は、つい飲み過ぎて御用をしくじったことがございました。世間ではよく、酒の上のしくじりは大目に見てやろうなどと酒飲みに甘い顔をいたしますが、悪い風潮で、酒の上での失態こそ、何よりも慎まなければなりません。量を弁えているうちは人が酒を飲むのですが、度を過ぎると、今度は酒が人を飲みます。人間、酒に飲まれちゃおしまいです。わたくし、商売柄、いつ何どき御用の呼出しがかかるか知れず、前後不覚に酔っぱらって御役目を疎かにするわけにはまいりませんでした。かと言って、飲まないと何となく寂しい。そこで量を決めたのですが、その目安が一升であったわけです」
自己を熟知し、好きな酒にも決して溺れない。弥八老人は並々ならぬ強靱な意志の持ち主だった。旧幕時代に町奉行所の手先として、数々の功績を残したのも当然である。
「酒は一歩間違えば命取りにもなります。立派な才を持ちながら、酒がために道を誤り、不運な最期を迎える人もたくさんおりました。わたくしも、あの時、酒で御用をしくじらなければ、その後も深酒が続き、どうなっていたことか。あの一件は手痛い不覚に終わりましたが、いい戒めでもありました。そうですか。では、今日はひとつ、その時の失敗談をお話しいたしましょうか」
わたくしが三島町で所帯を持ったのが、天保八年の夏、二十四の歳でございます。所帯とは申しましても、三島町の御用聞であった常吉親分の娘と一緒になったわけで、まあ、入り婿です。
御承知の通り、わたくし、最初は神田皆川町の為五郎親分の手下を勤めておりました。まだ見習いの天保三年の五月に例の鼠を捕縛いたしまして、これがことのほか評判となり、為五郎親分には随分と目をかけられたものでございます。
本当のところ、あれは運がよかっただけのこと、勘を働かせて悪事を探り当てたわけでもなく、腕っぷしで悪党を捩じ伏せたわけでもありません。たまたま夜道を歩いていたら、御屋敷の塀の上に黒装束の怪しい人影を見かけましたので、懐の豆鉄砲を食らわせた。これが目の前にどすんと落ちてまいりまして、縄をかけ番屋に引っ立てたら、ぺらぺらと悪事を白状したという次第。まさか、自分が捕らえた盗人が大泥棒の鼠小僧次郎吉だなんて思いもよらず、あとでぶるぶると震えあがったものです。ま、あんなものはまことの手柄ではございません。
三島町の常吉親分から鼠で評判のわたくしをひとり娘の婿にぜひ欲しいとの話が舞い込んだのが、天保八年の夏のこと。鼠小僧の一件以降も、わたくし、為五郎親分の手下を勤めた数年の間、たいしたものでないにせよ、いくつか手柄を立てております。ところが世間というのは派手な鼠の一件しか覚えておらず、いつまで経ってもわたくしを鼠捕りの名人と誉め讃える。
常吉親分は当時、四十五、六でしょうか、まだまだ隠居する歳ではありませんが、娘が二十一になっても行き遅れている。近頃は文明開化の世の中ですから、娘さんが嫁ぐ年齢もだんだんと高くなってまいりまして、二十過ぎようが、三十過ぎようが、四十過ぎようが、四十は大袈裟ですか、ひとりでいても誰も何とも申しません。その当時は娘が二十過ぎてひとり身だと、やれ行かず後家だの、とうが立ったのと陰口を叩かれた時代です。
父親の気持ちとしては娘に一刻も早く婿を取り、孫の顔も見たい。娘の相手は自分が隠居した時、跡目を譲れるだけの見所のある者でなければならない。常吉親分と為五郎親分とは懇意の間柄、そこで鼠捕縛で評判のわたくしに白羽の矢が立ったものと思われます。
わたくしの気持ちでございますか。二親はすでになく、天涯孤独の身の上でしたから、婿にと望まれれば願ったりです。為五郎親分としましては、大事な子分を簡単に手放したくはなかったでしょう。為五郎親分にも娘はおりますが、これが残念なことにまだ幼い。娘の成長を待つわけにもいきません。話はとんとん拍子に進んで、天保八年の六月、わたくし、目出たく常吉の娘お静と祝言を上げました。
お静というのは、わたくしの口から言うのも何ですが、あんないい女房はおりませんでしたね。歳が二十一というのは若くないが、わたくしも当時は二十四ですので三つ違い、釣合いは取れている。初めてお静の顔を見た時はびっくりしました。二十一まで縁がなかったというから、よほど男に好かれない御面相かと思っていたら、その逆で、あまりに美し過ぎて、男が避けてしまったのでしょうか。常吉親分はどちらかというと貧相な目尻のつり上がった狐のような面体でしたが、実の娘であるのにお静は目元はぱっちり、鼻筋はすっきりとして、口元には落ち着いた優しい笑みを湛えております。色白で、首が長くて、錦絵から抜け出てきたような、昔の女にしてはすらりといい体格をしておりました。
見た目ばかりでなく、心根も優しく、頭もいいが決してそれを鼻にかけることもなく、細かいところによく気のつく女でした。これほどの女に今の今まで浮いた噂のひとつもなかったのは、ひとつには身持ちが堅くて男を寄せつけない性分。もうひとつにはお静の母親が早くに亡くなっておりましたので、常吉親分をはじめ、子分たちの世話に追われていたためです。御用聞きの女房としての心得はひと通り仕込まれておりますので、明日からでも間に合います。
為五郎親分にわたくしの親代わりになってもらい、三三九度の盃も無事に済ませました。天保年間は飢饉が続いて米が不足する。米が足りないと当然ながら酒の値が上がり、満足に出回らない。祝言に酒はつきものです。そんな時勢ではありましたが、上等の酒ではないにしろ、この日ばかりは思う存分に飲みました。皆川町におりました頃は手下の分際ですから、滅多に酒など飲めません。それが、祝言の日ばかりは、横に座っている花嫁に対する照れ臭さもあり、次々と勧められるままに盃を干していたら、とうとう天井が回りだし、わけがわからないまま朝になっておりました。
それでも、お静というのはよく出来た女房で、愚痴もこぼさず、迎え酒を勧めてくれるのです。この迎え酒のうまかったこと。わたくしが心底酒好きになったのは、この迎え酒が始まりですかな。
常吉親分も酒が好きでしたね。神田川の河岸にある居酒屋に、わたくし、よく連れて行かれたものです。川で働く人足や船頭がとぐろを巻いている小さくて汚い店ですので、知り合いと顔を合わせる心配がない。それでも土間の空樽は避けまして、屏風で仕切られた畳敷の席に腰をすえ、捕物の心得を聞かされました。子分とは距離を置いて一緒には飲まなかったようですし、お静もまったくの下戸ですから、内心いい酒の相手が出来たと喜んでいたに相違ありません。実の悴のように可愛がってもらいました。
ところが、常吉親分、好きな割りに、そう強くありませんで、三合も飲むとへべれけです。普段は生真面目な一徹者で、子分にも睨みをきかせておりましたが、酒を飲むと分別をなくし、話が回りくどくなりました。
「弥八、おめえは本当にいい男だなあ」
「そうですか」
「そうだよ。おめえのように度胸があって頭が切れて腕の立つ男は、ざらにはいねえ。引く手あまただったろうに、よくぞお静のところへ来てくれた。お静はあんな女だ。気に入らねえことも多いだろうが、どうかひとつ、末永く面倒見てやってくれ。この通り、頭をさげる」
「いやだな。頭を上げてくださいな。お静はあたしには勿体ないぐらいによく出来た女房なんですから」
「おめえ、本心からそう思うか」
「本心も何も、あたしは心底、お静を気に入ってるんです」
「そう言ってくれるのはうれしいが、どうも、傍から見ていて俺は気になる」
「何がです」
「おめえとお静は、その、ちいとばかし、よそよそし過ぎやしねえかい」
「どういうことでしょう」
「夫婦の間のことは、実の親にだってわからねえもんだし、野暮なことは言わねえつもりだが、おめえに跡目を継いでほしいばっかりに、無理やりあんな出来の悪い娘を押しつけて、迷惑だったんじゃねえかと、それが心配の種だ」
「迷惑だなんて、とんでもない。お静は貞女の鑑、出来が良すぎて困るくらいです」
普段は堂々と胸を張って威張っている常吉親分ですが、飲むと気が弱くなるのか、大きな溜め息をついて頭を抱えました。
「ああ、貞女の鑑で困るか。なるほど、皮肉のひとつも言いたくなるだろうよ。おめえ、やっぱり、気がついていたんだな」
「え」
「そりゃそうだ。おめえほど頭の切れる男に隠しだてするのが、どだい無理な話だったんだ」
「何の話かさっぱりわかりませんが」
「とぼけなくたっていいよ。女房が生きてりゃ、目を光らせていたんだろうが、男親だけだと気が回らない。俺の目をかすめて近所の餓鬼と悪戯してやがったのさ」
「まあ、よくある火遊びってやつですね」
「そうとも。お静はおめえの推量どおりの傷物だ。悪かったな。あんな傷物を押しつけて」
世間にはわが子を自慢する親馬鹿というものがございまして、聞かされる方は最初愛想笑いを浮かべておりましても、だんだん顔が強張ってまいりますが、常吉親分はその逆で、飲むと自分の娘の小さな傷をあげつらい、悪し様に申し立てます。もちろん、わたくしだって御用聞の端くれ、女房の傷ぐらい気がついております。幼い頃の火遊びが残した痕ででもありましょうか。左の頬に虫に噛まれたほどのほんの小さな火傷の痕がありました。
「はは、お静は器量がいいんです。あんな傷ぐらい、虫に噛まれたようなもんです。何とも思っておりませんよ。かえって別嬪が引き立ちます」
「はあ、そうかい。そんな風に思ってくれるのか。おめえってやつは」
常吉親分は目頭を熱くしております。
「親の口から言うのも何だが、そのことさえ承知してくれるのなら、あれはどこへ出しても恥ずかしくない女だ」
「その通りですとも」
「さすがは鉄砲の弥八と異名と取るだけの男だ。俺が見込んだ以上の大物だな。若くして名を上げるやつはどこか違うぜ。至らない女だが、どうか、可愛がってやってくれ」
惚気るようで気恥ずかしゅうございますが、お静というのはまったく非の打ちどころのない女房でした。賢くて、気立てがよくて、芯のしっかりした働き者で、姿形はまるで錦絵の美人画のよう、その仕種の色っぽいことといったらありません。
まあ、これほどの女ですが、強いてあげれば、身持ちの堅過ぎるのがただひとつの欠点でございます。身持ちの堅いのが女の欠点になるかどうかはわかりません。そこが並みの堅さじゃないんです。堅いの堅くないの、劫を経た亀の甲羅と申しましょうか。祝言の夜、わたくしがそっと手を握ろうといたしますと、ぴしゃりと叩かれました。
生まれてこのかた色恋沙汰はおろか、男の手も握ったことのない生娘、二十過ぎた生娘というのも乙なものでございます。恥ずかしいのか、男が怖いのか、わたくしと一緒になってからも、なかなか肌を許してはくれません。夜はひとつ部屋に布団を並べて寝ますが、わたくしがそっとお静の方に手を差し込み、柔らかい餅肌を撫でさすろうといたしますと、ぎゅっと痛いほどつねられます。後ろからふっくらとした胸のあたりを抱きすくめようといたしますと、肘鉄を食わされ、いやというほど蹴飛ばされます。力づくで押しても死にものぐるいで押し返されるのが落ち、わが女房を無理無体に手籠めにするわけにもまいりません。堅い石から火の出るたとえもございますから、お静がその気になるまで待とう。夫婦とは申せ、お互い清く正しく、仲のいい兄妹のように寝ておりまして、まるで小野小町を女房にしたようなものです。
「なあ、弥八。気に入らねえ女房でも、冷たくあしらったりしねえで、どうか早く孫の顔を見せてくれ。おめえたちの夫婦仲が悪いと、俺は死んでも死にきれねえ」
「死ぬなんて縁起でもない」
「いいや、今日達者でいても、明日は何があるか。人間、一寸先のことはわからねえもんだ」
わけのわからなくなった酔いどれを相手に口論しても始まりませんので、わたくしも適当に相槌を打っておりますが、こんな親父と差し向かいで酒を飲んだって、ちっともうまくない。そのうち酔い潰れた舅を抱えて家まで帰るのが、わたくしの役目でした。
三島町の家には子飼の手下が四人おり、これら子分たちもひとつ屋根の下で寝起きしております。この子分のうちの三人がわたくしより年長でして、どうやらお静を狙っていたらしく、それがいきなり鳶に油揚、どこの馬の骨ともわからぬ若造にかっさらわれたのですから、面白かろうはずがなく、何かと意地悪く絡んでまいりました。三人固まってひそひそ何かしゃべっている。わたくしが声を掛けても返事もしない。そんな手合いを相手にしても仕方がありません。そんな中でわたくしよりひとつ下の利平という子分だけが、祝言の翌日からさっそくわたくしを若親分、若親分と立ててくれました。
これがまた、目端の利くいい子分でした。御用聞の勤めは親分の器量だけではどうにもなるものではなく、どれだけ子分に恵まれているかで決まります。利平は一見すると、こんな男にお上の手先が勤まるのかというほどの優男ですが、気の回る男で、一度ならず、利平のおかげで命拾いしたことがありました。
鼠小僧の一件以来、わたくし、どこへ行っても女たちからちやほやされましたが、三島町でお静といっしょになってからも、道端で流し目を送る女が後を絶たないのでございますよ。もちろん、わたくし、お静以外の女には目もくれません。そんなある夕暮れのこと、利平がわたくしを脇へ呼びます。
「いったい、どうしたんだ」
「ええ、実は、家の前で若い女から若親分に言付かったんですが」
そう言って差し出しましたのが小さく折りたたまれた文でした。今宵の五つ、玉池稲荷の銀杏の下で待つ、というような文面でしたか。
「おい、利平、若い女ってのはどこの誰だ」
「それが、見たこともない顔でして。ありゃ、素人じゃないな。ぞくっとするほどのいい女でしたから」
「ふうん。ちょっと来い」
わたくし、利平を神田川河岸の居酒屋へ連れ出しました。
「こいつは誰かの悪戯だろうよ」
「そうでしょうか。あの女の目は本気だったがなあ」
「もうその話は忘れろ。お静が心配するといけねえからな。親分にも誰にも言うんじゃねえぞ」
そう釘を刺しまして、酒を飲ませてやりました。お静はよく出来た女房ですから、万にひとつも悋気など起こしませんが、好いた亭主に付け文が届いたと知れば、面白くないに違いない。
「だけど、若親分、隅に置けませんね。今宵、五つ、銀杏の下か」
「馬鹿野郎、その話は言いっこなしだ」
「そうでした。さ、おひとつどうぞ」
この利平、なかなかの勧め上手で、いっしょに飲むうちにいつしかいい気持ちになって、店を出る頃には足元がふらふらいたしました。
「あ、そうだ。俺は用を思い出した。これから少し回るところがあるから、おめえ、先に帰ってくれ」
「へい。じゃ、この提灯をどうぞ」
若い女の付け文なんぞ悪戯に決まっているが、ひょっとして、人に言えない悩みを抱えた誰かが御用聞きのわたくしを頼って内密に相談したいことがあるのかも知れない。悪事の現場を見たのだが、仕返しが怖くて、お上に訴えられないから何とかしてくれとか。そういうことだとうっちゃっとくわけにもいかず、わたくし、玉池稲荷の銀杏の下までまいりました。
思った通り、誰もおりません。そろそろ五つだろうか。もうしばらく待ってみようか、などと思案しておりますと、わたくしの目の前でどすんと鈍い音がいたしました。
これがなんと、大きな唐茄子ほどもある石の塊。どうやら上から落ちてきたらしい。見上げますと、木の上の幹が二つに分かれたあたりに人影が動いておりました。いっぺんに酔いも覚め、得意の豆鉄砲、懐から取り出して投げつけます。
「痛っ」と声があがりました。
「誰だっ。観念して下りて来い」
「わかりましたから、年越しでもないのに豆をぶつけるのはよしてください。足をすべらせちゃかなわない」
聞き覚えのある声だなと思ったら、子分の利平が木からするする下りて来るではありませんか。
「おめえ、何の真似だ」
「すいません。評判には聞いておりましたが、若親分の豆鉄砲がこんなに痛いとは思ってもみませんでした」
「そんなことはどうでもいいや。俺は危うく頭をくだかれるところだった。何だってこんな真似をしやがるんだ。こんな大きな石を」
そう言いながら提灯で足元を照らすと、石の下で何やら動くものがあります。
「あ」
腹を石の下敷きにされながら、三角の頭をひくひく動かせているのは薄気味の悪い蝮でした。八またのおろちの昔から、蛇は酒が好きだと申しますが、わたくしの酒臭い息に引かれて這い出して来たものでしょうか。蝮のごとく嫌われる御用聞きは大勢おりますが、御用聞きを狙うとはあきれた毒蛇です。
「そうだったのか。おめえ、この蝮に気がついて、上から石を落として俺を助けてくれたんだな」
「ええっ、ええ、まあ、そういうことで、すいません。うわあ、こいつは大きな蝮ですねえ」
「おめえのおかげで、命拾いしたよ。それにしても、おめえ、俺がここへ来ることがよくわかったな」
「それなんですよ。若親分と別れてから、何だか胸騒ぎがしましてね。あたしに先に帰れと仰しゃるのは何か子細があってのことだろう。それにしても怪しい付け文。もしや、若親分の身に何か起こっては大変だと思い、先回りして木の上に姿を隠し、様子を伺っておりました。そこから後は御承知の通り。木の上でじっと息を殺していると、若親分が現れ、その足元で何やらしゅるしゅると動くものがある。あっ、蝮だ。そこでとっさに石を投げつけ、退治したようなわけでして」
「だが、そんな高いところにいて、暗がりの蝮がよく見えたな」
「自慢じゃありませんが、あたしは目がいいほうで」
「ふうん。それにしても、そんな大きな石がいい具合に木の上にあったもんだ」
「いえ、これは、もしも、どっかの悪党が若親分に危害を加えそうになった時の用心にと思い、持って上がったんで」
「こんな大きな石、さぞ重かったろう」
「いいえ、若親分のためならこれぐらいの石、何でもありませんや」
ああ、ありがたい。子分が親分を思う気持ち、子が親を思う気持ちに変わりありません。こういう子分こそ、大事にしなくちゃ罰が当たる。その時から、わたくし、利平を弟とも子とも思い、利平もまた、わたくしを実の兄のように慕ってくれまして、どこへ出掛けるにもいっしょについてまいります。
「ふん、そうしていると、まるで御神酒徳利だねえ。仲のいいこと」
滅多なことでは悋気しないお静が、わたくしと利平を見比べて口をとがらせるほど、わたくし、利平を大事にしてやりました。
「おい、弥八、子分の依怙贔屓はいけねえよ」
常吉親分にもよく注意されましたが、わたくしをないがしろにする三人の兄貴株と、若親分と立ててくれる利平とでは、区別するなというほうが無理です。
利平も大事にされればうれしいのが人情、何かとわたくしに気を使ってくれました。その年の冬、わたくしが風邪をこじらせ寝込みました折り、薬になるからと、わざわざ河豚を手に入れ、手ずから台所で河豚汁を作ってくれたのです。手先の器用な男でございましたね。男の手料理などと馬鹿にできません。腕のいい板前はたいてい男と決まっております。
「さ、若親分、たくさん上がって風邪なんか吹き飛ばしておしまいなさいよ」
枕元に河豚汁のいい香りが漂います。布団の上に座り直して鍋を見ると、味噌汁の中で河豚の切り身が手際よく煮えています。
「ほんとは河豚の身を一刻ばかり酒に浸すのがいいんですが、急いでたもんで、そのまま入れました。お気に召すかどうか」
「いいよ。うまそうだな」
「できれば白味噌のほうがよかったんですが、なかったんです。我慢してください」
「白味噌でも赤味噌でも、そんなことはいいよ」
「茄子が手に入らなくて、河豚汁は他の野菜とはあんまり合わないんで、身は河豚だけですけど」
「ああ、いい匂いだ。早く食いてえ」
「そうですか。たくさん召し上がってくださいな」
「おめえは食わねえのか」
「あたしはいいんです。さっき作りながら味見しましたから」
「みんなにも食わせてやってくれ」
「はい、余った分を後で分けます」
「そうか。じゃ、せっかくだから頂こうか」
その時、すっと障子が開き、常吉親分が赤い顔を出しました。
「おうっ、どうした。何の匂いだ」
「あっ、親分、お帰りなさい」
「利平、その鍋は何だ」
「はい、これは」
「あたしが風邪でふせってるもんですから、利平が風邪薬にと河豚汁を作ってくれたんです」
「そうかい。そいつは豪気だ。俺も相伴させてくれ」
「しかし、親分」
「何だ、利平」
「ええっと、これは若親分の風邪薬でして」
「いいじゃねえか。たくさんあるんだ。それより、涎の垂れそうな河豚汁に酒がないのは仏作って魂入れずだ。河豚と言えば鰭酒と 相場は決まってらあ。鰭を焙って鰭酒をつけて来い」
「へい」
常吉親分は外で相当飲んできたらしく、既に出来上がっております。
「こいつはうまいや」
酒飲みは意地汚いと申しますが、常吉親分は目の前の鍋からわたくしの椀に河豚汁をよそい、ひとりでむしゃむしゃと食い始めました。
「寒い時節にはこういうもんがあったまっていい。で、おめえ、風邪はもういいのか」
「まだ頭ががんがんして、胸がむかつくんです」
「きちんと養生しねえといけねえな。熱のある時は梅干しで粥なんぞがいいんだ。こんな生臭えもの食えるのかい」
「ええ、せっかく利平が作ってくれたんですから」
「それはそうだが」
酔っぱらいは自分のことにしか気が回らない。わたくし、早く河豚汁を食べたいんですが、親分はそのことに気がつかず、ひとり美味そうに食べている。婿の立場ですから、わたくし、どうしても遠慮があり、早くこっちにも食べさせてくださいな、とはなかなか切り出せない。利平が来れば気がついてくれるんだが、河豚の鰭を焙るのに手間取っているのか、なかなか鰭酒を持って来ない。ああ、じれったいなあと思いながらも、布団の中で指をくわえて見ているしかありません。
「あ、頭が痛え、痛え」
突然、常吉親分が頭を抱えて呻きました。
「どうかしましたか」
「うええ」
今度は胸をかきむしります。頭が痛くて胸が苦しいということは、わたくしの風邪がうつったものでしょうか。
「ふが、ふが、ふが」
親分はとうとう、その場に倒れ、俎の上の鯉かなんぞのように体をぴくぴく震わせております。酒飲みが酒が切れて手足が痺れるという話は聞いたことがございますが、口まで痺れて何を言っているのか皆目わからないというのは、どうも尋常じゃない。あっ、そうだ。わたくし、親分が食べていたのが河豚汁だと気がつきました。
「大変だあ。お静っ。利平っ。誰か来てくれえ」
わたくしの大声に驚いて、お静と子分たちが飛び込んで来ました。意地汚く病人から河豚汁を取り上げた罰が当たったのか、いや、河豚の毒に当たったのです。
子分たちが常吉親分の口に手を突っ込んで毒を吐き出させようとしましたが、とっくに全身に回っていて、黄色い涎以外に何も出てこない。悪党を締め上げて悪事を吐かせるのが得意の親分も、自分で自分の毒を吐き出せず、とうとう痺れたまま亡くなりました。
河豚という魚は素人が無闇に料理しちゃいけません。利平はわたくしの風邪を治したい一心で、つい河豚汁を作ってくれたのですが、考えてみれば、舅はわたくしの身代わりのようなもの、わたくし自身が一番危なかったのです。河豚のことをよく鉄砲と申します。これは当たると死ぬという悪い洒落です。当たらぬがあるゆえ河豚の怖さかな。世間から、わたくし、鉄砲の弥八なんぞと呼ばれておりましたが、あの一件以来、この歳になるまで、どんなに勧められようとも、河豚ばかりは一度も食ったことがございませんよ。
で、まあ、思いがけなく常吉親分が亡くなり、わたくし、お静といっしょになって半年も経たないうちに三島町の跡目を継いでおりました。祝言の日も酔い潰れましたが、舅の葬いでも、跡目披露の席でも、わたくし、歌を歌うでもなく、踊りを踊るでもなく、ひたすら飲み続けたものです。
子分たちはわたくしの下では面白くないのでしょう。ひとり去り、二人去り、とうとう利平がひとり。もはや大所帯でなくなったので、賄いの婆さんにも暇を出し、家の中はわたくしとお静と利平の三人だけです。
これからは可愛い女房と大事な子分、仲良く生きていこう。そうは思うのですが、どういうわけか、お静と利平はしっくりいきません。相性というものがございますから、無理に仲良くさせようとしても仕方ないんですが、普段はほとんど口も利きません。青白くてなよなよしている利平は御用聞きというよりも商家の手代かなんぞに見えます。これじゃ女に好かれません。
それにしても、お静も少しぐらい我慢して口ぐらい利いてやってもよさそうなものです。わたくしと暮らすようになって半年、未だに肌にも触れさせないほど身持ちが固い、というより男嫌いですから、青瓢箪の利平とは口を利くだけで鳥肌が立つのでしょう。わたくしだっていつも利平といっしょに出歩いているわけではなく、小さな家の中にお静と利平とが二人っきりになることだってありますよ。口も利かない、顔を合わせるのもいやだ。それじゃ、あんまり気詰まりだと思うんですがね。
ところが、このお静、あんまり惚気になるので言いたくありませんが、これほどの女房はおりません。よくよく出来た女でございます。いつだったか、わたくし、八丁堀の旦那に呼出しを受けまして出掛けたんですが、用事が思ったよりもずっと早く片づきまして、ひとりで家へ帰って来た。家の中に人の気配はすれど、お静がおりません。どこへ行ったんだろうと思案していると、二階の利平の部屋で声がする。階段を上って行って戸を開いて、わたくし驚きました。利平が胸をはだけて布団に横になっており、それに覆い被さるようにお静が両手で利平の胸を抱きしめるようにしております。あたりにぷーんと酒の臭い。
「どうしたんだ、いったい」
「ああ、おまえさんかい。実は利平が朝から気分が悪いというので、精をつけるために玉子酒を飲ませて寝かせてたんだけど、さっき呻き声が聞こえてね。何だろうと上がってきたら、熱でもあるのか、真っ赤になって唸っているじゃないか。見たら、全身寝汗をかいて、苦しそうなんだよ。あんまりかわいそうで見ていられないから、今、こうやって汗を拭いてやっていたところなんだ」
「そうだったのかい。利平、大丈夫か」
真っ赤な顔の利平が息を乱しながら喘いでおります。
「ああ、親分、少し、治まってきました」
それにしても、なかなか出来ることじゃありませんよ。普段は反りが合わず、口を利くさえ鳥肌が立つような子分でも、いざ熱を出して唸っているのは見過ごしに出来ず、玉子酒を作って飲ませてやり、親身になって汗まで拭いてやる。まったく見上げた女房の鑑です。
「お静、ありがとうよ。よく汗を拭いてやってくれた」
女房の真心に打たれ、思わずわたくし、その可愛い手を握りしめておりました。お静はわたくしの手をぴしゃりとはねつけて申します。
「やめとくれ、おまえさん、そんな水臭いこと」
このときばかりはわたくし、女房のために、なんとしてでも大手柄を立てたいと心の底から願い、朝まで飲み明かしました。
ところが世の中、なかなか思うようにはまいりません。翌天保九年となっても、大手柄どころか、こそ泥ひとつ捕まりません。旦那方から頂戴するお手当ては月にせいぜい一分、年にすると三両、閏月があっても年に三両一分ですから、とても暮しは立ちいきません。その頃、亀井町に夜な夜な辻斬りが出没するという噂が流れました。
「親分、こうなったら、辻斬りでもひっ捕らえて、手柄にしましょうか」
「よせ、よせ。辻斬りなんて剣呑なだけで、たとえお縄にしたところでたいして銭にはならねえよ」
それでも、利平は熱心に聞き込みをしている様子でした。
「親分、耳寄りな話があるんです」
「辻斬りの正体でも知れたのか」
「いいえ、そうじゃありません。親分の言う通り、辻斬りなんて、銭にも手柄にもなりませんや。それより、松枝町の佐野屋の様子が変なんで、ちょいと探りを入れてみたんですが、どうやらひとり娘がいなくなったようなんで」
「佐野屋のひとり娘というと」
「お夏といって歳は十七、器量自慢で評判の」
「ああ、あの娘か。おめえも岡惚れの口だろう」
「とんでもねえ。あたしなんかにゃ高嶺の花です。それより、顔を出しといた方がいいんじゃないんですか」
佐野屋というのは松枝町の糸屋で、店はそう大きくもないのですが、常吉親分の代からの出入り先です。こういう出入り先からの実入りの方が旦那方からのお手当てよりもよほどよろしゅうございました。
おっとり刀で出向きますと、座敷に通され、病み疲れたような主人の治右衛門が顔を見せます。
「もう、お耳に入ったので。さすがに弥八親分だ。お知らせにあがろうと思っていた矢先でございます」
治右衛門の話によると、娘のお夏は昨日、女中のお種を供に浅草の観音様へお参りに行き、そのままはぐれてしまった。十七の娘が迷子にもなるまいから、女中ひとりが先に帰ったが、いつまで待ってもお夏が戻らないので、昨夜から奉公人が手分けして探しているとのこと。
「どうか娘の行方を探してください。お願いいたします」
他人の不幸を喜ぶわけにはまいりませんが、どうやらわたくしにも運が向いて来たようです。首尾よく娘の居所がわかれば、礼金はたんまり頂けます。さて、どこから手をつけようか。家出か、駆け落ちか、かどわかされたか、神隠しか。いつ何どき、ふらっと帰って来ないとも限らないので、さっそく利平と手分けして聞き込みを始めました。
「親分、お夏はとんでもない娘ですぜ」
利平が糸口を見つけて来ました。
「女中のお種を締め上げましたら、白状しました。娘は観音様へお参りに行ったんじゃねえんで。奥山の茶屋で男と忍び逢っていたようです」
「何だと。で、相手はどこのどいつだ」
「女中が言い渋るのも無理ありません。素性の知れない浪人者だそうで」
「糸屋の娘に浪人か。妙な組み合わせだな。で、そいつの居所は」
「そこまではわかりません。もう少し探ってみましょう」
利平というのは、物腰が柔らかく、どう見たってお店者です。居丈高に十手をちらつかせるよりも、こういう男の方がかえって聞き込みに打ってつけらしく、巧みに話を集めてまいります。おかげでわたくし、利平が集めてきた材料だけで、だいたいのいきさつはつかめました。
「親分、どうやら、相手の浪人の名がわかりました。田宮佐平次といって、播州の出だそうです」
「で、居所は」
「そこが浪人のことで、あっちへふらふら、こっちへふらふら、腰の落ち着かない野郎ですね。ところが、亀井町に近頃珍しい上等の酒を飲ませる居酒屋があり、値段も安く、その浪人、毎晩のように飲みに行くとか」
「上等の酒で値段も安いのか」
「へい」
「今夜からでも張り込みに行こう」
「はい、親分。浪人を取り押さえ、娘の居所を吐かせて、大手柄を立てておくんなさい」
「だが、浪人とはいえ、相手は侍だぜ。いきなりばっさりやられちゃたまらねえな」
「心配ありませんや。昼間から茶屋で町娘と忍び逢う手合いです」
「そりゃそうだが、念には念ということもあらあ。そうだ。俺が客になって飲んでいるだろ。そこへ浪人が入って来る。俺がきっかけを作って酒を勧め、こいつを酔わせて口を割らせるてのはどうだ」
「そいつはいい思案だ。さすがは親分、目のつけどころが違います」
「よし、おめえはもう一度、田宮てえ浪人の人相風体を確かめて来い」
わたくし、日の暮れる前に亀井町の居酒屋へ客として入り込み、浪人が来るのを今か今かと待っておりました。
田宮佐平次といったって、わたくし、顔も知りません。たとえ浪人が入って来ても、そいつが目当ての浪人かどうかわからない。そこは利平が駆けずりまわって田宮佐平次の人相風体を調べあげ、おっつけやって来るはずです。
ぼんやり待っていても間が持ちません。手酌でやっておりますと、どのくらい経ちましたか、背の高い浪人がぬうっと入ってまいりました。歳の頃は三十前後、木綿の黒紋付で、腰に大小を差しております。月代は伸び放題ですが、色の青白い優男です。
ほんの少し後れて、利平が店に入って来ました。わたくしに何やら合図を送ると、黙って外へ出て行きました。
本当にいい子分を持つと幸せです。今回はわたくし、じっと飲んでいるだけで、聞き込みから何からほとんど利平がひとりでやってくれました。出来のいい子分はまさしく百人力です。が、ここからが勝負ですよ。この浪人が田宮佐平次ということはわかりましたが、これに酒をしこたま飲ませ、口を割らせて、娘を救い出すという大仕事が残っております。こればかりは利平では無理で、わたくしの腕の見せどころです。
さて、どうやってきっかけを作ったものだろうか。しばらく思案しておりますと、何を思ったか、その浪人、こちらへずかずかとやって来ました。わたくしの前にずらりと並んだ徳利を眺め、にやにや頷いております。その薄気味の悪いこと。
「貴様、見たところ、いける口だな」
「いえ、それほどでもありませんや」
「そう謙遜するな。まあ、一献参ろう」
こうして鴨が向うから懐に飛び込んで来てくれたんですから、願ってもない好都合で、勧められるまま差しつ差されつ、盃を重ねましたが、その間もこの浪人、にやにやと笑みを絶やしません。
「旦那、やけに嬉しそうな御様子ですね」
「おっ、わかるか。実はいいことがあっての」
いいことがあったとは、お夏を山女衒にでも売り飛ばし、金をせしめたものでしょうか。
「人間、いいにつけ、悪いにつけ、酒が一番じゃ」
「左様でございますとも」
「貴様、話がわかるやつだ」
わたくしと浪人との間にはみるみる徳利が並びました。
「旦那もいける口ですね」
「普段は控えておるのだが、嬉しい時はつい飲みたくなる」
この田宮佐平次、いける口ではありますが、なかなか酔ってくれません。そこで酔いつぶす思案が浮かびました。
「どうです、旦那。わたくしと飲み比べをいたしませんか」
「ほう、面白い。わしは強いぞ。貴様、負けたらいかがいたす」
「失礼ながら、わたくしが負けましたら、ここの勘定を持たせていただきます」
「よかろう」
「旦那が負けたら」
「なあに、わしが負けるものか」
さあ、それから、飲みましたなあ。これが気の利いた家なら朱塗りの大盃なんぞで勝負となるんでしょうが、こんな汚い店ですから、親父に大きめの丼鉢を持って来させて、徳利の酒を残らず注ぎ込み、一気にぐびぐびと飲み干します。
「ううむ。今どき珍しい、いい酒だのう」
浪人は顔色ひとつ変えません。続いて二杯め。
「うまい。これだけ飲んで只になるとは、貴様には気の毒だな」
「なあに、あたしだって、負けちゃいませんぜ」
三杯、四杯、五杯と続くうち、浪人は咳込み、胸を叩いております。
「旦那、大丈夫ですかい」
「いささか風邪をこじらせてな」
「そいつはいけませんね」
「うむ、もう半年も咳が止まらんのだ。体はだるいし、夕方になると微熱が出るのだが、酒さえ飲めば、すっと治まる」
「そうですとも。酒は百薬の長てえくらいです」
六杯、七杯、八杯、九杯と進み、あと一杯で十杯というとき、突然、浪人が丼鉢をばたっと伏せました。
「もういかん。わしの負けだ」
「何です。もうおしまいですかい。口ほどにもない。敵に後ろを見せちゃいけません」
「そう言うな。貴様のように酒の強い男は今まで見たことがない。酒でわしを負かせたのは貴様が初めてだ。わしもまだまだ修行が足りんな」
「人間、いくつになっても修行が肝心です」
「いいことを言う。わしは今日、ようやく先生に認められて、出稽古の口にありついたんだ。これからももっともっと修行に励まねばな」
「励むのは後にして、ねえ、もっといきましょう」
「いや、今の今まで不敗を誇ったこのわしだが、負け方も大切だということが、たった今わかった。これ以上重ねると、とんだ醜態を晒すことになる」
「いいじゃございませんか。醜態ぐらい」
「わしはひたすら、勝つことばかりを考えて来た。しかし、先生はきっぱりと言われたのだ。剣の道に技は不要だと。剣とは所詮、人を斬る道具だ。決して抜いてはならんのだ。道を極めるだけなら、木刀でも竹刀でも同じことだと。さすが、北辰一刀流、江戸一番の千葉先生だ。武士が剣を抜く時は人を斬る時だ。相手を滅ぼし、自分をも滅ぼす。その覚悟がなければ決して剣を抜くべきではない。剣を抜きながら相手を斬らずに鞘に収めれば、それはもう武士とは言えん。博徒の脅しだ。斬らないのなら、最初から抜かなければいいのだ。剣は人なり、酒も人なり。酒も剣と同じことだな。決して酔ってはならん」
酔ってはならんと言いながら、わけのわからない話をぺらぺらしゃべっているところは、かなり回っていると見えます。浪人はごほごほと咳き込みました。
「この歳になって、ようやく真剣勝負の意義がつかめたとは。天下万物ことごとくわが師ならざるはなし。わしは貴様の前で潔く兜を脱ごう。貴様のおかげだ。千葉先生はわしの腕を認めてくだされたが、まだまだ剣の道は奥深い。とりあえず、出稽古の口が決まれば、指南役として仕官も夢ではないがな。どうだ。わしは酔っているか」
「ですけど、これはどっちが先に酔いつぶれるかの勝負なんですぜ。旦那も酔わない。あたしも酔わないじゃ、勝負になりませんや。しっかりしてくださいよ、田宮の旦那」
「田宮の旦那だと。貴様、わしを誰かと取り違えておるようだな」
「えっ、旦那は田宮佐平次様じゃ」
「いいや。わしの名は平手造酒と申すが」
「そいつは、へえ、そうなんですかい。どうも、こりゃ人違いだな。じゃ、あたしはこれで帰ります」
立ち上がろうとしましたが、足元がふらついて、思うように立ち上がれません。
「人違いでも何でもいい。貴様とは馬が合いそうだ。そこまで送ろう」
自分で思った以上に酔っておりました。これじゃ勝負はわたくしの負けです。夢うつつというのか、勘定を払ったのが誰だったかさえ、定かではありません。いつしか、わたくしと浪人は連れ立って外を歩いておりました。
結局、田宮佐平次は姿を見せなかったんだ。この浪人が入って来てすぐ、確かに利平からの合図があったようだが、あれは人違いを知らせる合図だったのでしょうか。いや、それともこの浪人が正真正銘の田宮佐平次なのだが、わたくしを欺くために、平手だか平田だかを名乗っているのか。亀井町の寂しい夜道。そうだ。ここらあたりで最近、辻斬りが出るんだった。そんなことをふと思い出しておりますと。
「危ないっ」
わたくし、突然に浪人に突き飛ばされて、道端に転がりました。次の瞬間、しゅっと耳元に冷たい風が走ったかと思うと、浪人が抜き身を構えて突っ立っております。月明かりに目をこらすと、浪人のすぐ横に何やら倒れている。
「しまった」
浪人が呻きました。
「あれほど戒めておったのに、ついうっかりと抜いてしまった」
何が起こったのか、ようやく、わたくしにもわかりかけてきました。うつ伏せに二人の人間が倒れております。びくともしないところを見ると、最早息をしていない様子。
「旦那、斬ったんですね」
「うむ。背中に殺気を感じて振り向くと、男が二人かかって来た。あっという間のことで、抜いてしまった。剣というものは、抜けば必ず相手が死ぬ。相手が死ななければこちらが死ぬ。どうやら、わしは相当に酔っているようだ。酒のせいだと言い訳はしたくないが、酔ってさえいなければ、抜かずとも、叩きふせるなり手取りにできたものを。一度に二人も斬ってしまうとは、わしの腕はまだまだ未熟だ。未熟な人間は知らず知らずに他人を傷つけてしまうのだなあ」
そう呟くと、浪人は刀の血糊を拭い、鞘に納めました。目の前で人が二人も斬られたんですから、わたくしもいっぺんに酔いが覚め、商売柄、倒れている死骸を仰向けて調べることにいたしました。月明かりに浮かんだ青白い死顔は、ひとりは若い浪人風の侍、もうひとりは町人です。
「旦那、このお侍に見覚えはありませんか」
「さあ、知らんな。人に遺恨を受ける覚えはないが」
「じゃ、こっちの町人の方は。あっ」
驚いたことに、子分の利平ではありませんか。
「どうした」
「これはあたしの子分です」
「貴様の子分、それがどうして貴様に匕首を向けたのだろう」
「あたしに匕首を向けたですって」
利平の手には確かに匕首が握りしめられております。
「そうだ。だからわしはとっさに貴様を突き飛ばし、その時にはもう、刀の柄に手がかかっていたのだ。抜き打ちでこれを払うと、すぐ横で白刃の閃く気配がして、また、あっと思う間もなく人が倒れていた」
「あっと思う間もなく人が倒れていた。冗談言っちゃいけねえ。お前さんが斬ったから倒れているんだ。第一、何で利平があたしに匕首を向けるんです」
「そこまで立ち入ったことは知らん」
「あたしは三島町の弥八という御用聞きで、こいつはあたしの子分なんですぜ」
「貴様、十手持ちだったのか」
「こいつは佐野屋のお夏をたぶらかせた浪人を追っていたんでさ。旦那をその浪人、田宮佐平次と思い込んで、ずっと尾けていたんでしょうよ。ここらあたりは近頃辻斬りが出るという噂だ。そっちで死んでいる侍が何で旦那の命を狙ったかは知りませんが、利平はあたしたちが辻斬りに襲われたのを助けるつもりで飛び出して来たんだ。それをいきなりばっさりとはひでえや」
「いや、しかし、この男の切っ先は確かに貴様を狙っていた」
「いい加減なこと言うない。てめえ、ほんとは田宮佐平次じゃないのか。三島町の弥八を甘く見るなよ」
「何を言うか。わしは平手、平手造酒だ」
「ええい、うるせえや。どういう事情にせよ、人が二人も死んでるんだ。出るとこへ出て申し開きしてもらおうか」
「申し開きでも何でもするが、今宵はひとまず、道場へ帰り」
「てめえ、逃げる気か」
わたくし、威勢よく十手を突き出しました。
「人を二人斬ったのだ。逃げも隠れもせん」
「うまいこと言いやがって、逃がすもんか」
「こら、よせ。よさないか」
あっという間に当て身を食らわされ、あとは何にもわかりません。目を覚ましたのが、先程の居酒屋の店先です。親父が心配そうにこちらの顔を覗き込んでおります。
「おい、おい、そんなところで潰れてちゃ、迷惑だよ」
すると、今のは夢だったのか。わけを話して親父に提灯を借り、夜道を急ぐと、やはり夢ではなかった。道端に倒れている利平と侍を見つけました。利平は腹を横一文字に、侍は肩から胸にかけてざっくりと、それはもう見事な斬り口でした。
こうなったら、わたくしひとりの手に負えません。皆川町の為五郎親分に加勢を頼み、浪人の口にした北辰一刀流だの、千葉先生だのという言葉を手掛かりに、その夜のうちにお玉が池の千葉道場を訪ねました。平手造酒という門人は確かにいるが、外出してまだ戻って来ないとのこと。
利平を斬ったのは、やはり田宮佐平次ではなく、平手造酒という剣術使いでした。ただ、佐野屋のお夏とは何の関わりもなく、その一件については単なる人違いと知れました。
斬られて死んでいた侍の身元がわかりましたが、驚いたことに、この侍こそ、わたくしと利平が追っていた播州浪人田宮佐平次だったのです。しかも、夜毎の辻斬りの下手人もこの田宮で、平手さんははからずも辻斬りを退治したのだから本来ならば誉められるところ、間の悪いことに田宮を追っていた利平も斬ってしまっている。これは間違いじゃすみません。斬られた利平も不幸だが、平手さんにとっても気の毒な結末となりました。なまじ腕が立つばっかりに、あれだけ酔っていても二人の人間を一刀の下に斬り捨てたんです。ひとりは殺されても文句の言えない辻斬りですが、もうひとりが町方の御用聞の手下でしたから、厄介なことになりました。
千葉周作先生に腕を認められ、これから出世という矢先だったのに、平手さんは江戸を出奔し、流れ流れて利根川で博奕打ちの用心棒にまで落ちぶれたと申します。六年後の天保十五年八月、笹川と飯岡の出入りに巻き込まれて命を失ったというから哀れなもんです。あれだけの使い手ですから、出入りではさぞかし大勢の渡世人を斬り殺したのだろうと思うと、そうではなく、胸を患っていたらしく、血反吐を吐いてうずくまっているところを、四方から竹槍で突かれ、刀を抜きさえせず、あえない最期を遂げたそうです。これはわたくしの同業で二足の草鞋を履く飯岡の助五郎親分が江戸に出て来た折り、直に聞いた話ですから間違いございません。
わたくしさえ、もっとしっかりして辻斬りを取り押さえていれば、利平が斬られることもなく、平手さんが江戸を追われることもなかったのです。目の前に酒があると、つい飲み過ぎて、御用をそっちのけにしたわたくしのしくじりです。それに懲りて、わたくし、その後は深酒を慎み、一升より飲まないと決めております。
「それじゃ、行方知れずの佐野屋の娘はどうなったのです」
老人は遠くを見つめ、深々と溜め息をついた。
「それが、見つかるには見つかったんです。押し込められていた田宮の浪宅を命からがら逃げ出して、助け出されました。よほど怖い目に遇ったのか、かわいそうに気が触れたようになっていました」
「どうもわかりませんね。娘はどうして辻斬り浪人なんかと人目を忍ぶ仲になったんでしょうか」
「それが、娘の話によりますと、あの日は観音様へお参りしたあと、本当に女中とはぐれてしまった。人混みに揉まれているうちに、いつしか寂しい場所に出た。それを待ち構えていたかのようにひとりの浪人が現れ、いきなり、手を引っ張って行こうとする。あまりの恐ろしさに、手を振り切って、駆け出すと、すぐそこに若い番頭風のお店者がいて、大丈夫かと声をかけてくれた。助けてくださいと近寄ったとたん、気を失う。どこをどう連れて行かれたのか、気がつくとあばら家にいて、浪人とお店者のふたりに代わる代わるとても口にできないような恐ろしい目に遇わされたと申します」
「その浪人が」
「はい、田宮佐平次です」
「では、奥山の茶屋で惚れた浪人と忍び逢っていたというのは」
「あとで女中にも確かめましたが、利平の早とちりでした。どんなに目端の利く男でも、手柄を焦ると、往々にしてこんな間違いをいたします。が、利平の偉いところは、これだけの間違いを犯しても、ちゃんと娘を連れ去ったのが田宮佐平次という浪人だと調べ上げていたことです」
「その浪人といっしょにいた若い町人は誰でしょう」
「さあ、盛り場に網を張って若い娘を手籠めにする悪党はいくらもおりますからね。悪浪人とつるむならず者でしょうよ。娘は女衒にも売られず、この浪宅に押し込められて毎日ひどい目に遇わされていたのですが、突然、鬼のような女がやって来て、男はもう死んだ。おまえのせいで死んだから、おまえも殺してやると恐ろしい剣幕でつかみかかって来た。首を締められ、もう駄目かと思った時、手元に火鉢があったので灰を女の目に突っ込み、相手がひるんだ隙に逃げ出したと申します」
「その女は何者なんです。田宮佐平次の妻女でしょうか」
「そうかも知れませんが、娘も気が抜けたようになっており、どこまで本当かわかりません。わけのわからないことを申しまして、泣いているかと思うと笑ってみたり、そんなことがあったので、佐野屋も左前になり、やがて潰れてしまいました」
「なんともすっきりしない事件ですね」
「まるで二日酔いのようですな。とんとん拍子に悪事が露見し、悪党がふん縛られるというのは、案外少のうございます。わたくしが酒さえ飲まなければ、もう少し目鼻もついたのでしょうが。手柄を立てられなかったよりも、たったひとりの大事な子分を失ったことが、わたくしには痛手でございました。利平は娘をかどわかした辻斬り浪人を追い詰め、健気にも浪人に斬りかかられたわたくしを救おうとしてふたつとない命を落としたんですから、後にも先にも、こんなよくできた立派な子分はおりません」
「そうでしょうね」
それにしてもすっきりしない。これは老人が語っているような単純な事件なのだろうか。どうも、裏に何か隠されているような気がして仕方がない。
たとえば、一連の事件の発端が常吉親分の頑固さにあるとしたらどうだろう。常吉は一度こうと思い込んだら、誰が何と言おうと決して意見を変えることのない性分だった。その常吉が娘の婿に捕物の名手として名高い弥八を選んだ。ところが、お静にはすでに恋仲の男がいたとしたら。
お静はそれとなく縁談に不承知の意を表すが、父親は気づかない。あるいは気づいていたところで耳を貸さない。そしてとうとう祝言となる。だからこそ、お静は弥八といっしょになってからも、肌を許すのを拒み続けたのだ。なら、お静の恋する相手というのは誰か。これはもちろん利平であろう。だからこそ、みんなの前ではことさら、よそよそしく反りの合わない振りをしていた。
だが、こんな無理がいつまで続くものではないから、やがて、お静と利平は邪魔な弥八を亡き者にしようと、良からぬ相談をする。相手は鉄砲の弥八と異名を取る捕物の名手、まともにぶつかって勝ち目はない。そこで一計を案じ、偽手紙で神社の木の下へ誘い出し、上から弥八の頭めがけて大きな石を落とした。だが、弥八は酔ってふらふらしていたから、この石はわずかに外れて、かえって弥八を狙っていた蝮を潰してしまった。
次に企んだのが河豚による毒殺。これも血みどろの肝をたっぷり混ぜたせっかくの河豚汁を舅の常吉が横から食べて死んでしまったために失敗に終わる。
ちょっとやそっとで倒せない手強い相手だ。そこにたまたま起こったのが亀井町の辻斬り事件。これを探るうちに、目の寄るところへ玉が寄る。利平は辻斬りの浪人、田宮佐平次と知り合い、小悪党同士で意気投合して、佐野屋の娘をかどわかし、これを餌に弥八を居酒屋におびき寄せ、田宮が斬り捨てようとの魂胆。悪知恵の働く利平のことだから、弥八を斬った田宮を今度は自分が取り押さえるなり、突き殺すなりして、手柄を立てるぐらいは考えていたかも知れない。
ところが、どうした手違いか、弥八は田宮に出会う前にたまたま酒を飲みに来ていた平手造酒という浪人と知り合い、これを田宮だと勘違いする。田宮と利平は酔った二人が出て来るのを尾け、寂しい場所で斬りかかるが、腕の格段に勝る平手に一瞬にして斬り殺されてしまう。
いや、これはあくまでも事件をすっきりさせようとする私の突拍子もない空想で、真相は弥八老人の言う通り、すっきりしないものかも知れないが。
「三島町の家もいっぺんに寂しくなりましたよ。一年もしないうちに、舅の常吉が河豚の毒で亡くなり、兄貴株の子分たちが出て行き、利平も斬られ、恋女房のお静までがあんなことになるなんて」
「え、おかみさんがどうかしたんですか」
「わたくしの口から言うのも何ですが、お静は本当に心根の優しい女でした。あれだけ反りの悪かった利平の死を聞くなり、みるみる真っ青になって、泣き崩れたんですから。あれほどまでに狂ったように泣き続けられるものではございません。恋しい亭主を守ろうと命を投げ出してくれた子分のためです。泣くのも無理はないとはいえ、二日経っても三日経ってもしくしくと泣きやまないとは、なんと、心の広い人情の厚い女でしょうか。わたくし、ますますお静に惚れ直しましたよ」
「で、そのおかみさんが」
「そうそう。この年は晩春から初夏にかけて風の強い日が続きましてね。風が吹くと桶屋が儲かるかどうかは知りませんが、ほこりが舞うので眼病が流行って眼医者は儲かります。お静はあんまり泣き続けて目が弱っているところに、悪い砂でも入ったのか、目を悪くいたしまして、洗っても冷やしても痛みが治まらない。そこで日本橋伊勢町にある眼医者へ療治に通っておりました。目を患っている女というのも、また色っぽいものでございます。で、この療治がどうも長引きそうな具合。目が不自由では通うのも大変ですから、たまたまお静の叔母が近くの瀬戸物町に住んでおりましたので、療治の間だけ厄介になることにいたしまして、寝泊まりしておりました。それが四月の大火事で、あの辺一帯が焼けた際に、目の悪いのが仇となり、折悪しく逃げ遅れまして、かわいそうに、わたくしが駆けつけた時には、もう真っ黒焦げとなっておりました」
私は言葉もなかった。これほどの不幸を淡々と語れるとは、老人の中でそれだけ歳月が流れたということだろうか。あるいは、老人もまた、事件の裏にあるどろどろとしたものを嗅ぎつけているのでは。もしかして、弥八老人はお静と利平の仲も、二人が自分を殺そうと企んでいることも、何もかも承知の上で、彼らが自滅するのを待ち、三島町の家と町方の手先としての地位を手に入れた。いや、それは考えすぎか。久し振りに飲み慣れないいい酒を飲むと、空想までが変な方へ向いてしまう。
「その後、後添をもらい、それにも死に別れて、また別の女房を持ったりもしましたが、この最初の女房、お静ほどの女は後にも先にもおりませんでした。あ、こんなことを言うと、他の女房たちが化けて出ますかな」